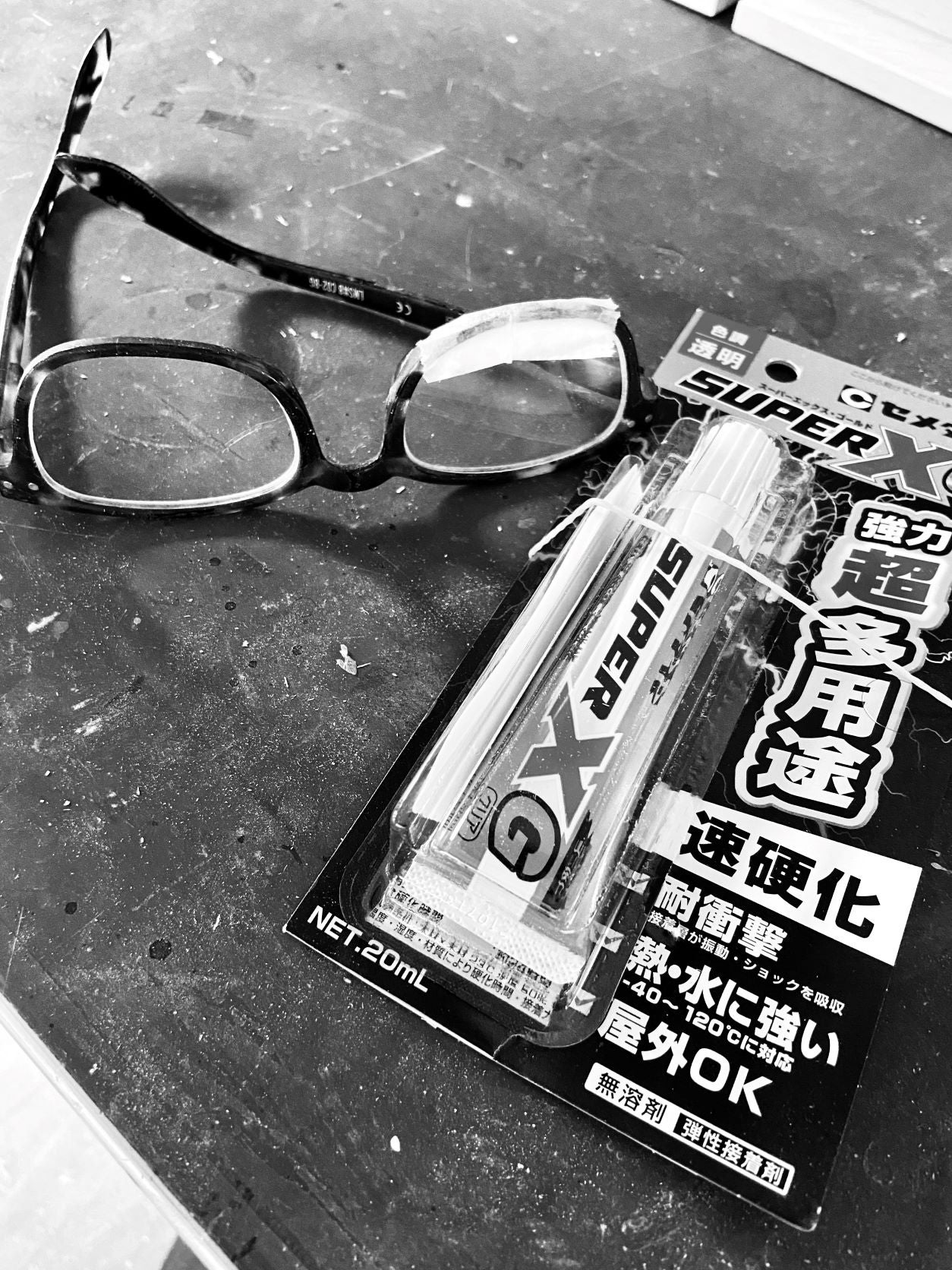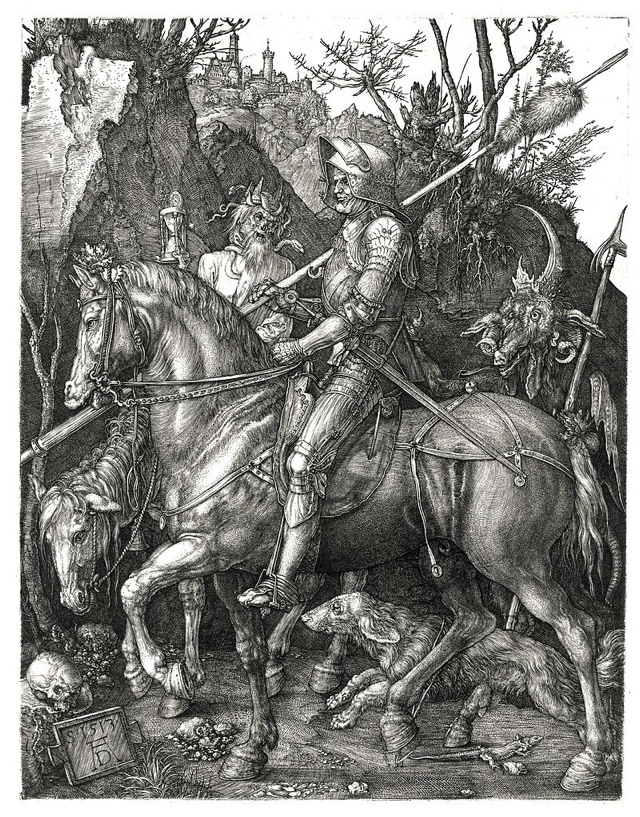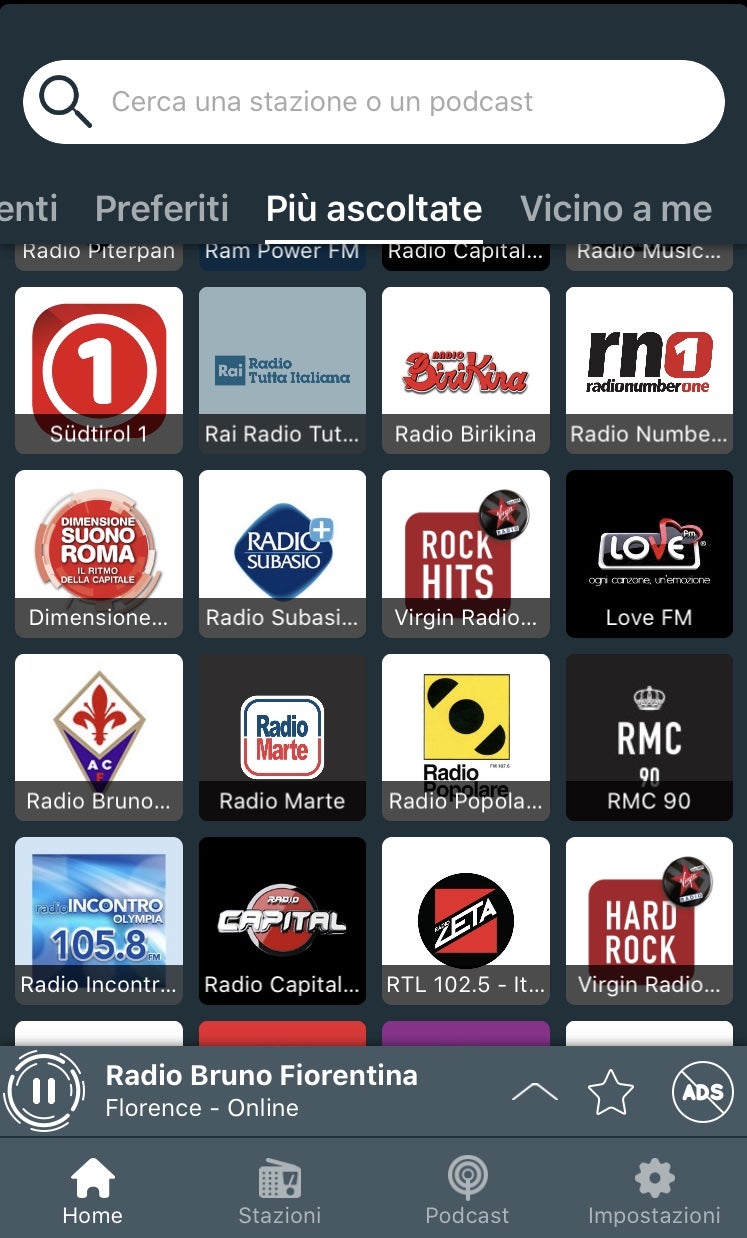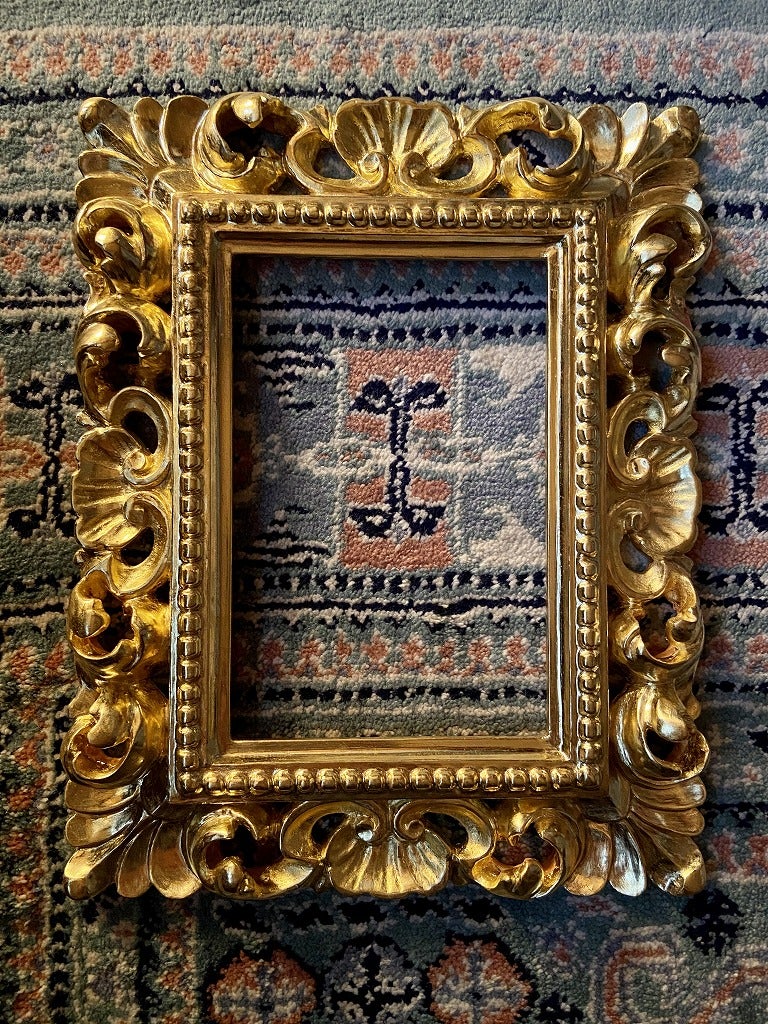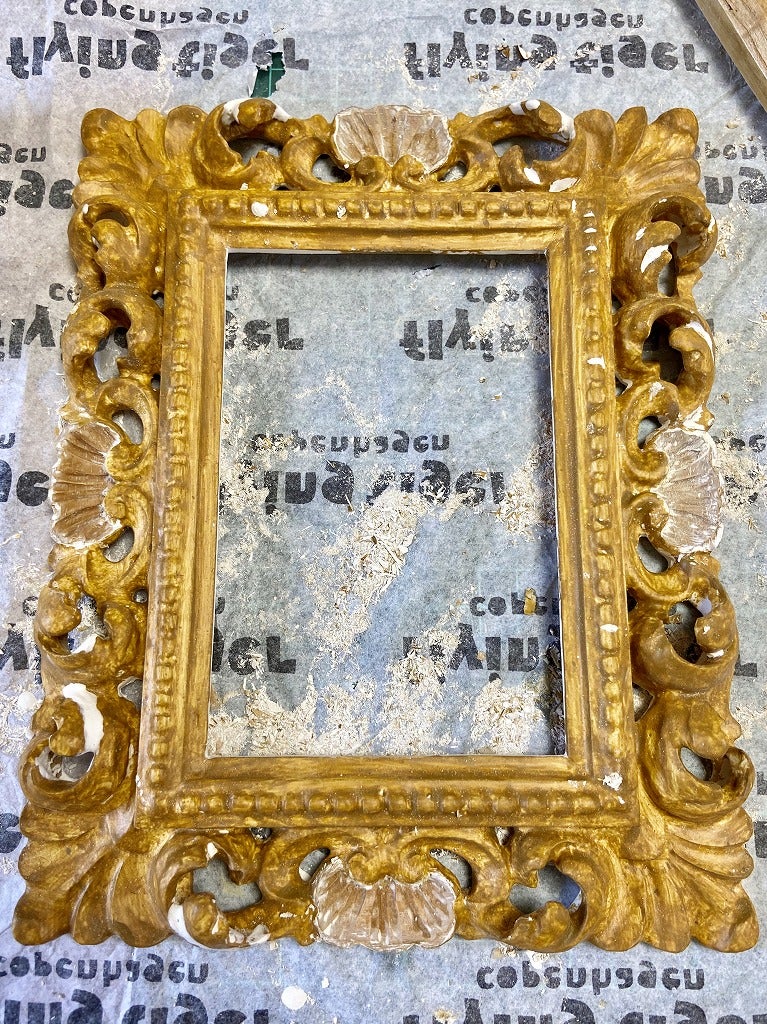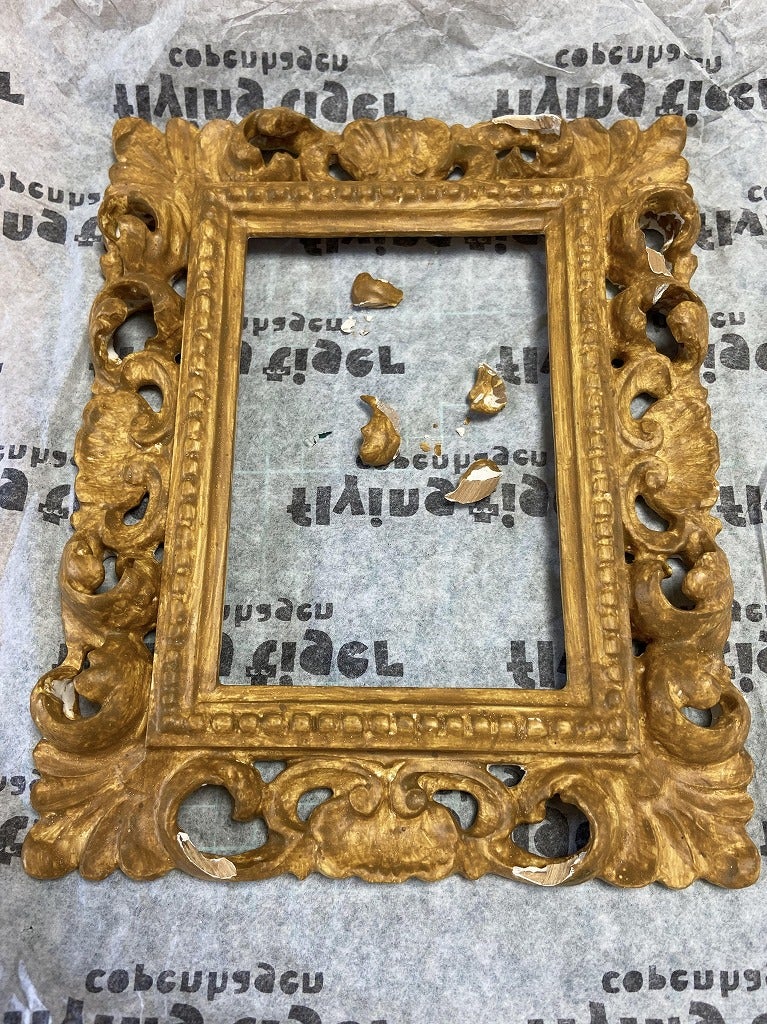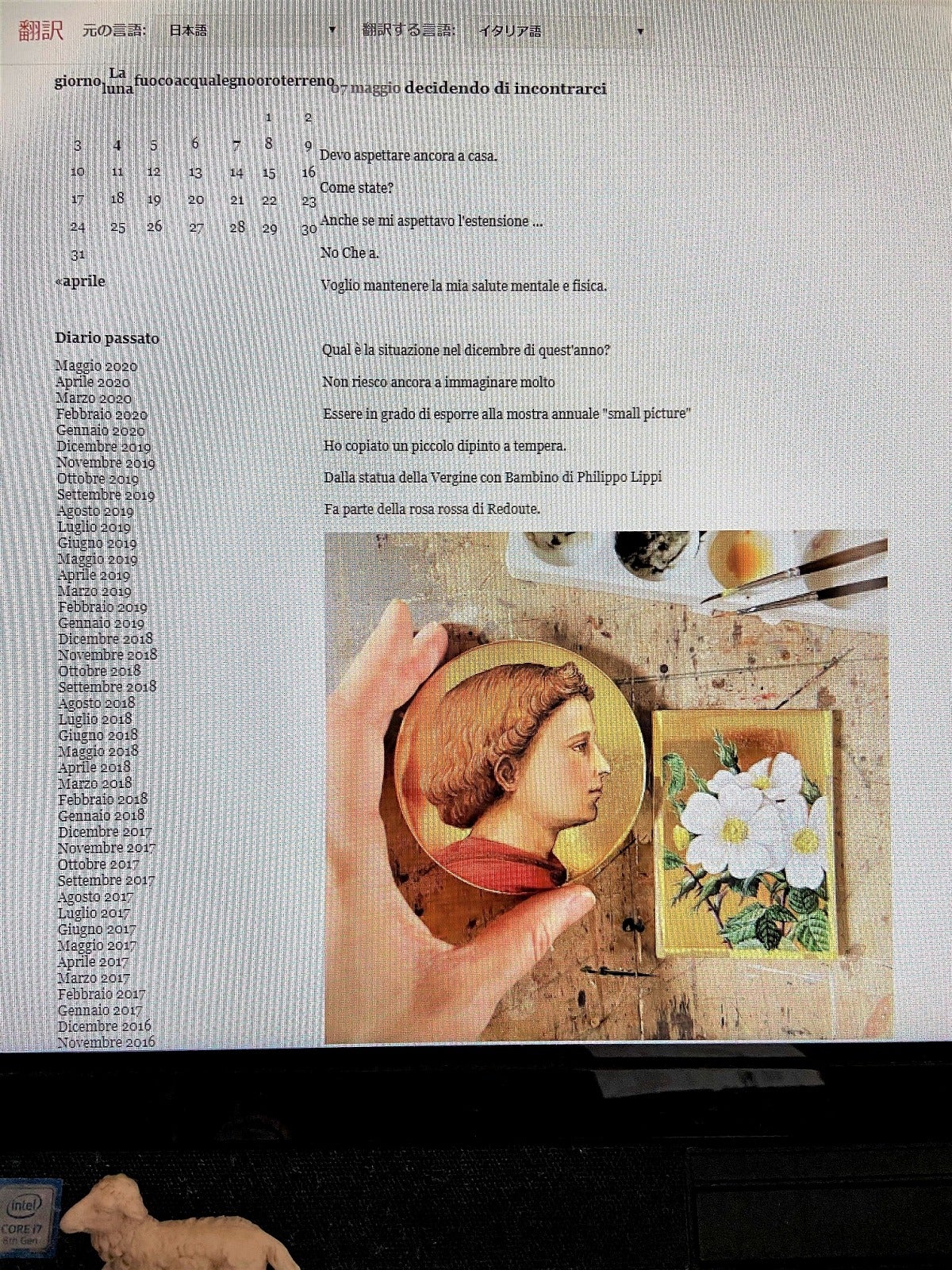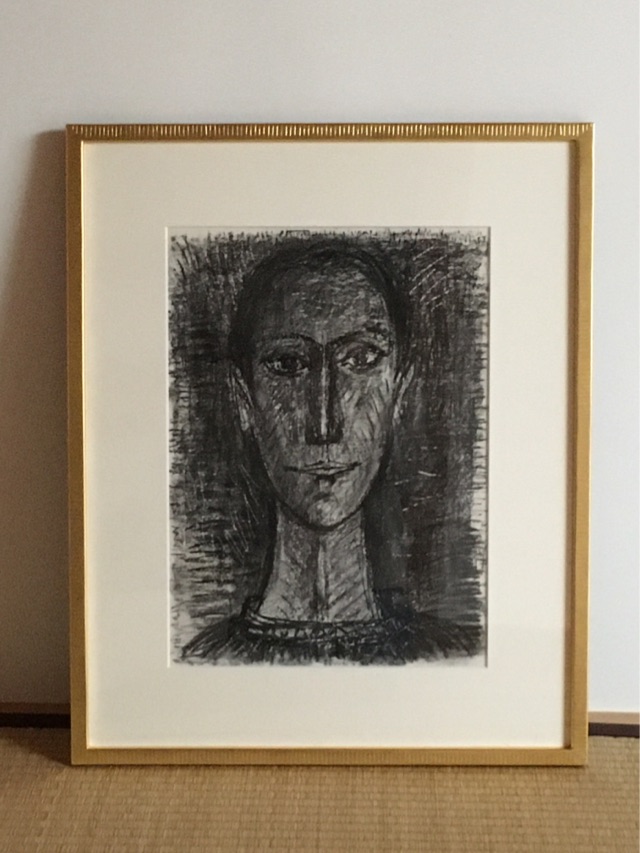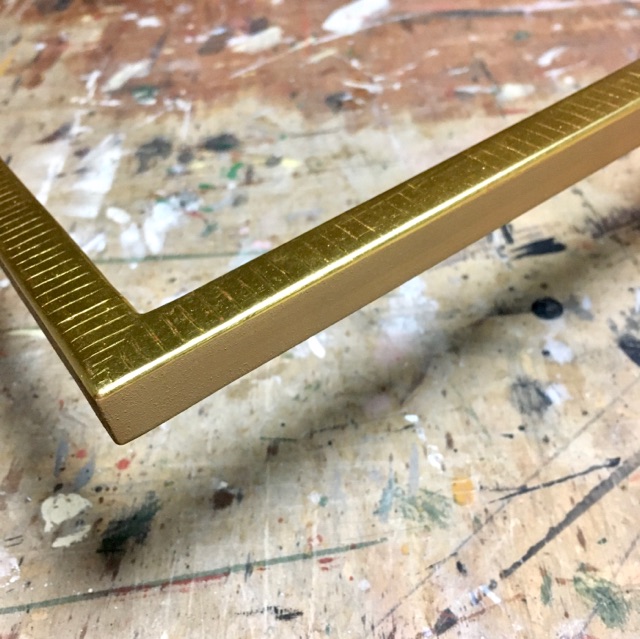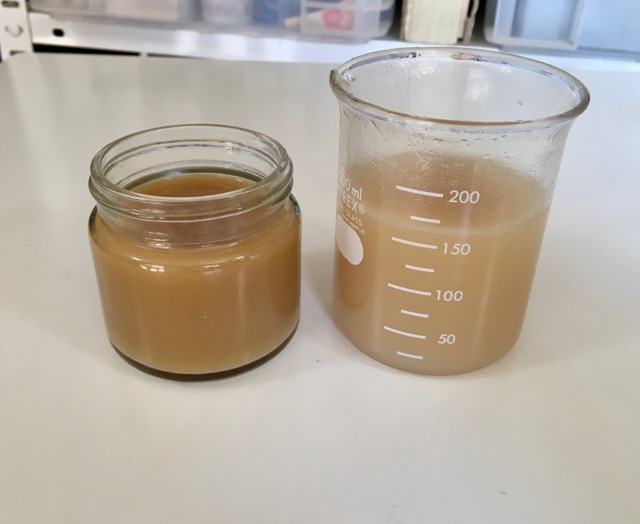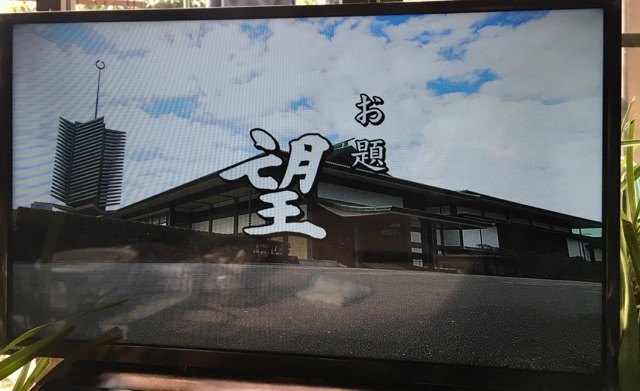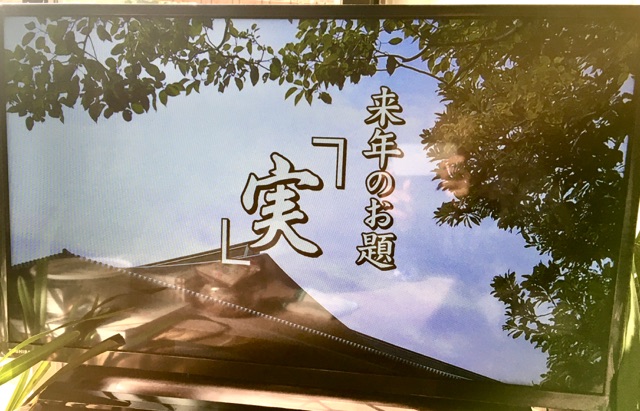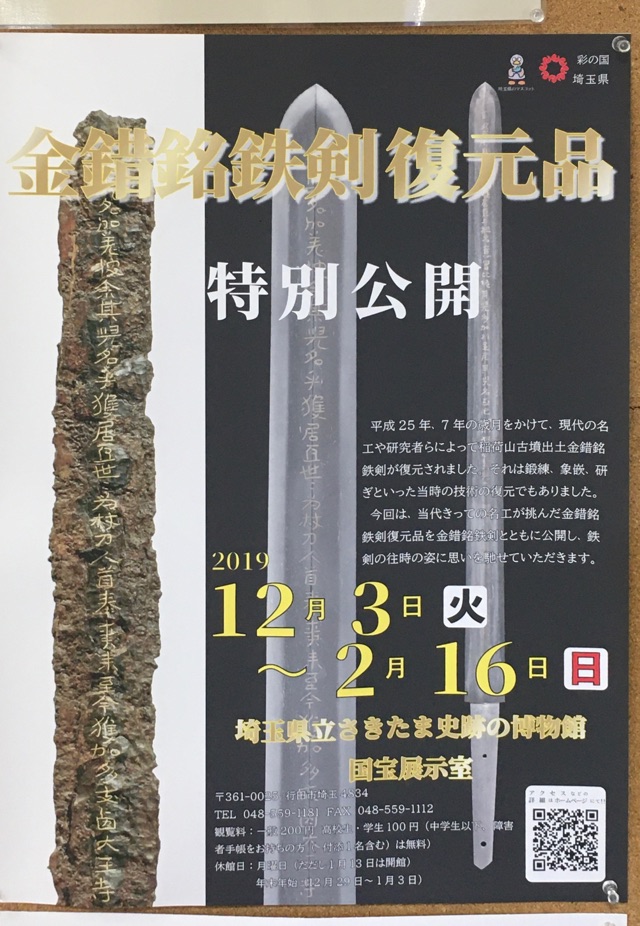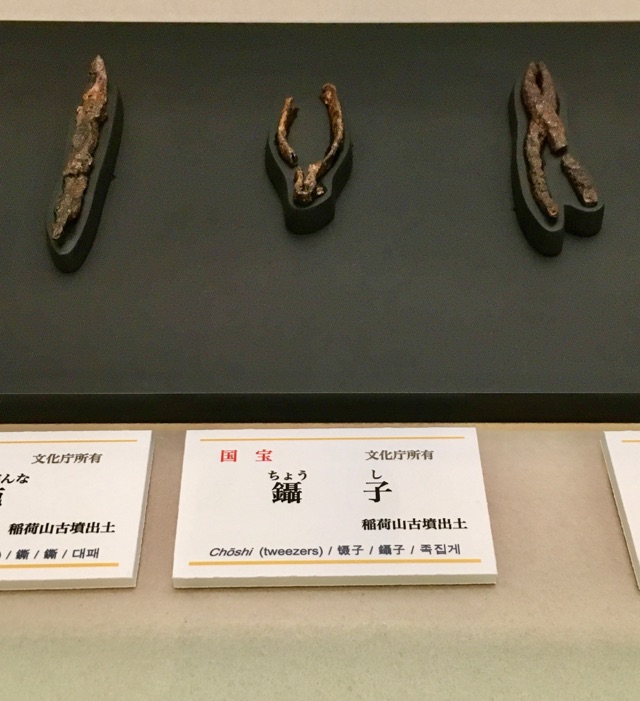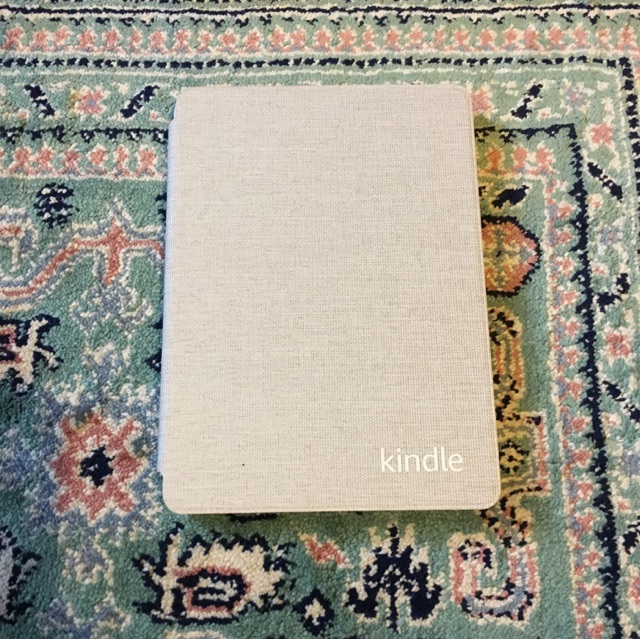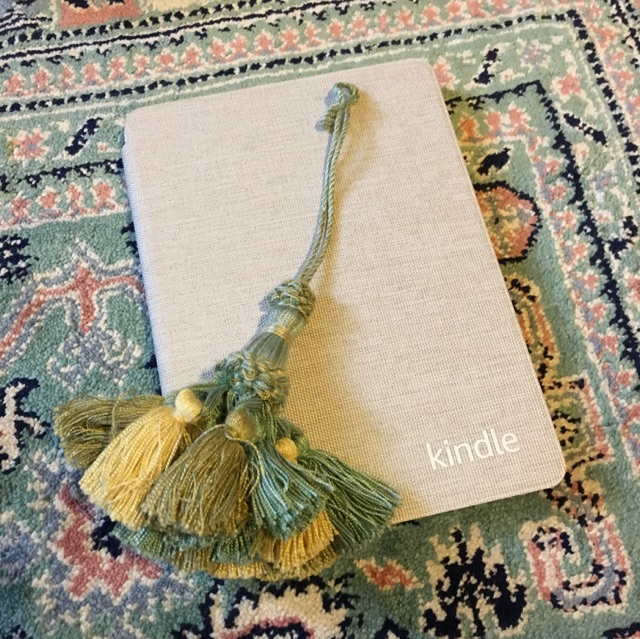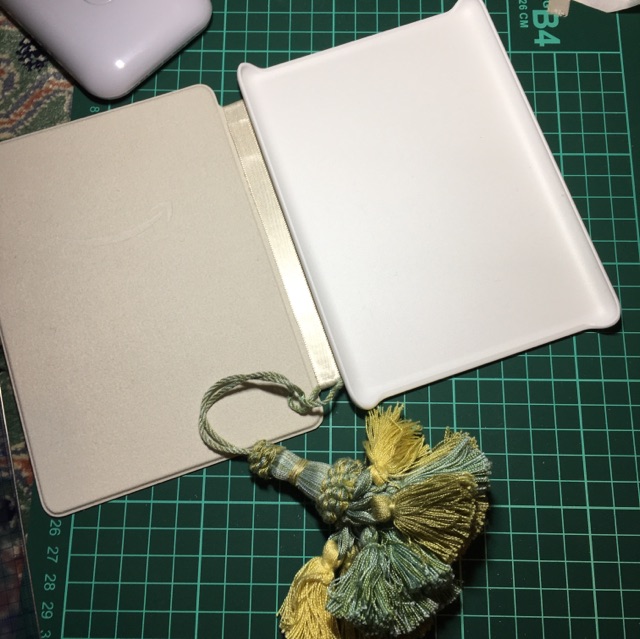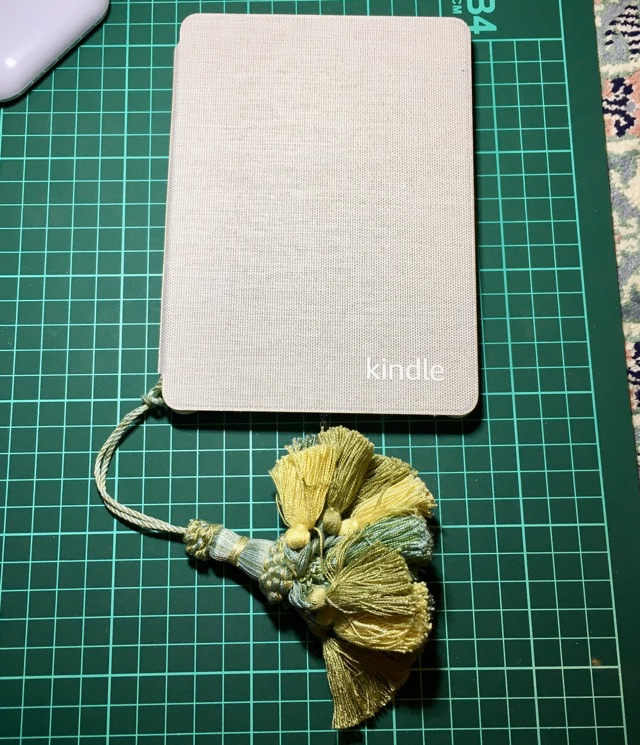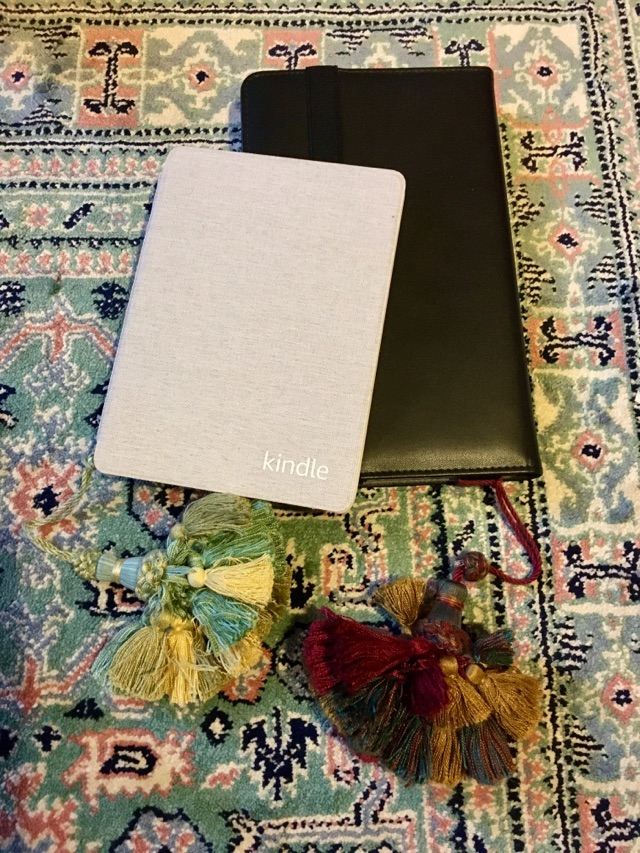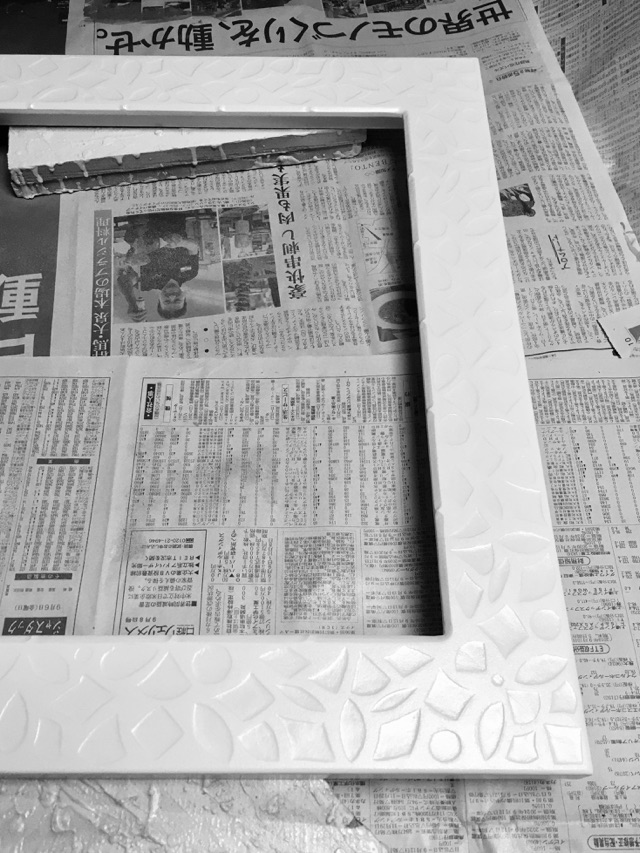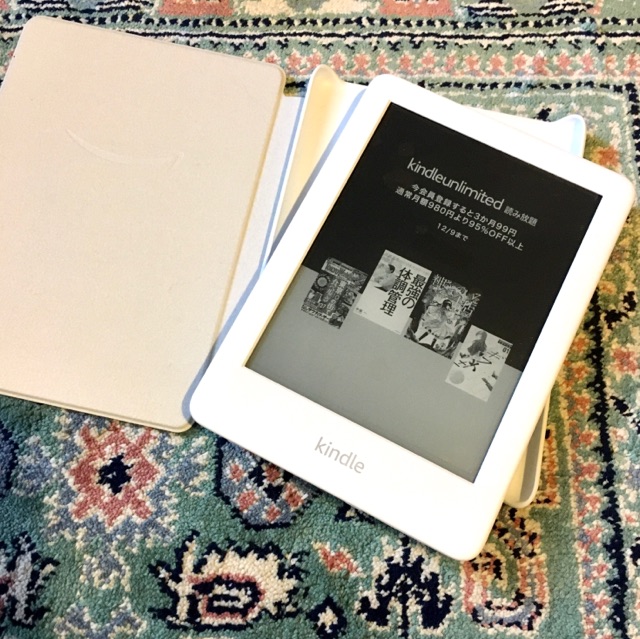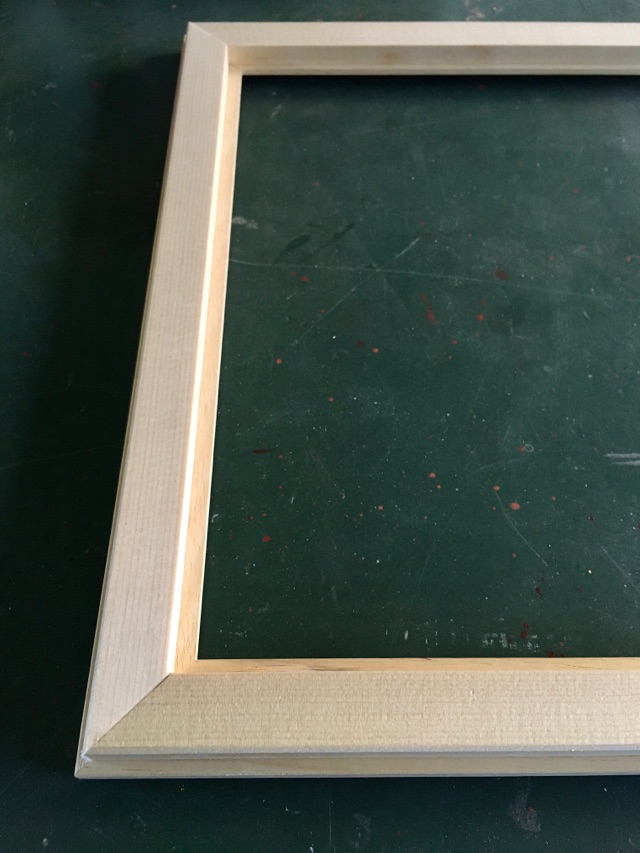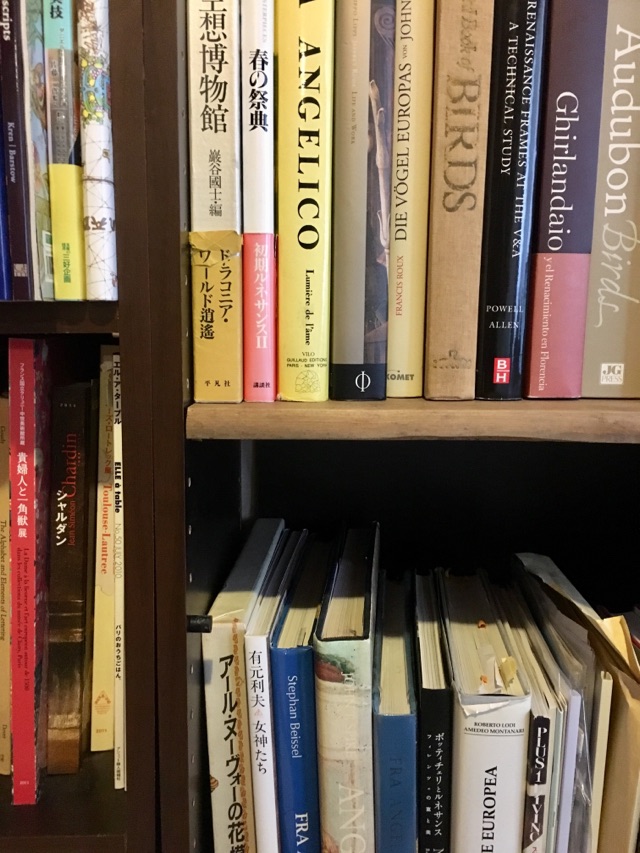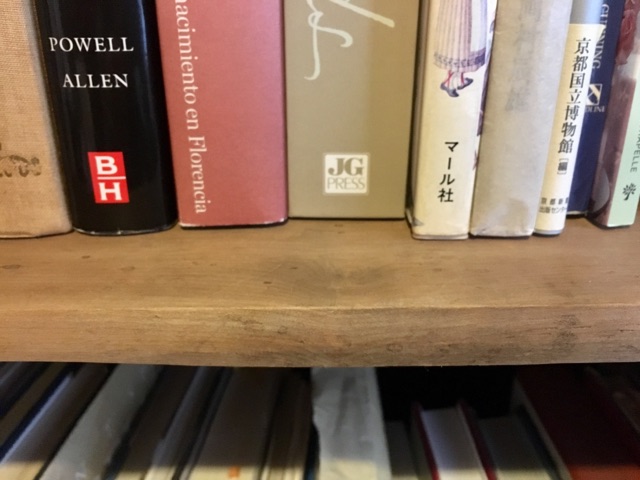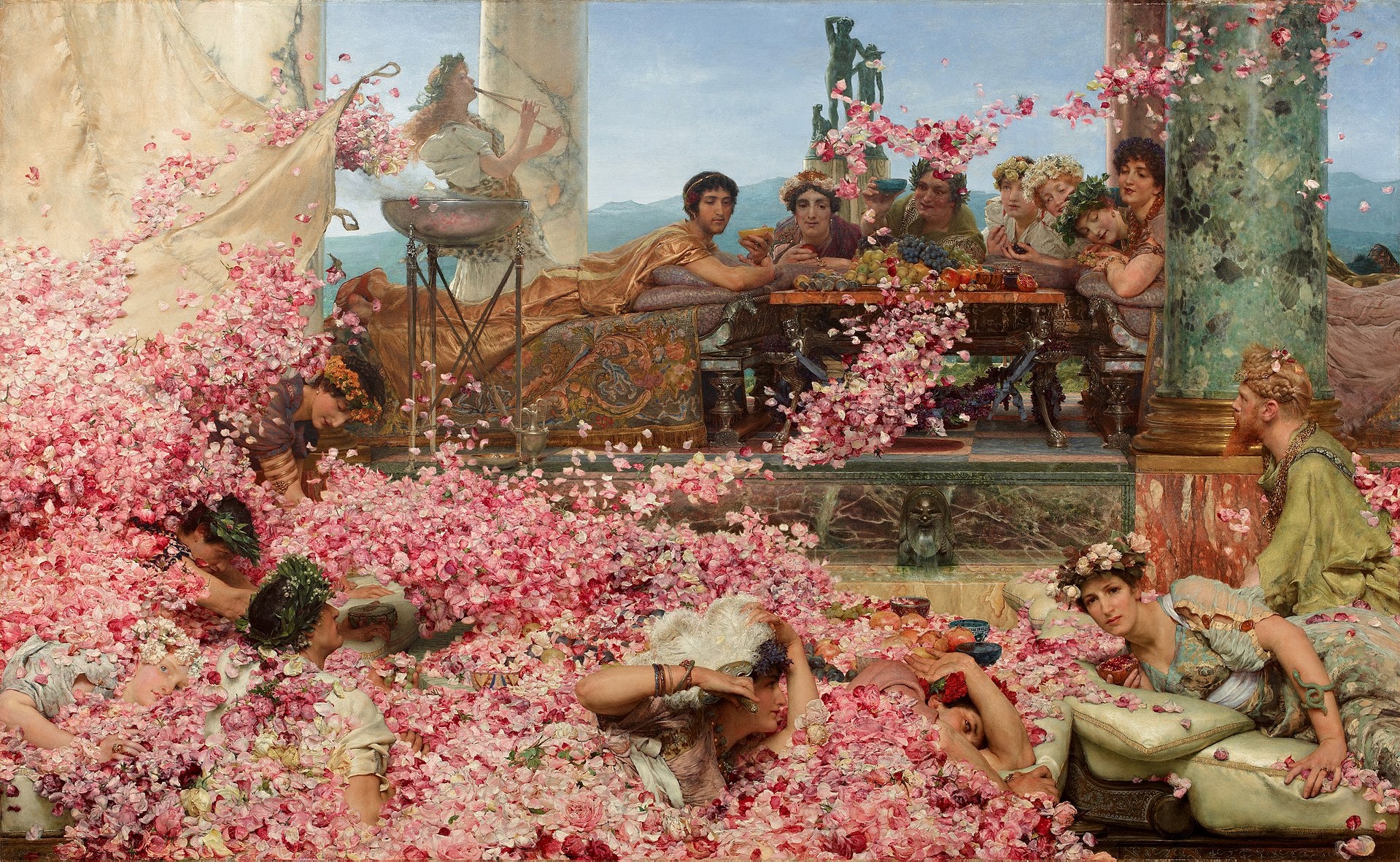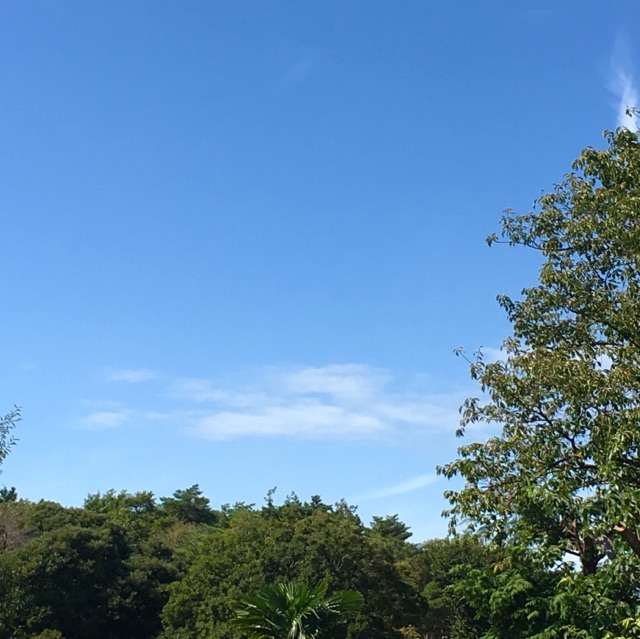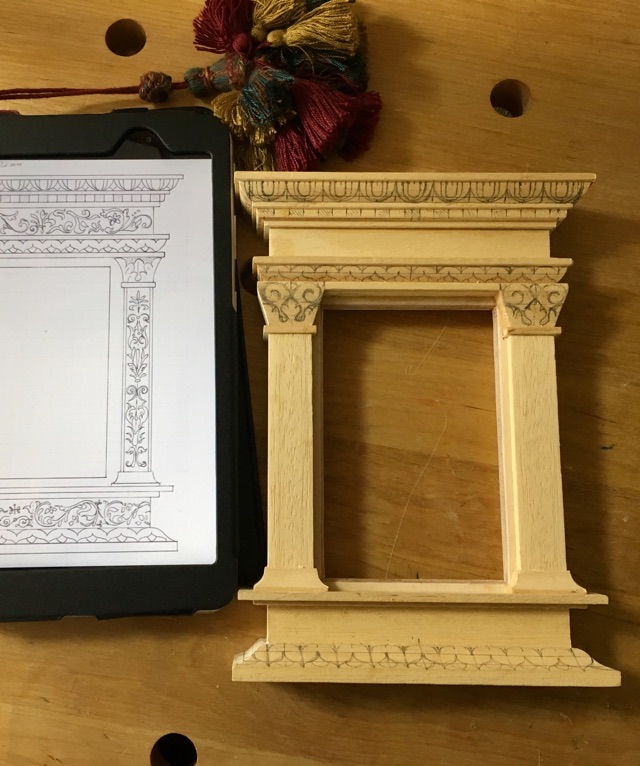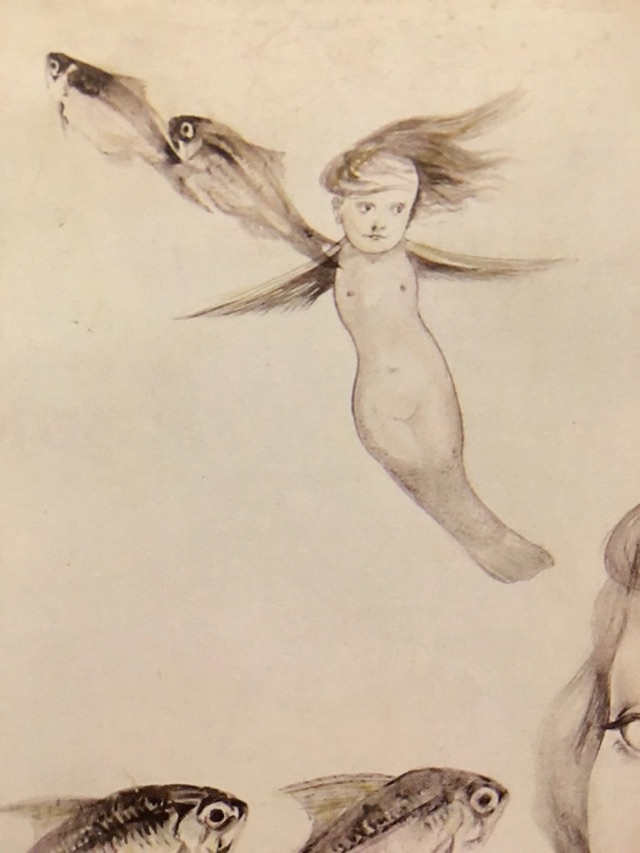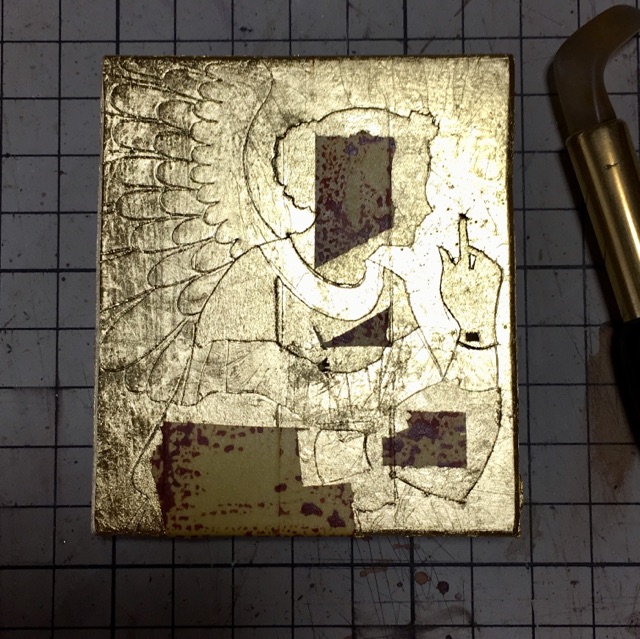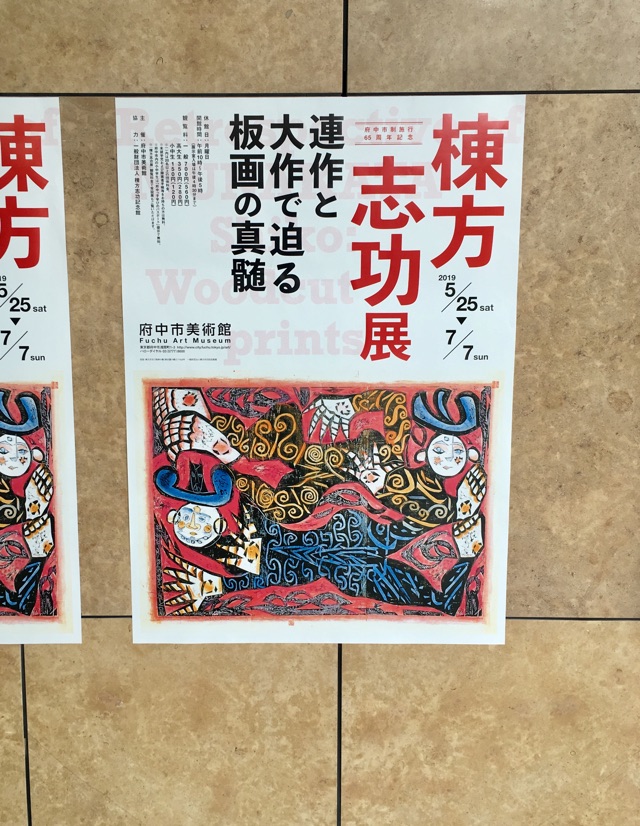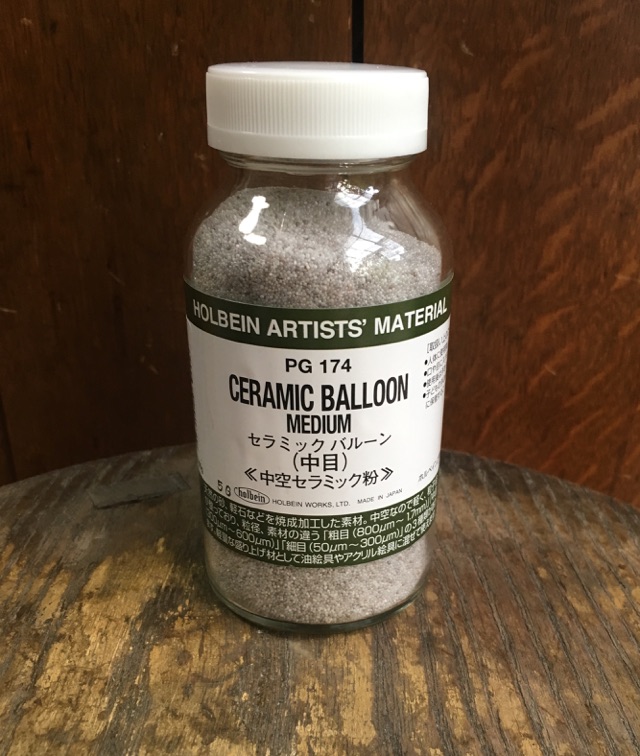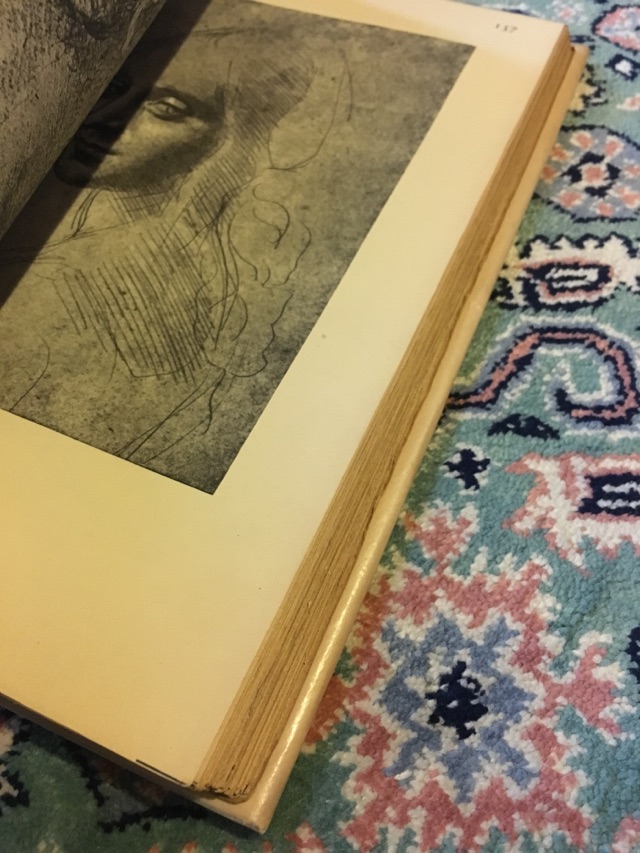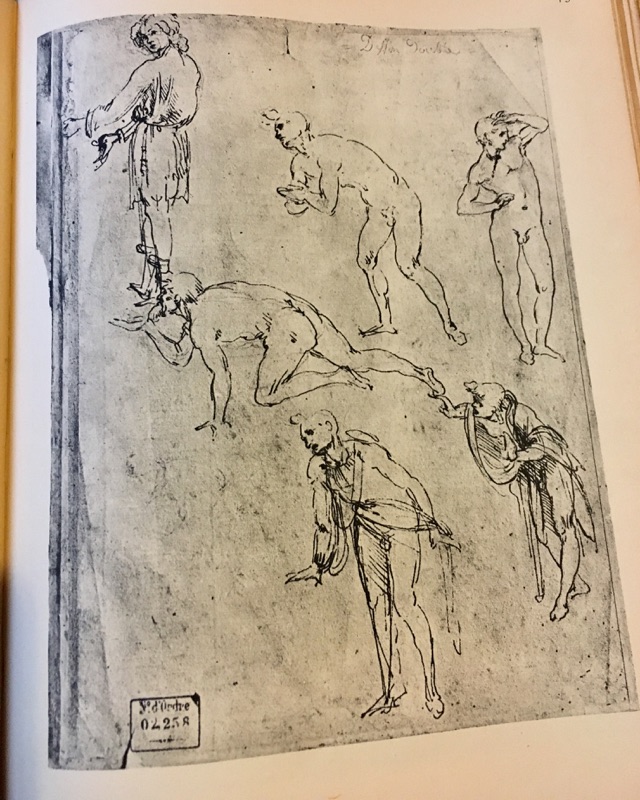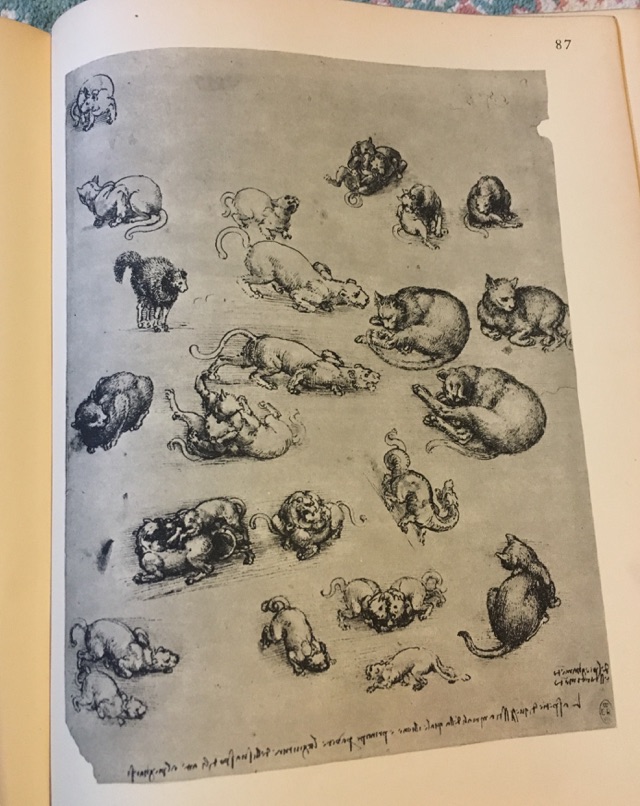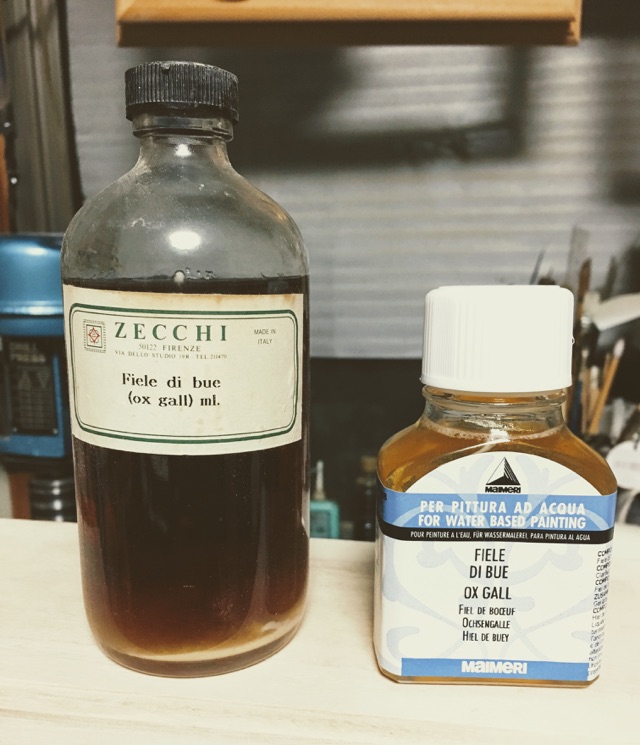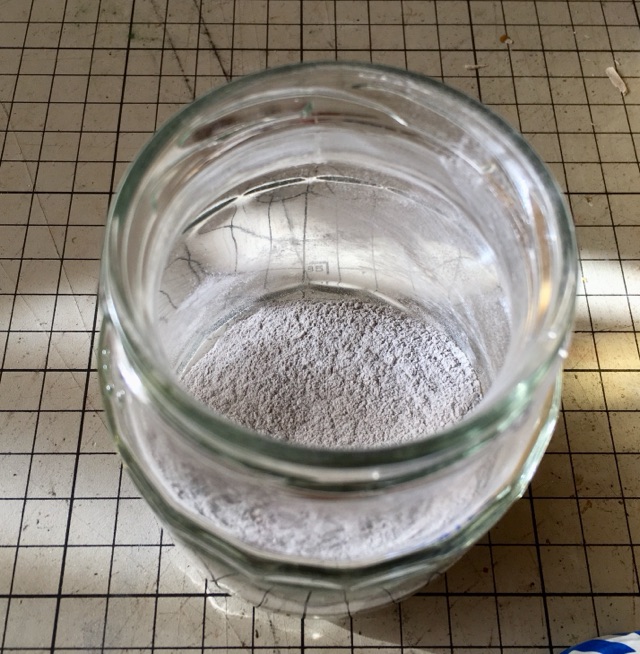diario
粉で復活、宝もの 12月02日
引き出しの奥から、ずっと前に
絡んでほどけなくなったネックレスが
出てきました。
もうすっかり忘れていたのですが。
そうだった、大事にしていたのに。
何度かほどこうと思ったけれど
出来なくてお蔵入りしたのでした。
▲ぎっちり玉結び・・・
そしてふと思い出したのです。
少し前に何かで読んだぞ・・・
絡まったネックレスは片栗粉を使うと
簡単にほどけるって。
わたしはタルク紛を持っています。
お化粧で使う仕上げパウダーのような細かい粉。
粒子の細かさが片栗粉に似ているかんじ。
片栗粉を使うのはもったいない気がして
(だって記憶があやふやだし、後が困るし。)
タルクのボトルに入れました。
▲それで、どうするんだっけ・・・?
いや、思い出しました。
そうだ、粉に入れて、振るんだ!
▲小さい器に移しました。
で、手のひらで蓋をして器ごと振る!
パタパタと振ってネックレスを
引き上げてみると、当たり前だけど粉だらけ。
かたい結び目にも粉が入りこんでいます。
振っただけでほどけて出てくる・・・を
期待したけれど、さすがにそれは無し。
当たり前ですけども。
だけど、いままでどんなにしてもダメ、
(石鹸水のなかで試したり、いろいろ・・・)
かたかった結び目をピンセットで引っ張ったら
あらまぁ、ほどけましたわ・・・。
あっけなくするすると。
▲ほどけた!
粉が飛び散り、期待の大きさが伺える・・・
なるほど、結び目に粉がついて
滑りが良くなった、のですな。
片栗粉やタルク以外に、たとえば
コーンスターチとかでもいけるかも。
こんなアイディア、気づく人もいるのですね。
「粉とは」をご存じの人にとっては
分かり切ったことかもしれませんが
これは面白かったです。
ちょっと夏休みの実験宿題を思い出しました。
さて、粉だらけになったネックレスは
すかさず首に装着!でございます。
身に付ければ絡みませんからね。
粉は、まぁシャワーを浴びれば
流れるでしょう。
うれしいかぎり。ふふふ。
絡まったネックレスをお持ちですか?
ぜひお試しあれ!
大切にお届けします 11月29日
額縁をご注文いただいたとき
大きなものや額装したものなど
黄袋に入れて差し箱やタトウ箱に
納めるのが一般的です。
小さい額縁(ハガキサイズ等)には
わたしは白ボール紙で箱も作ります。
採寸してカッターでボール紙を切り
組み立てて大きなホッチキスで留めて、
仕上げにホッチキスの針をつぶせば
(額縁に傷をつける可能性があるので)
いっちょ上がり、でございます。
額縁を薄葉紙で包んでこの箱に入れて
お届け準備が完了します。
この箱作りも長年やっておりますと
コツも分かってジャストサイズに
作ることができるようになりました。
最初のころはなんだか上手く行かなくて。
額縁作りと同時に箱作も上達いたしました。
思わぬ技術習得・・・ムハハ・・・。
そのものの価値を決めるのは誰 11月22日
額縁の修理修復、絵画の修復の場で
お客様からのご依頼品を拝見したとき
「これはもうあきらめても良いのでは・・・?」
と思われるようなことが、たまにあります。
ご購入したであろう金額よりも
修理修復にかかる金額がうんと高い、
美術的価値があるように思えない、
言ってしまえば
「お金を払ってまで直す価値があるか?」
と、思われるようなもの。
でも、これははっきり言って
余計なお世話なのであります。
そのものの価値は、そのお客様が
感じるものであって、わたしは知る由もない。
持ち主(ご依頼主)にとっては
対価を払ってでも直して大切にしたいもの
であるからこそ、ご相談下さっている・・・
それをつい忘れてしまいそうに
なることもあります。
そんな時に思い出すのは、もう随分前に
Tokyo Conservation 絵画修復部門に
ご相談があった作品です。
紙をセロテープで何枚も貼りつないだ
大きな絵で、落書きの様なかんじ。
紙もテープも酸化して、かなりぼろぼろ。
修復には時間と手間がかかりそうです。
すべて職人作業ですから見積価格は
かなり高額になってしまったのでした。
「きっと見積もりは通らないだろう」
とわたしは内心思っていたのですが
見積価格は通り、ぼろぼろだった絵は
とてもきれいに蘇りました。
あとで聞いたところによりますと
この絵は亡くなったご家族が描いたものとか。
どんなに安価な紙に書かれた
名も無い人の絵だろうと、
大切にしたい人にとっては宝ものです。
そうした「宝もの」を託される仕事
と言うことを折に触れて思い出して
作業しなければ・・・と思っています。
梨地風細工に挑戦 11月15日
先日のAtelier LAPIS展には
講師数人も出品いたしましたが
その中で井上雅未花先生の作品から
目が離せなくなりました。
井上先生はテンペラで可愛らしい
猫や小鳥を描いていらっしゃるのですが
作品には箔を使った装飾も入っています。
(写真をご紹介できず残念です!)
その箔の細工が、なんと言いましょうか
ものすごく細かい点で模様を打ち出していて
あまりの細かさに仰天してしまった!
その作品に感化されまして、わたしも
いざ細かい細かい点刻に挑戦でございます。
小箱に純金箔をきっちり貼り磨き、
模様を下描きして準備完了。
そこからは極細のメノウ棒
(ポーセレン用)でひたすら点打ちです。
アウトラインを点で起こしたら
模様を点で埋めていきます。
てんてんてんてん・・・そしてつづく点打ち。
隙間なく点で埋め尽くすと、徐々に
艶消しの梨地風になります。
このサイズの模様で3時間かかりました。
これが早いのか遅いのか分かりません。
大変だったけれど恐れたほどでは無かった。
・・・ような気がするような。
なににせよ達成感は大いにあります。
今回は成功。次回もっと大きな小箱に
この梨地風細工で模様を入れようと思います。
秋だから、ではないけれど 2 11月04日
コロナ禍がはじまって
自宅にいる時間が増えたのだから
読書量が増えたかと言いますと
わたしの場合は逆なのでした。
理由は移動時が読書タイムだったから。
電車の中や隙間時間のドトールなど
知らない人に囲まれてざわめきがある
ような場面が一番読み進められる、
と言うのは分かっていたのですけれど。
自室や作業部屋では、どうも気が散って
読書に落ち着かないのです。
そんな訳で、本棚の片隅には
順番待ちの本やら
途中まで読んでそのままの本やら
好きだからもう一度読みたいけれど
それっきり・・・の本が行列をなして
「さぁさぁ、どうするの?!」と
無言の圧力をかけてきています。
聞いたところによりますと、
読もうと思ってそのまま放置した本は
結局読まずに終わることが多いとか。
なぜなら「既にタイミングを失ったから」。
その時に読みたいと興味を持った内容も
タイミングを失えばもはや必要ないから?
うう~む、一理あるかもしれません。
だけど、情報を得るための読書なら
その通りだけれど、楽しみとして、また
変わらぬ興味の対象を綴った内容の読書なら
いつでも、十分「役割を果たす」のでは
ないかなぁ、と思っています。
「役割を果たす読書」という表現も
我ながら違和感があります。
読書に役割とか義務とか、
考える必要もありませんかね。
何を言いたいのかと申しますと
「本棚の行列は少しずつ解消する所存です!」
と言う宣言なのでございました。
移動中読書も徐々に再開です。
ありがとうございました 月光荘より 11月01日
10月25日より銀座月光荘画室Ⅱにて
開催いたしましたAtelier LAPISの展覧会
「心の遠近」は無事終了を迎えました。
遠くから、また、お忙しいお時間の
合間を縫ってお越しくださった皆さま
大変ありがとうございました。
だいぶ感染者が減りつつある東京
久しぶりの銀座は予想以上の人込みで
驚き恐れ、それでもやはり賑やかなのは
嬉しくて、心が浮き立ちました。
ギャラリーでも例年以上に皆さんの
会話が盛り上がっていたように感じます。
自分が丹精こめて作った物を飾り付けて、
時間と労力を割いて見に来てくださる方々に
褒めていただいて話を聞いていただいて、
そしてお互いの心に共感して笑顔になって、
とても励まされ幸せな機会になりました。
一時期は開催も危ぶまれた展覧会ですが
開催できて本当に良かったと思っています。
今日からまた、新しい作品制作に励む所存です。
ありがとうございました。
秋だから、ではないけれど 10月28日
先日読んだ辻仁成さんのブログに
「某月某日、なんだか、寂しい年齢なのである。
仕方ないけど、ここんところ、毎日、
寂しいので、なんでかな、と思ったら、秋だった。
秋だからか、と思ったら、思わず、笑ってしまった。」
とありました。
「そっか、寂しいのは秋だからだって。
秋だからかぁ・・・じゃぁ仕方がないよね!」
とわたしも納得してしまいました。
年がら年中どこかしら
うすぼんやりと寂しいのだけれど、
普段はあまり認めたくないというか
自分で見て見ぬふりをしている。
でも秋は寂しくても許されような
「寂しくて当然、だって秋だから。」
と大っぴらに言い訳できるような気がしています。
そうやって認めると楽になるのだけれど
改めて自覚すると余計に寂しくなったりして。
「やれやれ、あ~あ。」
とやり過ごしております。
秋は一番好きな季節なのですけれどね。
もどかしくも終了とする。 10月25日
なかなかイタリア人にならず
悩んでおりました天使です。
フラ・アンジェリコの作品を
卵黄テンペラで模写しました。
オリジナルよりだいぶ小さくした
手のひらサイズの模写ですので
なんとも・・・小さな点ひとつで
表情が変わってしまう。
これ以上いじくるともう
「ドツボにはまって這い上がれなくなる」
という時点で、お終いにいたしました。
フラ・アンジェリコ
「ボスコ・アイ・フラーティの祭壇画」より部分
フラ・アンジェリコ
「リナイウォーリの祭壇画」より部分
どちらもフィレンツェの
サン・マルコ美術館所蔵の作品。
本当は実物をじっくり観察しつつ
模写できれば良いのだけど、と
思いつつも、いや、やっぱり
実物と自作を見比べる勇気は無い。
・・・もどかしいのです。
やっぱり小さい 10月18日
小さい額縁を4つ
同時進行で作っています。
小箱制作はひとまず置いておいて
額縁を作るけれど
やっぱり小さい。
▲手前の2枚はハガキサイズ。
奥の2枚はさらに一回り小さい。
手元でガサゴソとチマチマと
作ることができるから
そしてなぜか本能的に
幼いころから小さいものが好きです。
幼稚園児のころ、焼き物の
2~3センチの動物を集めていました。
ウサギや羊、ブタやアヒルとか・・・
それはそれは可愛いのです。
引っ越して以来とんと見かけない。
どこにしまっちゃったかなぁ。
三つ子の魂百まで、ですな。
わかりやすい達成感が欲しい 10月11日
絵画修復にしろ
額縁制作や小箱作りにしろ
テンペラ模写にしろ
「これにて完了・終了」という
時点を迎えることができます。
この「おしまい」にすることで
得られる達成感がわたしには必要なんだと
つくづく感じています。
分かりやすい達成感があって
お疲れ様!と仲間や自分に言う。
そうしたら次に進める。
この繰り返しが必要なのです。
もっとも、自分の作業に
どこで区切りをつけるか
「おしまい」にするかは
悩み深いものがあって
毎回達成感を得られるわけではない
というジレンマもあるのですけれど。
区切りなのか見切りなのか。
ある種の諦めもあるようです。
人生の半分は 10月04日
わたしも年齢相応に
作業時にはメガネが必要になりました。
(普段は裸眼なのですが。)
愛用しているメガネのフレームが
ぽっきり折れてしまったので
直そうと思ったら
メガネが無いからよく見えない・・・
というトホホな状況です。
▲接着してテープで仮止めしました。
またすぐに壊れてしまいそうだけど。
以前にラジオで「老眼鏡が必要になって
なんだか悲しい」という投稿がありました。
パーソナリティの方が
「でもまぁ人間は今や長生きになって
人生の後半分はメガネが必要なのだから、
好きなメガネを選んで楽しんだ方が良い」
というようなことを話していて
「そうか、人生の半分はメガネかけるのか、
そんなもんか!」と
老眼鏡嫌悪気分から
不思議なくらいあっさり抜け出しました。
そんな訳でして、お気に入りのメガネを
大切に使おうと思っています。
イタリア人にする。 9月30日
フラ・アンジェリコの天使模写を
続けておりますが
顔を描きながらいつも悩みます。
イタリア人になかなかならない。
どうにも日本人顔になるのです。
▲製作途中の図。
まだまだ陰影も色味も足りずのっぺり。
聞いたところによりますと
フラ・アンジェリコに限らず
顔を描くとき(模写も含めて)
無意識に自分の顔に近くなるとか。
ちなみにわたしは見本のような一重瞼で
まったく陰影のできない顔です。
いわゆる「平たい顔族」の典型。
幼いころ、父と母に真剣なまなざしで
「平安時代に生まれるべきだった顔」
と言われた衝撃が忘れられません・・・。
この天使の顔は、なんとしても
イタリア人にする所存であります。
わたしは何する人? 9月27日
先日、親しい友人と話していたときのこと。
彼女いわく「この間、職場であなた(わたし)の
ことを話したのよ、小箱作家の友人がいるって。」
小箱作家?
それはわたしのこと?
ふぅむ、そうか、小箱作家か。
もうずっと前から、それこそ
額縁を作りはじめたころから、出会う人に
「肩書はなに?」と聞かれるのです。
額縁職人? 額縁作家?
フレームアーティスト??
フレームビルダー???
いやいや、違う、しっくりきません。
額縁を作るし、修理修復するし
額縁の作り方を教えてもいます。
Tokyo Conservation のスタジオで
絵画修復の仕事もしますし
黄金背景テンペラ画の模写を販売したり。
最近はもっぱら小箱ばかり作っている。
結局「肩書きは決めていません。」と
お答えすることにしています。
額縁や絵画周辺の仕事をしていて
古典技法が得意、といったところ。
その中に「小箱作家」的な作業も
含められますからね!
決める必要はないのかな、と思ったり。
だけど。
・・・やっぱり肩書き、必要ですかね??
そしてどうなった製麺機 9月20日
先日お話しました製麺機のその後
でございます。
無事にデュラムセモリナ粉と
イタリアのパスタ用強力粉を入手しまして
いざ、初の手打ちパスタの日です。
セモリナ粉100g 強力粉50g 薄力粉50g
卵2個にオリーブオイル少々、塩ひとつまみ。
▲黄色いのがセモリナ粉です。
凹に卵を割り入れたら、すでに土手崩壊・・・
粉はお菓子のようにふるう必要も無く
フォークで卵を溶きつつ粉と混ぜます。
▲大学時代、彫刻家のアシスタントバイトで
習得したはずの菊練りを試す。微妙。
10分程度こねたらラップにくるんで
冷蔵庫で数時間寝かせます。
その間にラグーソースを作りましょう。
▲ラグー?いや、ミートソースでございます。
シイタケやお醤油入り。
ラグーアッラジャッポネーゼ・・・なんちゃって
いよいよ満を持して製麺機の登場。
生地を1センチ厚に切って、まずは伸ばします。
伸ばして畳んでまた伸ばす、を繰り返して
きしめん用の刃でカット。
▲パスタっぽいものができた。
打粉をたっぷりしてしばし乾燥タイムです。
▲くるりとまるめるべきだったか?
思ったより麺の本数が少ないような。
そうして夕飯、渾身の一皿です。
美味しかったか、ですか?
ええと、そうですね
ミートソースが美味しかったですよ!
▲麺は、これはどう見ても
う・ど・ん・・・
それはそれはアルデンテなパスタ。
硬くてアゴが疲れました。
敗因は、生地をカットする前に
薄く延ばす段階で、もっと薄くするべきでした。
厚さ調節7段階の3にしたのですけれど
もっと2とか、いっそ1でも良いくらい!
本数が少ないと感じたのはただひたすらに
分厚かっただけなのでした。
ちなみに、茹でた麵は翌日になっても
まったく伸びないし柔らかくならない。
さすがセモリナ粉と強力粉!
と変なところで感動しました。
ううむ、これで引き下がると
武士が廃る。
粉もまだあります、再チャレンジ近し。
乞うご期待であります・・・
やっぱり天使が描いた天使 9月16日
今年2021年の秋もまた
「小さい小さい絵」展に出品する
ちいさなテンペラ模写を作っています。
黄金背景テンペラ画は、なんと言いますか
「描く」より「作る」がしっくりきます。
支持体の板を切り、ニカワを塗り
ボローニャ石膏を塗り磨き
ようやく下描きをしたら
ボーロを塗って金箔を貼り磨き
装飾を入れて・・・さて。
最後の最後に卵黄メディウムを作って
絵を描くのです。
描く作業は全体のほんの僅かなのです。
今回はフラ・アンジェリコの天使を
2枚作ることにしました。
フラ・アンジェリコは学生時代から
ずっと何度となく模写していますが
その度に新たな発見があって驚きます。
まぁわたしの観察眼が及ばない
と言う証拠でもありますけれども。
初心に帰る、原点回帰です。
今回下描きをしていて思ったのは
フラ・アンジェリコの描く人物(天使含む)は
三白眼が多いような気がする。
一般的に三白眼ってあまり人相が良くない
きついイメージを与えがちですけれど
フラ・アンジェリコの絵は
その三白眼から、厳かさや人間を超えた者
としての表現を感じたりしています。
美味しい版画を 9月13日
今年の夏、誕生日に父が
製麺機をお祝いにくれました。
いわゆるパスタマシーンです。
箱には「製麺機」とあって
美味しいうどん、きしめん、中華麺
ワンタンや餃子の皮も
自宅で作れる、とあります。
もちろんパスタも作れると。
テレビで、イタリアの家庭で手作りパスタの
シーンを見るたびに「ほしいなぁ」などと
つぶやいていたのを父が聞いてくれたのでしょう。
製麺機をもらったとき、わたしは
もちろん「わぁ!」と喜びました。
なにせずっと前から欲しかったものです。
わたしが「これで版画ができる!」と言うと同時に
父は「これで美味しいの作ってくれ~」と。
ふたりで
「え、美味しいの・・・?」
「え? 版画?!」
としばし固まりました。
目的が違う。
パスタマシーンで凹版画ができると
知って以来、気になっていたものですから。
とは言え、これはやはり贈り主の希望を汲んで
まずは美味しい(できるかどうかは謎だけど)
タリアテッレやラビオリ製作など
することにいたします。
パスタ作りと版画刷りと
同じ機械で同時に、ってわけには
やっぱり行きませんかしらね。
版画はすこし先にして、まずは
製麺に特化してチャレンジです!
そこにあるから。それで良い。 9月09日
2020年春に世界が大きく変わって以来
わたしが打ち込んでおりますのが
小箱作りなのですが
完成した小箱もだいぶ増えました。
作りはじめた当初はべつに
こんなに作りためるつもりも無く、
楽しいし無心になれるし
合間あいまの娯楽、なんて感じで
「打ち込む」つもりもありませんでした。
でも気づけば生活のペースも心模様も変化し、
思うように活動できない毎日で
とにかく無心になれる小箱づくりは
わたしに必要な作業になりました。
そして今、逃避としての制作の時期は過ぎて
ただもう「そこに小箱があるから」作る。
そこに山があるから登る
といった心境になっております。
それで完成した小箱は
いま手元にあるもので大小66個
制作中をふくめると、ちょうど70個。
改めて数えてみて、ちょっと達成感です。
横で家族が(呆れて笑いながら)
「それでどうすんのぉ・・・その小箱・・・」
と言っており。
そうですなぁ。
画廊やお店で展覧会と言っても
この秋~冬はおそらくまだ無理かも。
それならそれで、なにか
発表するなり売るなり考える時期が来た。
ネット販売・・・でしょうか?
ううむ、まずは調べて比較して
具体的にする必要があります。
なにせ無知極まれり、ですので。
ああ、だれかに任せたい!と叫んでも
誰もいませんからね・・・。
どなたか販売して下さる方が
いらっしゃいましたら
ぜひご連絡くださいませ!
「こんなに作ってどうすんの」ですが
理由も無く作ってしまうのです。
物を作るって、そんな感じで良いんだと思います。
夏は終わったか、正月はまだか 9月02日
もう2021年の終わりが見えてきました。
そんなことはない?
早すぎますか?
ようやく暑さが納まってきたところで
まだ夏の終わりだよ!・・・でしょうか。
でも気づけば正午の影がすこし長くなって
雲が薄く遠くなってきました。
石膏液やニカワ液を庭の日差しで
溶かし温めることができなくなって
(これぞエコロジーであります。)
金箔を磨き始めるタイミングが
早くなってきた、ように思います。
金箔が暑苦しく見えなくなってきた時も
「夏のおわり」を感じたりして。
▲小箱は同時にいくつかつくります。
奥にあるのは先日のお姫様じゃなかった小箱
名付けて「陰謀の小箱」
そうして「あら、秋本番だわね、爽やか!」
なんて言っているうちにすぐ木枯らしが吹いて
ビールより赤ワインや熱燗が欲しくなって
街にクリスマスの広告があふれたと思ったら
お正月のお節作りを考えなければ・・・
と言うことになるのですよね。
毎年のことですけれども。
季節の移り変わりは、わたしは
空と庭の変化と作業の進み具合で
ある日気づくことが多いようです。
すこし気が早く「2021年のおわり」に
心が持って行かれそうになっても
だからと言って何かを急いで始めるとか
あれもこれもしていない・・・と
後悔するとか、そういう気持ちには
ならずに日々を過ごそうと思います。
すこやかで穏やかな秋をお迎えください!
絵画修復に向き合う 8月23日
絵画修復というのは、じつに
地道な作業の連続であります。
Tokyo Conservation のスタッフとして
油彩画修復もしておりますが
大きな作品になると
キャンバスの裏面のアイロンがけで
一日が終わる、なんてこともあります。
裏面からアイロンで亀裂を緩やかに伸ばします。
裏面の裏面、つまり表側には「絵がある」を
つねに意識しつつ慎重に作業を進めるのです。
下ごしらえも必要で、これは修復に
限らずいろいろな仕事に言えることですけれど、
下ごしらえの良し悪しで仕上がりが左右されます。
▲ストリップライニングと呼ばれる、キャンバスの
耳を補強するテープを作っています。
これも大切な下ごしらえのひとつ。
修復作業をするには安定した心身
——イライラせず飽きずに淡々と―—が
大切ですので、修復を仕事とする人たちは
精神状態の波をゆるやかにする術を持つ
朗らかな人が多いように思います。
(なかには八つ当たりしたり不機嫌を表す修復家も
いるのでしょうけれど。人間だもの。)
わたしはそんな穏やかで楽しい人たちに囲まれて
作業をすることができています。
人間関係のストレスが無い職場ほど
幸せなことは無いかもしれない、と思います。
学校の教室4つ分くらいの広大な部屋で
数人のスタッフが各々の作業を黙々と進める。
そこには静寂しかないのだけど
不思議と空気は張りつめず、明るい雰囲気が
ただよっているのです。
そんな訳で、終わりが見えないコロナ禍で
ドンヨリオロオロするわたしにとって、
絵画修復の仕事に向き合い過ごす時間は
ある種穏やかな精神統一のような、
瞑想に近い時間になっています。
庭にないなら 8月12日
先日、ルドゥーテの薔薇の
小さな模写が完成しました。
大輪の花びらが幾重にもなった
「これぞ薔薇」の花ではありませんが
一重で原種に近そうなシンプルな
そんな花もとても好きです。
もう夏真っ盛りになって
蝉が飛び交う我が家の庭には
(蝉爆弾炸裂で悲鳴を上げる日々)
薔薇など一輪もありませんので
絵で再現してしまえ、と言ったところです。
四苦八苦 8月05日
毎日毎日暑い中、何をしているのか。
三度の食事をして、なんならオヤツも食べて
出稼ぎに行ったり(修復の仕事や教室など)
自宅の作業部屋で何かを作ったり直したり
自分も家族も健康で衣食住そろって、
これは幸せとしか言いようがない状況です。
テレビでオリンピックを観て
戦いと勝利の疑似体験をさせてもらって、
ワクワクドキドキも十分にある。
だけどなぁ。なんだか。
いまわたしが求めているのは
穏やかなちいさな日々ではなくて
挑戦の疑似体験でもなくて、
「非日常を経験すること」なのです、きっと。
飛行機のチケットや滞在先を決めて
現地情報を集めたり準備をあれこれ始めることから
「服は何を持って行くか」
「あの教会を訪れる最短ルートはどれか」
「これは持って行くか現地調達か」
「あの人へのお土産は何が良いか」
など小さな幸せな悩みをたくさん抱えたい。
そして緊張と楽しみの、心からの
ワクワクドキドキを経験したいのです。
イタリアに行きたのです。
今現在イタリアにお住まいの
日本の方々のブログなどを読んでいますと、
帰りたいのに帰れない、
日本の家族の緊急事態で、小さな子供を
イタリアに残してひとりで一時帰国、
なんてことも書かれています。
行きたいのに行けない。
帰りたいのに帰れない。
どちらが辛いかと言えば当然ながら
帰りたいのに帰れない、でしょう。
・・・そうしてまた振出しに戻る。
「必要以上の行動ができない」から
ウダウダしているなんて。
お気楽能天気にも程がある。
分かっている。
そして、本当に本心から行きたいなら
無理をすれば行けない訳では無い、という事実。
実際に行っている人もいるのだから。
だけど。
いやはや。どうにもこうにもままならぬ。
そんなことを考えて
自分を説得するのに四苦八苦している
8月のはじめです。
デューラーの砂時計は 8月02日
1400年代後半から1500年代前半の
ルネッサンス期に活躍したドイツの画家
デューラーの、とても高い再現度で
原寸大に印刷された版画集を観ていました。
じつに細かいのですが、デューラーが楽しんで
熱中して制作した様子が伝わります。
寓意画でも有名なデューラーですが、
砂時計も好んで登場させていたようです。
砂時計の寓意は「限りある時間」でしょうか。
「人生の短さ」などもあるようです。
メメント・モリのひとつ。
▲ひげの悪魔が騎士に砂時計を見せている。
(画像はwikipediaからお借りしました)
デューラーの作品に出ている砂時計を見ると
そのどれもが必ず(わたしが見つけた範囲内で)
砂は、半分落ちて半分残っている。
「人生の半分がすでに終わってしまった」
なのか
「人生、まだ半分残っている」
なのか。
▲壁にはおおきな砂時計。
(画像はwikipediaからお借りしました)
さて、わたしはどちらだろう。
上の砂が、残された時間が、わたしに
どれくらいあるか知るのは恐ろしいけれど。
考えている間にも刻一刻と砂は落ち続けるけれど。
行きつく思いは「有意義に過ごしたい。」
それしか思い至らない今日です。
何か秘密があるのかい? 7月22日
夜、夢は見ますか。
わたしは幼いころからずっと
毎晩見る夢をひとつは覚えています。
夢を見る理由って脳の整理だとか
潜在意識の表れとか聞きますけれど
単純に自分が見る夢が面白くて
あるいは恐ろしすぎて
自分でも理解できていない内面が
大きいのだな、としみじみ思います。
今朝見た夢も、なかなか変でした。
自分は高校生、でも意識は現在のもの、
そしてクラスメートも現在の友人知人。
ポテトチップスを貪り食べるのです。
我ながらものすごい勢いでした。
どれだけポテチが食べたかったのだ。
そしてはっと気づいたら賞味期限が先月。
一緒に食べている友人に見られないように
必死でパッケージを隠す!・・・という
バカバカしいような意味深なような
夢でした。
なにかわたしの秘密が暴露される
などという暗示でないことを祈るばかり。
もうひとつの sansovino 7月05日
2020年秋に作った双子のサンソヴィーノ額縁。
ひとつは石膏を塗って純金箔と黒で仕上げて
サンソヴィーノらしい強烈額縁になりました。
そして片割れのもうひとつは白木のまま放置し、
仕上げを迷いに迷っておりました。
完成したのは昨年。
そろそろどうにかせねばなるまいよ・・・。
オリジナル通り全面金にしてみる?
でもそれも完成が見えてつまらない。
じゃぁ、シンプルに茶色にしようか?
などと自分会議をしまして。
さっそく水性ステインのオーク色で塗ります。
そういえば、全面ただの茶色の
サンソヴィーノ額縁って
見た記憶がありません。
知らないだけで存在するのかな、
イタリアの方にとっては
ちょっと変な感じなのかしら、
と心配になりつつも
完成したらきっとかわいいですぞ!
久しぶりに再開 6月24日
ここしばらく、グスターヴォさんに
教わったヴェネト額縁の
彫刻から距離をとっていたのですが
久しぶりに「そろそろ良いだろう」と
再開いたしました。
半年以上本格的な彫刻から
離れていたので感覚が変!
あれ、どうするんだっけ・・・
とは大げさですけれど
腕慣らしが必要でした。
えーっと、ううむ、んん??
などと言いつつ。
やっぱり木槌を振り上げて
ガシガシと彫り進めるのは
楽しいのです。
これはなかなかよろしい額縁が
完成する予感です。
気づけば窒息寸前 6月17日
小箱も少しずつ作っております。
ヨーロッパの古典技法を使った
小箱ではありますが
日本の模様を使ったものも
作りたい・・・と思いまして
天平時代のデザインを。
東大寺三月堂の仏様にある模様を
参考にしました。
▲天平時代の模様は地中海世界のものが
シルクロードを通って日本にやってきたそうですから、
バランスが洋風、アラブ風にも感じられる。
桐の小箱に下地を施し
ボローニャ石膏を塗り磨き
模様を線彫りしてから
アクリルグアッシュで彩色。
なにせ細かい模様なので
神経を使います。
▲この後にバックの色を塗ります。
じぃぃぃぃ~っと描き続け
はたと気づくとものすごい頭痛。
びっくりした!
呼吸をほとんど忘れておりましたよ。
窒息して酸欠になっていたのでした。
やれやれ。
いくら楽しくても息はしましょう。
もう寝なさい。 6月10日
どうもわたしは日ごろ
ひとりで作業しているからか
はたまた根っからの性格なのか
煮詰まりがちで、
そんなときは大抵作業も
上手く進まなかったり
失敗したりします。
・・・いえ、そんな頻繁に
失敗しているわけでは
ありませんけれども。
眉間にしわを寄せつつ家族に
「失敗した」などとブーブー訴えて
気を紛らわそうとしていると母は
「まぁ、そんなときは一晩寝るのねぇ」
とノンキな口調で言うのでした。
結局その日は手直しの準備だけして
違う作業をして一晩寝ました。
翌朝見ても、やっぱり失敗は失敗で
小人が夜中にこっそり直してくれているわけもなく。
でもまぁ、昨日思ったほど深刻でもないし
失敗の理由の整理がついたので直せるし
「もう同じ失敗は繰り返さない」と思えたし
一晩寝たことで煮詰まりも消えました。
分かってはいたことだけれど
寝ちゃって仕切り直しって
改めてわたしには効果的なのです。
この年齢になってもやっぱりまだ
母には助けられているのだわ・・・と
苦笑いの朝なのでした。
ヴェネト額縁はひとまず 6月07日
2020年2月にフィレンツェにて
木彫職人グスターヴォさんの
工房に通って制作した額縁木地は
帰国後に追加工をして
先日無事に完成しました。
勝手に呼んでいた名前
グスターヴォ額縁改め
ヴェネト額縁でございます。
なんたる派手。
額縁の中に見えている写真は
参考にしたオリジナル額縁
18世紀イタリア・ヴェネト州で作られたもの。
Roberto Lodi 著
Repertorio della cornici europea P.270掲載
▲技術的に足りないのはもちろん、葉の向きとか
いろいろとオリジナルとは違う部分もあります。
すぐにアンティーク加工をしようと
企んでいたのですけれど、
完成してみたらなんだかこれも悪くない。
もう少し眺めて楽しんで
具体的にどうするか検討しようと思います。
実は完成前日に、ふと遠くから
離れて眺めてみたら気が付きました。
左下角、対で葉が足りない。
え、今気づくってどういうこと。
彫って、塗って、磨いて、
また塗って、貼って磨いて・・・
ここまでの作業中に一度も気づかなかった。
ちょっと自分が信じられないのですが。
そういえばフィレンツェで作業中に
わたしが「あ!間違えて彫りすぎた!」
と叫んだ時にグスターヴォさんは
「そんなのは後からリカバリーできる」
と確かにおっしゃったのでした・・・。
これを今、書いていて思い出しました。
ハハハ・・・もうリカバリー不可。
でもまぁ、それもまた思い出
と言うことにしよう・・・
分かっているからきっと 5月24日
読んでいる本の
登場人物のセリフで
「期待しない。
期待すると自分が壊れてしまうから。」
とか
「焦らないで。」とか
糸井重里さんの言う
「落ち着け」とか
時計の針がちくたく進む音が
頭の中に響くような毎日の中で
こうして目に飛び込んでくる言葉は
「自分にいま必要な言葉」
「無意識に求めている言葉」
なんだろうな、と思っています。
ヨーロッパやアメリカでは
着々と再開が準備されて
イタリアのラジオからは
ヴァカンス旅行の広告が流れて
じゃあわたしたちは?
と考え込んでしまう。
期待しないで焦らないで落ち着いて。
それともうひとつあるとすれば
「でも希望は失わないで」です。
ムスカ大佐化する夜 5月20日
グスターヴォ額縁は
いい加減に呼び名を変えなければ・・・
箔を貼り、メノウで磨きました。
なんと言いましょうか、
箔作業って一投入魂!という
集中力もをもって作業しますので
はたと気づいた時には
箔貼り中の写真を撮ることも
忘れておりました・・・。
まだ箔の繕いがありますけれど
とりあえず、磨き上げまして
一息ついたところでございます。
▲四辺中央の平坦な部分には
箔を2枚重ねで貼りました。
重厚感が加わります。
そして、四隅の彫刻部分には
点の刻印が入るのです。
▲点をひとつひとつ打ちます。
とんとんとん・・・こつこつこつ
永遠に終わらない気がする作業
いやはや本当に、純金の輝きは
目によろしくありません。
相変わらずムスカ大佐風に
「目が、目がぁぁ~!」と叫びつつ
夕刻には無事に打ち終えました。
花は小さくとも 5月17日
ことし初のバラが咲きました。
手入れもほとんどされずに
けなげに植木鉢で生きているバラは
花がとても小さいけれど
薫り高いのです。
数日後にはもううつむいてきていたので
切り花にして近くに置くことにしました。
記念写真を撮りましょう。
左向きが良い?
それとも右向き?
はい、右に向きたいですね。
ではブロマイドを。
まだ蕾がいくつか枝にあります。
この切り花とお別れしても
また会えるでしょう。
気が抜けた~ 5月10日
4月末に大きな仕事が終わって
どっと気が抜けたゴールデンウィーク
だったのですが、
せっかく心身に余裕ができたのだから
自分の作業も進めよう、と思って
石膏を磨いて放置していた
グスターヴォ額縁の
2020年2月にフィレンツェで
木彫師グスターヴォさんに
教わりながら作ったので
こんな呼び名になってしまった・・・
作業を再開いたしました。
作業部屋の冷蔵庫には
いつもニカワや石膏液は
準備してありますので
黄色ボーロと赤色ボーロを
湯煎した魚ニカワでちゃちゃちゃと
溶きまして、ベベベと塗りました。
今回は黄色も赤も厚めです。
クラシカルで重厚な雰囲気に
仕上げる予定でおります!
それは君が考える必要ないよ 5月06日
またしても小箱の話・・・
なのですけれど
「ああ、そうだなぁ」と
つくづく思ったことの話。
小箱を作りはじめたころ
昔から額縁でお世話になっている方に
「いまこんなものを作っております・・・」
と相談に乗って頂いたことがあります。
とはいえ、仕事ついでに気軽に
「見てみて~ちょっとかわいいでしょ」
なんて感じでもあったのですが。
▲小箱の内側には布を貼っています。
大切なものを入れてもできるだけ安全なように。
この小箱たちを売り出すにあたって
形もサイズもさまざまだけど
いったい何を入れるために売るか?
どうやって買っていただく??
おすすめの使い方はあるかな???
・・・と考えていたのですが
その方いわく
「入れるものを君が考える必要はないよ。
買った人が入れたいものを入れるのだから。
思いもよらない素敵な使い方をする人が
いるはずだよ。」
目からうろこが落ちました。
そりゃそうだ。
空の箱を売るのですから
入れる物を指定する必要は全くない。
▲こんな長細い小箱ですが
なにか素敵なものを入れていただきたいのです。
とかく視野が狭くなるわたしです。
この頂いたひとことで、なんだか
こころがぽわ~んと軽くなりました。
ブラックレター装飾 5月03日
装飾に文字を入れるのが大好きなのは
もうずっと昔から変わりません。
それも、ゴシック体が好きです。
日本のフォント・ゴシックもありますが
「ブラックレター」の方を指しています。
ラテン語の慣用句などを探し出して
小箱に描きこんでいます。
身近な言語だと文章の意味を強調しすぎて
意味深な小箱になってしまうのですが
ラテン語ですと、パッと目に入っても
ひとまず文字装飾に見えますし
中世の雰囲気が好きなので
ラテン語を選んでおります。
(でもこれはわたしの感覚です。
分かる方が見れば意味深かも・・・)
今回の小箱、なかなか好きな感じに
仕上がりつつあります。
小箱作り、つくづく楽しいです。
楽しい迷走 4月29日
あいかわらず小箱は作っております。
デザインやイメージは大まかに決めて
作りはじめるのですけれど
具体的になってくると途中で
「なにか違う」になって
その都度デザインを変更したりします。
鉛筆で模様を書き入れてみたりして。
▲格子模様をパスティリアで入れたけれど
釈然としなくて模様を試してみた図。
ご注文品ではないからこその迷走。
成り行き任せと言いましょうか。
でも思いがけない楽しい結果に
なることもあるのです。
おや、失敗か?と思っていても
案外と気に入ってくださる方もいたり。
楽しみつつ迷走しております。
大切な「よしはる彫刻刀」 4月26日
石膏を塗り終わり、乾いたら
石膏の凹凸を整えるために
紙やすりで磨くのですが、
今回のような彫りが細かい場合は
彫刻刀などで再度彫り起こすこともあります。
リカットと呼ばれる作業です。
▲こちらまだ石膏を塗っております。
特にこの額縁、オリジナルは
17世紀ヴェネト地方(ヴェネチアがある場所)
で作られたのですが、それはそれは
キリリとシャープなラインなのです。
デザインが曲線と花々でロマンチックですが
シャープなラインで引き締まっていて
それを再現したいのでございます。
上の写真、リカットに使っているのは
小学校時代に図工で使った学童用彫刻刀。
物持ちが良いにも程がありますな。
裏側にはマジックでデカデカと
名前が書きこまれております。
おそらく4年生で買ってもらったのでしょう。
石膏を削ると彫刻刀が傷むので
リカットには専用の彫刻刀が便利です。
学童用ですので切れすぎず丈夫ですから。
思えばこの「よしはる彫刻刀」で
ずいぶんいろんなものを作りました。
図工では自分の肖像浮彫りや木版画、
中学生になってからは消しゴムはんこ、
高校の美術クラブでは壁掛け木彫時計・・・
そして今も現役なのですもの
わたしの長い長い仲間です。
ネット検索してみたら、この「よしはる」は
いまも同じデザインで販売されていました。
ただ箱は紙からプラスチックに変更。
この部分に時の流れを感じました・・・。
ワックス実験悲喜こもごも 4月22日
ずいぶん前、2017年に
完成させました彫刻の額縁は
市が尾のAtelier LAPIS に飾らせて頂いたり
サンプルとして手元に置いていましたが
どうも・・・なんだか気に入らない。
4年経って感覚や好みが変わったのかも
しれません。
▲以前の状態。汚しが不自然なのです。
気に入らないなら変えてしまえば良いじゃない?
なにせ自分で作って自分で持っている
額縁なのですから、遠慮は必要ありません。
まずはスチールウールで磨ります。
同時に以前に付けた古色のワックスや
パウダーも取り除いてしまいましょう。
そして改めて褐色のワックスを塗ります。
このワックスは最近手に入れたもので
今までのワックスと少し違います。
今までは留学時代に教わったレシピで
調合していたワックスなのですが
今回の新しいワックスは市販品。
実験もかねて使ってみることにしました。
▲黄色味が抑えられ、濡れた感じ。
ふうむ。
今までより褐色が強いイメージです。
そしてなんだか・・・日本の他工房の製品の
色とツヤに似ているような?
言ってしまうと「日本製っぽい」ような。
以前に「KANESEIの金は色が軽い」と
言われたことがあるのです。
他製品より黄色味が勝っていて重厚感が無いと。
いろいろと謎が解明されてきました。
今までの自作ワックスも
今回の市販ワックスも
一長一短あるのです。
まだ調整が必要だけれど
使い分けることができそう。
手持ちの札が増えましたよ・・・フフフ。
黄色いお花のお家 4月19日
わたしの記憶によりますと
モッコウバラの満開時(東京)は
5月の大型連休ごろなのですが
今年2021は4月18日現在すでに
満開~終わりに差し掛かっています。
思えば昨年2020年も「今年は
満開が早い」と書いておりました。
そんな昨年よりさらに早い今年
どうしちゃったのでしょうね。
桜も早ければモッコウバラも早い。
いつもモッコウバラが咲くころは
わたしの額縁作業がなぜか
一年で一番忙しいことが多いのですが
今年は「命がけ」(大袈裟ですが)な
最終局面を迎えて、我ながら
寝ても覚めてもその額縁ばかり
考えている状態になっています。
納品は間近、制作は順調ですし
こうした場面も人生には必要ですから
いっそのこと楽しんでしまえ!
(実際は難しくとも)と
張りきって咲き乱れるモッコウバラに
今年も励まされております。
作業部屋の側壁に植えてあるので
道行く親子の会話が聞こえます。
「わー、今年も綺麗ね~」とお母さん
「きいろいおはなのおうちだ!」と
幼稚園くらいの子供の声。
たまらなく嬉しく、和みました。
どうにもこうにも。 4月15日
先日に外側に木枠を取り付けて
縁彫刻をしていた額縁ですが
まぁ・・・こんな感じで。
思ったようにはなかなかいきませんが
目の前に「ドツボ」(いつまでたっても
終えられない心境)が見えてきたので
これはこれとして、次に進みます。
グスターヴォさんとの会話中の
メモ書きが木地に残っています。
「stracantone」三角刀
「tiglio」シナノキ
「spigolo」エッジ、縁
この3つの言葉、留学中には
知っていたはずなのに、もうすっかり
頭の中から消えていたのでした。
石膏を塗ると消えてしまう。
もう2度と忘れないように。
コンスタブル展と額縁の謎 4月12日
三菱一号館美術館で開催中の展覧会
「コンスタブル展」に行きました。
なんと・・・展覧会は1年以上ぶり。
我ながら信じられませんけれども。
さて。
この展覧会ではもちろん19世紀イギリスの
美しい風景を描いたコンスタブル作品を
ぼんや~り観て心を洗うのが目的ですが
実はもうひとつ。
額縁にある謎があって、実物が見たかったのです。
▲最後の部屋にあった撮影可の作品
「虹が立つハムステッド・ヒース」
1836年 カンヴァス テート美術館所蔵
この額縁はおそらく19世紀のオリジナル。
上部をご覧ください。
スライド式の仕組みと突起があります。
これは一体なんだ・・・?
▲本展では厚い無反射ガラスが入っていました。
先日、京都の「ガクブチのヤマモト」さんの
インスタグラムにこの謎があったのです。
山本さんが「これは一体なんだ??」と。
その後、わたしもどうしても気になって
イタリアの額縁史先生に尋ねました。
先生がさらにロンドンのナショナルギャラリー
額縁部門の方に問い合わせてくださり
とうとう謎が解けたのでした。
「額縁の表からガラスを出し入れできる仕組み」
なのですって。
当時のロンドンは産業革命真っ只中で
大気汚染もひどかったとか。
(おそらく石炭の煤でしょうか)
ヨーロッパでは今も昔も一般的には
油彩額縁にガラスは入れないのですけれど
当時は室内に飾る油彩画も煤で汚れるほど
大気汚染がひどかったから、だそうです。
なるほど・・・。理由は分かりました。
だけど、具体的にどのような仕組みで??
実物を見ましたけれど、その仕組みは
想像するしかありません。
ガラスのサイズはおそらく、
左右は額縁窓と同寸法で、上下の寸法が
5~10mm程度大きいのではないでしょうか。
で、下のカカリ内側にサンがあって
ガラスを表から差し込んで、
上の金具をスライドさせて留める、と。
そんな風に想像します。
突起は引っ張る取っ手なのか、
はたまた押してガラスを動かすのか
これは謎なままです。
▲展覧会見学後に外に出ましたら
コンスタブル的な空と雲が。
いつか実際にガラスの出し入れを
しているところを見学したい。
額縁の仕組みをじっくり見たい。
などと夢見ています。
いつかきっと実現したいです。
三菱一号館美術館 5月30日まで
花を見て思う 4月08日
あっという間に咲いた桜は、やっぱり
あっという間に散って
もうつつじが満開になっていたりして。
庭のライラックを摘んで生けたら
部屋が日差しで暖かすぎたのか
これもあっという間にしおれました。
なんだか・・・早すぎる!と思うも
コロナ禍は一向に終わる様子もなくて
じりじりと焦げそうな気持になります。
早く去ってほしいものは去らず
待ってほしいものは待ってくれない。
ままなりませんね。
・・・などと愚痴を言っていても
わたしの時間は待ってくれないのでした。
するべきこと、できることをするのみ
でございますね。
完成に向けて準備しよう 3月29日
このブログで2020 Firenze として
昨年のフィレンツェ滞在記を
話し続けておりますが、
あの旅は額縁彫刻修行でした。
グスターヴォさんの工房に通い
必死で作った額縁は
ひとまず彫刻を完成させて帰国しました。
ですが、じつはまだ外側に一周
縁彫刻があるのです。
作業の合間に完成させましょう!
▲持ち帰った彫刻木地と参考にした本の写真
いつもいつもお世話になっている
千洲額縁さんにお願いして
ジェロトンの細い棹を送って頂き、
外周に取り付けました。
▲ボンドで貼り付けてから彫ります。
上の写真、金属の輪(というかC字型)
で固定していますが
この金具もグスターヴォさんから
お土産で分けていただきました。
バネの利いたC をぐいっと開いて
はめると思いの外しっかり固定します。
▲C をあてた部分には小さな穴ができるけれど・・・
留学先の修復学校でも使っており
日本で探したのですが見つかりません。
それもそのはず、職人さんが自作するとか。
古いベッドのスプリングなのですって。
これまたアイディアですね。
やっぱり似て非なる 3月25日
同じサイズ、同じデザインで
装飾技法を変えた小箱を
作ってみました。
グラッフィート装飾と
純金箔の上に卵黄テンペラを塗り
模様に沿って絵具を掻き落とし
下の金箔を見せる方法
パスティリア装飾です。
石膏盛り上げ。ボローニャ石膏地に
ボローニャ石膏液を垂らし描きして
レリーフ状も模様を作る方法
左のパスティリアには
錫箔を貼りました。
同じサイズの小箱だけど
錫のほうが大きく見えるような。
面白い。
似て非なるふたつです。
兄弟というか、いとこくらい?
額縁の作り方 33 錫箔を貼る 比べると 3月15日
先日お話しました錫箔ですが
とても使いやすい箔でした。
銀箔ともホワイトゴールドとも
ちがう深い色です。
比較してみました。
上の写真は左が今回作った錫箔箱
右はホワイトゴールド箔の箱です。
ホワイトゴールドとは、金に
パラジウムや銀などを混ぜた合金だそうです。
ホワイトゴールドは反射が白く
繊細で華やかな輝きな印象、
錫は輝きは少ないけれど
暗い色で重厚感がある。
錫はよりひんやりしています。
同じようで全く違う箔の色です。
海外の額縁工房では
銀箔ではなくホワイトゴールド箔を
使うことが多いようです。
錆びないからでしょうかね、やはり。
ちなみにイタリアの額縁史の先生に
伝統的に錫箔をに使うことはないのか
聞いてみましたが
「無い。金箔か銀箔のみ。」
とのお答でした。
錫は古くからある金属ですのに
なぜ使われなかったのでしょうね。
いろいろ比較して楽しみました。
ほかの箔も試してみたい!
イメージからイメージをつなげる 3月11日
最近は小箱のおはなしが続いておりましたが
額縁も作ります・・・もちろん。
暖かな印象のバラの油彩画のために
淡い色の額縁を作ろうと思います。
木地にボローニャ石膏を塗りみがき
内側の端先に純金箔の水押し。
そして角に線刻で模様を入れましょう。
あまり目立ちすぎないように
柔らかでクラシカルなイメージで考えます。
ふむふむ。
線刻道具はわたしの愛用五寸釘・・・。
そして淡いベージュに全体を塗りましたら
模様部分に一段暗い色をのせて
線刻がやんわりと見える程度まで持ち上げて
さて。どうだろう。
今回、額装予定のバラの作品は
すでにお客様のお手元に納まっており
わたしは昨年秋に一度拝見しただけ
あとは写真からの印象で製作しています。
なかなか作品の印象がさだまらず
額縁のイメージが決まりづらく
悩み深い製作になっております。
イメージからイメージをつなぐのは
たしかに悩み深いけれど
やりがいのある面白い作業です。
響いて届いた言葉 3月01日
もう何年も前に、カウンターの席で
偶然となりになったオジサマから
突如いただいた、ある言葉があります。
お店の紙ナプキンにボールペンで書かれていて
お酒の席の一興といった感じで帰り際に
「この言葉を君にあげよう」と渡されたのでした。
わたしの身の上話もしていませんし
お悩み相談をしたわけでもなく、
わたしは同席した方々の話を
聞いていただけだったのですけれど。
だけど、その時のわたしの心と脳に
ドカーーン!と入り込んで、
あまりの衝撃にぎょっとした記憶と共に、
未だにこの紙ナプキンは見えるところに置いています。
いまは目に入るたび、肩をポンとたたいて
励まされている気持ちになります。
そうして「ああ、そうだな」と落ち着きます。
「心配するな、工夫せよ」
タイミングと言葉 必要とする人にバシッと届いて
ガチャッとはまった瞬間だったのですね。
ものすごく個人的だけど、
ものすごく衝撃的な出来事ってまれに起きます。
このオジサマ、どなただったのか
なぜわたしにこの言葉をくださったのか
もはや知る由も無し。永遠に謎なまま。
でも知る必要もないのかもしれません。
この言葉、生涯たいせつにします。
似て非なるふたつ 2月25日
相変わらず小箱のおはなし。
同じサイズ、同じデザインでも
ちがう装飾技法で作ってみる試みです。
どちらもボローニャ石膏下地ですが
上の完成している小箱には
全面金箔を貼ってから卵黄テンペラで
彩色後に、模様を細かく削り出す
「グラッフィート」技法で、
下の白い現在制作中の小箱は
下地とおなじボローニャ石膏を
垂らし描きして盛り上げを作る
「パスティリア」技法で。
完成したら、きっとまったく
印象の違う二つの小箱になりそうです。
たのしみです。
アボリジニ風 2月22日
オーストラリアにあるオルガ山、ご存じですか?
この山の写真を額装するご依頼がありました。
真っ赤な夕焼け空に黒々とした山がそびえる
力強い作品です。
ご依頼くださった方のイメージやお好み、
お家のインテリア等をふまえてご相談した結果
アボリジニアンアート風にしましょう
と言うことになりました。
わたしは実は・・・今回までオルガ山の存在も
いわゆる「アボリジニ・アート」も知らず・・・
いやはや、自分の興味の狭さを恥じるばかりです。
気を取り直し、いろいろと検討しまして
ドットで円を散らばせることにしました。
(どこまでもアボリジニ「風」でございます。
ご容赦ください。)
▲ランダムに円を下描き。色は7色に決めて、
そこにお箸を利用してドットを入れていく。
▲色の順番など考えすぎると固くなる。
自分の感覚を信じるのみ・・・。
今までのわたしとは別世界の
カラフルで楽しそうな額縁になってきました。
作っている時、外は寒い一日でしたが
気持ちは明るくてワクワクして
なんだか新しい扉をこっそり開いた気分です。
少しずつ増える 2月15日
ここしばらく励んでいる小箱制作は
順調に進んでおります。
いくつか以前に作ったものも含みますが
集合写真を撮ってみました。
左上の一番大きな青い箱が
片手の平に乗るサイズです。
最小のものはOKサインの輪に
(親指と人差し指で輪を作る)
すっぽり収まります。
こうして写真で客観的に眺めますと
偏りや改善点が見えてきました。
ふむふむ・・・でもまぁ、かわいいかも。
いや、まったくの自己満足であります。
まだまだ増える予定です。
再燃の予感 2月11日
先日、まとめて何通か手紙を書く機会があって
とても久しぶりに封蝋をしました。
あぶって溶かした蝋を封筒にたらして
印を押すというもの。
この封蝋をひとつ押すだけで、ただの手紙が
ぱっと古典的なヨーロッパの雰囲気になるのです。
▲久しぶりすぎて蝋の適量もコツもすっかり忘れている。
もう10年以上使っていなかった封蝋ですが
なんだかとても楽しくなって、
あたらしい蝋が欲しくてネットで探しはじめたら
蝋を溶かす炉のようなものやスプーンなど
いろんな道具がどんどん出てきて
物欲が増す一方なのでした。
「封蝋をするためだけの美しい道具」
必要ない。でも欲しい。でもいらない・・・。
ああでも、欲しいなぁ。
封蝋熱が再燃しそうな予感です。
じゃんじゃん作ろう 1月28日
2度目の緊急事態宣言が発令されて
市が尾の Atelier LAPIS 古典技法教室は休講
田町の Tokyo Conservation の仕事も休み
お茶の稽古も休み・・・
幸いにもご注文いただいている額縁制作は
ありますけれど、発注した木地の到着待ちやら
なにやら(まぁつまり、そういうことです・・・)
自宅の作業部屋で好きなことができる時間が
とても増えました。
何する?
小箱を作るのだ。
じゃんじゃん作るのだ!
楽しく過ごしたいと思います。
ムフフ・・・。
ishigaki-2 1月18日
先日ご覧いただきました石垣模様の額縁は
黒色に塗装して完成いたしました。
タイトルは「ishigaki-2」にしました。
いつものように、黒色の下に赤褐色を塗って
深みを出し、艶消しに仕上げました。
ちなみに初めて作ったときは白木色仕上げでした。
▲2015年の展覧会時の写真。今回よりずっと大きい。
写真は篠田英美さんによる。
同じ木地を使ったデザインの額縁でも
サイズと色を変えると違う雰囲気になるものです。
わたしは普段、白木色(いわゆるナチュラルカラー?)
で仕上げることはほぼ無くて、2015年の ishigaki-1 は
新鮮でもあり落ち着かない気分でもありました。
今回は慣れた黒で仕上がって(もちろんお客様の
ご注文が黒だったからです)
ホッと落ち着きつつも、他の色も模索したいような。
真っ白とか・・・いつか作ってみたいと思います。
「works」内「modern」にこちらの額縁をアップいたしました。
どうぞご覧下さい。
「いつか」を現実に 1月14日
新型コロナで落ち着かない日々にくわえて
個人的にも少々落ち込むことがあって
ここはひとつ、自分で自分を励ますと言いますか
なにか目標を立てたほうが良いかな、
と思いました。
以前から「いつかできたら良いな、エヘヘ」
などと漠然と考えていたことを
実現に向けて動こうかと思っています。
小箱の展覧会です。
まだどこの画廊をお借りできるか
いつ開催するのか
いったいいくつ小箱を作るのか
まったく未定ですけれども
(なにもかもコロナ禍状況次第)
この場で皆様にお話ししてしまえば
覚悟も決まるのでは、と自分に期待しつつ。
初めてのグループ展では胃を壊し
その次の2人展では蕁麻疹でボリボリになり
「もう2度と展覧会などするものか」と思ったけれど
3度目の正直です。
時間の余裕があって、ひとりで行うなら
きっと大丈夫。
すこし光が見えてきました。
メノウ棒の遠い思い出 1月11日
大学2年の夏に学校の企画で行ったヨーロッパ旅行。
その時にフィレンツェで、将来留学することになる
Palazzo Spinerri 修復専門学校を知り
卒業生の先輩方にローマやフィレンツェでお話を伺い・・・
今思えば将来に関する重要な方向を見つけ出した。
そんな夏でした。
その時に訪れたフィレンツェの古典技法画材店
Zecchi で購入したメノウ棒4本(1本は折れてしまった)は
現在制作中の大きな祭壇型額縁でも活躍してくれています。
このメノウ棒を買ったころ、わたしはひたすら
黄金背景テンペラ画模写に熱中していたのです。
なので、メノウ棒を買うぞ!と鼻息荒く行ったZecchi で
「細かい凹凸も平らな面も緩やかなカーブも
きちんと磨けるオールマイティな形のメノウ棒を!」と
ああでもないこうでもない・・・と駄々をこねた記憶があります。
なんと生意気な東洋女学生だったことでしょう。
そんな生意気小娘相手にZecchi のおじさんは
「そうだねぇ、いま作られているメノウ棒はほとんどが
額縁用だからね、君が言うような形は難しいかもしれない。」
とやさしく説明して下さったのでした。
結局わたしは夢のオールマイティ1本をあきらめて
実用的な4本を購入したのですが、心の中では
「額縁なんてどうでも良いのに。絵があっての額縁なのに
絵に適したメノウ棒が無いなんて信じられない!」と
腑に落ちず。無知炸裂でした。
そして経つこと幾歳。
今となってはこの3本が
わたしの額縁制作に大いに役立つことになるとは。
いえ、それ以前に「自分が額縁制作を生業にして
メノウ棒を一生使い続けることになる」なんて
思いもよらない若かりし日です。
このメノウ棒を毎日握る今日このごろ。
ふとよみがえった古い記憶のおはなしでした。
逃げずに大切に 1月04日
あらためまして
あけましておめでとうございます。
2021年お正月の三が日
いかがお過ごしになりましたか。
わたしは、結局いつものお正月どおり
自宅で家族とお節を食べ、年賀状をよろこび
変わりない3日間を過ごすことができました。
毎年・・・と言いますか年を追うごとに
何事もない旧年とおなじお正月を迎える
有り難さを感じます。
▲お節料理も毎年ほとんど同じ・・・
先日の「鎌倉へ」でもお話しましたが
今年はすさまじかった2020年に授かった
「驚くような嬉しいこと」を
諦めないで逃げ出さないで大切にして
過ごしたいと思っております。
そしてその喜びをもっと大きくしたい。
わたしの今年の抱負は「逃げ癖をなおす」
これにいたします。
いま決めました。
年末にどんな気持ちで今日を振り返るか
ちょっと怖いですけれど、
それもまた楽しみにしようと思います。
▲そしてお雑煮もほとんど同じ。
さて、新しくなった日常へ戻ります。
機嫌よく過ごす一年に!
あけましておめでとうございます 1月01日
旧年中はありがとうございました。
新春を迎え皆様のご多幸をお祈り申し上げますと共に
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
令和3年 元旦 KANESEI
シミーズか、シュミーズなのか。 12月28日
年末の大掃除、ほんの少しだけしております。
寝室はさておき(おかせてください)
作業部屋はやはり大切にしたいところ。
この作業部屋は東西と南の三方向に窓があり
とても明るいのが素晴らしいのですが
道から丸見えですのでカーテンが欠かせません。
大掃除ですからカーテンもガラガラと洗いました。
そうしましたら・・・東窓のカーテンがびりびりに。
ネットに入れなかったわたしが悪いのです。
長年の紫外線で劣化もしたのでしょう。
急きょホームセンターに走り、麻のカーテンを買いました。
いままでの白レースより落ち着いた色ですし
道からも見えづらくなって部屋の居心地もアップです。
▲いままでより一回り大きいサイズにしましたので
ギャザーも寄ってカーテンらしい雰囲気になりました。
さて、タイトルの「シュミーズ」ですが
びりびりになった古いカーテンが、あらためて見ると
いわゆるシュミーズ(ワンピーズ型下着)なのです。
レースのデザイン、布の雰囲気なにもかも。
今までシュミーズ的な布を窓にぶら下げていたのかと
少々無言の境地になりましたが、これはこれで
明るくエレガントなカーテンでありました。
わたしが幼いころ、母がわたしにシュミーズ
(綿製でレースなど無い)を着せていたのですが
当時は「シミーズ」と呼んでいたことを思い出します。
だいぶ大きくなってから「あれは『シュミーズ』
と呼ぶのである、シミーズではない」と知りました。
そしておそらく、今は「スリップ」と呼ぶのです。
だけどいまだ勝手に
「シミーズは綿で子供用、シュミーズはシルクで大人用」
と思っております。昭和的であります・・・。
Buon Natale 2020 12月24日
メリークリスマス!
いちにちフライングですけれども。
今年も無事にクリスマスに
たどりつきました。
お疲れさまでした。
つぎの2021年のクリスマスは
きっともっと穏やかな気持ちで
迎えることができているでしょう!
いや、もう迎えることに決めました。
今日よりまた軽々と飛び越えて
気持ち新たに参りましょうぞ。
諸々を捨てるときなのか 12月21日
ことしの秋から最近まで、なぜか
ずっと長い間愛用していたものや
気に入っていた食器がぞくぞくと
壊れるのです。
毎日使っていたマグカップと昼食用の皿、
金継していたアンティークの砂糖ボウルふたつ、
なんども修理して履いていた大切な革靴、など。
どれも思い入れがあるので扱いにも気を付けていて
食器はぶつけたり落としたわけでもないのに
ある日突然に、持つとぱかっと割れてしまうのです。
革靴も、はっと気づいたら革が破れていた。
どれもが「とてもうつくしく壊れた」のには驚きました。
食器も靴も、修理しようと思えば可能だったけれど
手放すことにしました。
と言いますもの・・・
なにげなく読んだホロスコープに
「いまは執着を捨てるのに適したとき」とありました。
物以外にも思い当たる執着があったので
それ以来、他の占いも気になって見るようになったら
おおよそどの占いにも
「心身の整理をしましょう」
「断捨離をして部屋を整えると吉」
「執着心と物を減らせば新しいものが入ってくる」
とあるのでした。
占いは楽しむ程度に、と思っているわたしですが
ここまでいろんな占いに同じことをお勧めされているなら
まずは物から手放すことにしました。
これらの物がわたしの執着心も一緒に
持って行ってくれたら良いな、と期待したりして。
だけど物は物。心は心。あたりまですけど。
いろいろ捨てられないのは自他ともに認めるわたしです。
心の執着も手放せたら楽になるのでしょう。
でもこればっかりはなかなか難しい課題なのです。
努力目標としておきます。
何かに似ている 12月17日
2015年の秋に、友人のフォトグラファーと
ひらいた写真と額縁の2人展のために作った
「ishigaki」という額縁があります。
なんとなく、フィレンツェにある
メディチ・リッカルディ宮殿の外壁の石垣
(石垣ではなくて石組の壁ですが)に似ているな
と思って作った額縁なのです。
溝の入った既成品の木地を使って
互い違いに切り込みを入れただけなのですけれど
シンプルで、ちょっとだけ美味しそうでもあって
(香ばしいショートブレッドに見えなくもない)
なかなか可愛らしいデザインだな、と
我ながら思っております・・・。
Radio Bruno Fiorentina 12月10日
久しぶりにイタリアに行くと、まずは
ヒアリングに慣れなければなりません。
わたしが拙いイタリア語を話すのはもう
友人知人(お店の方も)に許していただくとして
ヒアリングだけは!1週間くらい過ぎてようやく
緊張状態から脱する感じなのです。
これはいかん・・・今がこれじゃあ
年々悪くなる一方なのでは?!ということで
イタリアのラジオを聴くことにいたしました。
なんて便利な時代でしょう、スマホアプリで
オンエア中のラジオが聴けてしまうのですね。
2月滞在中に通ったグスターヴォさんの工房では
いつもラジオが流れていて、耳に残っています。
グスターヴォさんとおなじ局「RadioBrunoFiorentina」
を見つけてさっそく視聴開始です。
ここは日本のAMラジオのような雰囲気です。
▲数え切れないほどあるラジオ局、その中から
「RadioBrunoFiorentina」を発見。
ニュースや宗教に特化した局もありました。
なにせフィレンツェのラジオ局ですので、
コマーシャルもスーパーマーケットの
週末のセールのご案内とか、かなりローカル。
それが面白く懐かしいのです。
もちろん聞き取れないことも多いですし
政治経済やニュースなど、単語から想像しかできません。
でもDJのおしゃべりなどは一緒に笑っちゃったり。
流行のイタリアンポップスやスラング(?)など
「今の生きたイタリア語」に触れています。
語学の本を見ながら唸っているより良いかも?
気が向いたら他の地方局、ヴェネツィアやローマの
放送も聞いてみようと思います。
方言やイントネーションの違いも聞けて面白そう。
つぎにいつイタリアに行くことができるか
今もって不明ですけれど、準備だけはしておきたい。
ヒアリングは大事だよ・・・と思っている毎日です。
気分転換はおしまい 12月07日
古色を付けて完成しました。
デザインは額縁本「CorniciXV-XVIIIsecolo」に
掲載されている16世紀末の額縁デザインから
拝借しました。
あいかわらず入れる物のあてはありません。
空の小箱ばかり作ってどうするの・・・ですが
まぁ楽しいですから良いかなぁ。なんて。
「works」ページ内「other」にアップいたしました。
どうぞご覧下さい。
アレッサンドロ・アレッサンドリの息子 11月30日
今年はもしかしたら無いかもしれない
と思っていた「小さい絵展」ですが
無事に開催されるとのこと、ほっとしています。
毎年暮れの恒例行事ですから。
こうした「決まりごと」があるほうが
日々に目標や区切りがあって健康に過ごせるようです。
外出自粛期間中にのんびりと描いた模写
フィリッポ・リッピの「アレッサンドリ祭壇画」
部分模写の額縁を作りました。
シンプルだけど、穏やかな表情に合っているかな
と思っています。
▲この青年はアレッサンドリ君。
彼の父親(アレッサンドロ・アレッサンドリ氏)が
この祭壇画の注文主で、自分と二人の息子を
祭壇画の中に登場させているのだそうです。
1440年頃の制作・・・600年近く前の作品。
展覧会については、改めてご案内させてください。
気分転換に 11月26日
制作中の額縁の金箔作業に疲れて
気分転換に金箔作業をする、という
よく分からないことをしています。
結局のところ、わたしは金箔作業が
好きである。
ということに尽きるのですけれども。
ハハハ。
これから磨り出し、古色付けです。
かわいい小箱になりますぞ。
もしそれが薔薇なら、咲くだろう 11月19日
すでに2020年も終わりが見えてきて
いったい今年は何だったんだろう・・・と
呆然とするような、でも振り返ると実に
色々とあった一年でありました。
まだ何か大きなことが起こるかもしれないけれど
2020年はすでに終わった気でおりまして、
早くも次の2021年に希望を抱いています。
コロナ禍で計画も予定も、希望と夢も
ブツリと切られてしまって
初夏にはちょっと取り乱したりしたことを
思い出しています。
そして秋が深まってきて、ようやく
心身が落ち着いてきた感覚です。
イタリアのことわざに
“Se son rose,fioriranno” という言葉があるのを知りました。
直訳すれば「それが薔薇なら咲くだろう」と。
「なるようになる」とでも言いましょうか。
「成ると決まっていることは、何をしようとも成る。」
いや、なにかもっと前向きな美しい表現があるはず。
諦めたとかではなくて、なんと言うのだろう
「人事を尽くして天命を待つ」かな?
でもこんなに大げさな感じではなくて。
▲初夏に咲いた我が家の薔薇。見事でした。
わたしのイメージで、ありきたりですが
「柔らかく前向きな気持ちで、
日々できることをする努力を続ければ
やがて希望が叶う日も来るでしょう」
・・・とでも思っておきます。
Se son rose,fioriranno
希望を薔薇に表現するところが
イタリア人ってとてもすてきだな、と思っています。
秘密の左手は 11月16日
先日ご覧いただいた秘密の左手は
金箔をメノウで磨き、古色を付けて完成しました。
完成後にわたしが「かわいい!」と叫んだら
家族は「こわい!」と叫んでいました。
そうかなぁ、こわいかなぁ。
まぁ、手だけですからね、こわいかもしれません。
だけどイメージしていた「イタリアの古い聖像から
取れてしまった左手は、秘密に大切にされていた」
という物語は、そんなに悪くないと思うのです。
▲仏像風からも脱却した・・・と思うのですが。
なんだかとっても気に入った左手です。
グスターヴォさんに写真をおおくりしたところ
「次は右手を作ってあげましょう・・・」とのこと。
わーい、うれしい!
右手もいいけれど、右足もいいなぁ!
きっと右足もかわいいだろうなぁ、などと
図々しいことを想像しております。
何とかなる。たぶん。 11月12日
大きな祭壇型額縁は、着々と進んではいるのですが
なにせ大きいものですからスピードがゆっくりで
気持ちは焦ります。
予想外の事で計画通りに作業を進められなくなって
急きょ違う部分から、可能な方法で作業継続です。
中断にならなくてよかった、と思っています。
その時になってみると、案外と慌てないものですね。
まぁ何とかなるし、こっちがダメならあっちから。
経験って大切ですね。
それなりの経験が積まれていれば計画変更も可能。
年々図太くなってきている気がします。
それも悪いことばかりではないかも。
秘密の左手 10月29日
2020年2月に木彫修行でお世話になった
わたしの師匠グスターヴォさんから、帰国時に
いろいろとお土産をいただいたのですが
その中に、木彫りの小さな手がありました。
グスターヴォさんが以前、彫像の手を修復するときに
作ったのだけど、形が違うからと作り直しになって
そのボツの手をもらっちゃったのでした。
ボツと言ったって、爪の形まで彫ってあるような
とても美しい左手なのです。
▲35mmくらいの小さな木彫りの左手
ピアノの上のお気に入りコーナーに飾って
しばらく楽しんでいたのですが、思い立って
金箔を貼ってアンティーク風にしてみることに。
▲ボローニャ石膏を塗って磨いて、赤色ボーロ。
▲仕事が終わったあと、夜に箔を貼りました。
なんだか仏像の手に見えてきた・・・けれど
いやいや、これから磨いて古色を付けたら大丈夫。
イタリアのどこかの教会にある古い聖像の手が
取れてしまったのだけど、こっそり拾った人がいて
いまも大切にされている、なんて雰囲気になる予定です。
cassetta-1 つづき 10月26日
16世紀のフィレンツェで作られた cassetta 額縁
そのレプリカ制作のつづきです。
先日は四隅の点打ちによる装飾を終えたところまで
お話しましたが、今日から中央部分のグラッフィート
つまり絵具の削り出し装飾と言いましょうか、
こちらを開始いたします。
マスキングしていた部分、そして金箔の上に
黒の卵黄テンペラを塗ります。
▲またもや黒と金の組み合わせ。
なんだか一気に派手になりました・・・。
絵具が乾きましたら、チャコペーパーを使って
下描き模様を転写いたします。
(黒地にはパステルカラーのチャコペーパー転写が
見やすくて便利です。)
そしていよいよ絵具の削り出しです。
▲額縁右にあるGペンを使って
金箔の上の黒テンペラ絵具を削り落とします。
絵具の下から美しい金が見えてきます。
いやもうほんと、この楽しさと言ったら!
ひとりでニヤニヤ、眺めてはよろこび、
また作業に戻るの繰り返しなのです。
この削り出し作業は、少々間違えたとしても
また黒テンペラで補彩して削り直せば大丈夫。
やり直しの利く技法なので気持ちも楽ちん!
細かい作業が苦にならない方には
ぜひともお試しいただきたい技法です。
しあわせな悩み 10月19日
今までに無く大きな祭壇型額縁制作中です。
このサイズはわたしの小さな作業部屋に対して
そしてわたしの体力に対しても最大と思われます。
鼻息荒くわっせわっせと彫ったり削ったりして
はっと気づくとすでに夕方。
床には今までに無く大きな削り屑が散らばっていて、
掃除を始めるとおもむろに、ものすごく腕と肩が
痛くなっていることに気づく!
いやもう、作業中は楽しくて仕方がないのだけど
夕飯時にはお箸を持つので精一杯というのが
目下の悩みであります・・・。
cassetta-1 10月15日
最近はどうも彫刻した額縁ばかり気になって
摸刻もはかどっていたのですけれど
気分を変えて平面的な装飾をしようと思い立ちました。
16世紀半ばのイタリア・フィレンツェで作られた
美しい額縁のレプリカです。
「a cssetta」というスタイル。カッセッタとは
イタリア語で箱を指しまして、つまり箱型の額縁です。
木地を組んで下ニカワを塗って、ボローニャ石膏。
ここまでは先日の「留め切れを作る」で
ご紹介した木地なのですが、この木地に
装飾模様の下描き線刻を入れてからボーロです。
これもいつも通りの作業。
金箔を貼り磨き、いよいよ装飾の開始です。
この額縁、形はシンプルなのですけれど
小さい世界に装飾がぎゅっと詰まっています。
四隅には点打ち、中央にはグラッフィートと
さらに点打ちの両方が入るという凝りようです。
いやもう、楽しくて楽しくて!
▲オリジナル額縁の装飾拡大写真。ぎっちりです。
まずは四隅の点打ち作業から開始します。
相変わらず「目が、目がぁ~・・・」と
眩しさに耐えつつ、ひたすらに何千何万
(大袈裟ですかな)と点を打つ2日間
ようやく四隅の装飾を終えたのでした。
在宅ワークと「ご機嫌は自分で作るもの」 10月12日
わたしはもうずっと前からなのですが
基本的にひとりで在宅ワークです。
自宅にある作業部屋でガサゴソと
作業をしていると、考え事がはかどります。
はかどると言うより考えすぎると言いましょうか。
手を動かしていると、頭の半分は実際の作業について
残る半分はまったく関係のないことを考えています。
2015年にも似たようなことを書いていますので
もうわたしのクセというか性格なのですね。
前向きなこと、計画とか準備とかを考えるなら良いけれど
わたしの場合は「それをいま考えても仕方がない」
というような事が多いのが問題なのです・・・。
わたしの考え事は「考える」というか「想像する」ばかりで
悪い方へぐるぐる螺旋を降りていってドツボにはまるパターン。
何もない(だろう)ところに自分で問題を作って
勝手に落ち込んで閉じこもるのは、もう何なのでしょうね。
ひとりでいる時間が長すぎるのか、ひまなのか。
自分が考える(想像する)ことさえままならないのに
ましてや相手のあることなど、どうしようもありません。
他人が心の奥底で考えていることなど知る由もなし。
だけどそれを鬱々と想像してしまうのです。
▲削り屑がイタリアのパスタ「オレッキエッテ」に
似ているな、お腹空いたな、なんてことも考える。
朝のラジオでパーソナリティーの別所哲也さんが
「ご機嫌は自分で作るもの」と言っておられました。
まさにまさに。
いやはや、わたしのスローガンですな。
別所さん、ありがとうございます。
青い光が降ってくる 10月05日
2020年の中秋の名月、その翌日の満月。
ご覧になりましたでしょうか。
当日より雲が多くてよりドラマチックでした。
寝る前に撮った写真には、青い光が写っていて
まるで月からこちらに向かって飛んでいるような?
「青い光が月からのしあわせの贈り物になって
わたしに降ってくる」そんな風に感じたのでした。
レンズの反射とか、そんなことだとは思うけれど
楽しい想像を膨らませるのも、まぁ良いではないか・・・と
穏やかな気持ちになって眠りました。
サンソヴィーノの双子 強烈・・・ 9月17日
金箔を磨き終え、いよいよ箔塗りつぶしで
黒彩色をいたします。ううむ。
フィレンツェの師匠パオラは水彩絵の具を使いますが
わたしはアクリルグアッシュのジェットブラックと
カーボンブラックを混ぜたもので彩色します。
金の上は水溶性塗料ははじかれてしまいますので
これまたいつものように Fiele di bue 雄牛の胆汁液を
少量絵具に足します。
▲7mmの平筆と0号の細密用の筆を使って彩色します。
でも、あれなんだか、えーっと・・・
わたし、こんなに強烈な額縁を作るつもりは
あまりなかったのだけど。
と思うような額縁になりつつあります。
▲金と茶色や黒の組み合わせのサンソヴィーノは
存在するのです。左の額縁を参考にしたのですが。
男性的な(わたしのイメージですが)彫刻に
コントラストの強い金と黒となれば
否応なく強い印象になるのは分かっていたけれど
それにしてもこれは強烈。
このサンソヴィーノ額縁が流行したのは16世紀ですが
当時はこんな完成したばかりの真新しいサンソヴィーノ額縁に
肖像画を入れたりしていたのです。
この額縁が引き立て役に回るくらいの肖像画・・・
さまざまな想像が膨らんでしまいます。
▲金も黒も生々しくて目に刺さる派手さ。
さて、今回の実験「金塗りつぶし作戦」は
今のところ問題なさそうです。
当然と言えば当然か。
塗りつぶす場合ときっちり分ける場合とでは
ラインのイメージがほんの少し違うけれど、
それを改めて理解できたように思います。
あとは古色付けで完成です。
この強烈コントラストでは終えられません・・・。
サンソヴィーノの双子 自称ジォットの弟子として 9月10日
いよいよ箔作業をいたします。
この額縁、オリジナルは全面金箔が貼られていますが
今回はアレンジで金箔と黒色の組み合わせにする計画。
どこを金にしてどこを黒にするか検討・決定しまして
ひたすらに箔を貼ります。
ちいさな額縁ですので、使った金箔は4枚+αでした。
▲こちら参考にした額縁は全面金箔。
そしていつものように夜なべをしてメノウ磨きです。
必要部分だけ磨いたあと、コットンで強めに拭くと
ボーロに残った余分な箔が取り除けます。
▲とはいえ黒にする予定部分にも箔が残っています。
今回の悩み、といいますか以前からの悩み。
金と色の組み合わせのデザインの場合、余分な金をどうするか。
色で金を塗りつぶすか、きちんと取り除いてから色を塗るべきか。
それが問題なのでございます・・・。
以前はボーロを箔部分にだけ塗り、余分な金は取り除き
2手間多く作業をしておりましたけれど、今回は思い切って
もう全面にボーロを塗っちゃって、余分な金は塗りつぶしちゃう!
なぜかと言うと。
ジォットの作品を見たからなのであります。
▲ホーン美術館所蔵ジォット作「聖ステパノ」
色々な角度から見ていたら、頭の一部分は箔の上に
描かれているのが分かったのがわたしの大発見でした。
いちいち箔を取り除かず、気にしないで描いてしまう。
そうか、まぁそりゃそうかもね・・・と納得したのでした。
(マスキングテープも紙やすりも売っていない時代)
この発見といいますか、ジォットから学びまして
自称ジォットの弟子のわたしとしては箔塗りつぶしに
トライすることを決めました。
次回は「ジォット秘儀(?)塗りつぶし大作戦」決行です。
サンソヴィーノの双子 石膏とボーロ 9月03日
サンソヴィーノの双子木地は
ひとつは練習台、もうひとつが本番として
どうにか彫り終わりに到着しました。
▲左が練習台。パテ部分を影に隠して記念撮影・・・
まずはパテが痛々しい練習台から石膏作業開始です。
今回使ったのはエポキシパテ木部用で、
彫った材より硬く密度も高いのですが
いままで何度か使った経験によりますと
石膏~箔仕上げの下地に使っても大丈夫なようです。
▲真っ白になってパテが隠れて一安心。
さて、いつもの辛い石膏磨きはのご報告は割愛しまして
箔の準備、下地のボーロでございます。
今回もまたいろいろと悩みはあります。
まずはどんな色のボーロにするか。
わたしの額縁史先生にご相談したところ
「真っ赤。典型的なヴェネツィアのボーロ色にするように。」
とのことで、普段あまり使わない赤ボーロを
ガサゴソと奥から探し出しました。
わたしが普段使っているシャルボネの赤ボーロより
赤が強いゼッキオリジナルの赤ボーロを使います。
▲ゼッキのボーロにおまじない程度シャルボネボーロを足しました。
あまり意味はないけれど、安心感のためと言いましょうか。
いつもより気持ち厚めに塗りました。
見慣れない赤色に塗りあがったサンソヴィーノ。
蛍光灯下で見ると乾いた部分が赤というか
紫がかったピンクに見えます。
▲紫ピンクもこれはこれで可愛らしいような。
さて、これで箔の準備ができました。
あとは箔を貼るだけ・・・ではあるのですけれども。
まだ悩みはあるのです。ううむ。
サンソヴィーノの双子 その後 8月27日
先日ご覧いただきましたサンソヴィーノの
双子額縁は、どうにか彫り終わりが近づきました。
とは言え、これはふたつのうちのひとつ。
もうひとつは悲しいかな、練習台の犠牲となって
パテで修正されつつ控えております。
▲だいぶ良い感じ。
双子で同時制作と言っても、なぜだか同じにならない。
職人とは同じものを同じように繰り返し作ることが
できなくてはいけないんじゃ・・・と思いつつも
まぁ今回はひとつは練習台、ひとつが本番と考えて
「同じ失敗を繰り返さなければそれでよし」
としようと思っています。
▲下の額縁が「練習台」、パテで補修されているのを
隠しつつの写真撮影・・・
さて、練習台のほうはパテを隠して取り繕うために
石膏を塗るほかありませんけれども、
もうひとつはまだ仕上げを決めていません。
どうしたものか。
まだ時間はあるので悩んでみます。楽しい悩み。
飛ぶのじゃ! 8月20日
このコロナ禍がはじまって、運動嫌いなわたしの
運動量はますます減る一方
そして身体は重くなる一方。
友人と話すと、みんな散歩をするとかランニングするとか
それぞれ頑張っているのです。
わたしもどうにかせねば・・・と思い立って
手に入れたのは縄跳びの縄です。
なにせ続けられるか自分が信用ならないので
高い器具を最初から買うのもナンですし、
あきらめがつく価格の縄跳びでございます。
▲いかに室内でできるか、ひとりでできるかにこだわる。
絨毯の上で縄跳びをする無謀・・・
高校生以来の縄跳び、3分飛んで1分休んでを3セット。
縄跳びで疲れた記憶もなく、前飛び後ろ飛び交差飛び
遊んでいた記憶だけだったのにいざ始めてみたら、
ただの前飛びの飛び方も忘れたのか
10回と続かない! 2セットで脚はガクガク
滝のような汗と動悸息切れ・・・
我ながら呆然とします。
そして意外なことに縄を回す二の腕も
パンパンに疲れるのです。
ようやく最近はもう少し続けて飛べるように
なりましたけれども、たかが縄跳び、されど縄跳び。
一説によりますとジョギングより負荷があるとか。
もう少しがんばって続けてみようと思います。
ダイエットになって、ふくらはぎと二の腕も
引き締まって、ついでに体力が付けば
などと期待してニヤニヤ飛んでおります・・・。
サンソヴィーノの双子 8月06日
ロンドンのナショナルギャラリーで2015年に
開催された展覧会のカタログである
「THE SANSOVINO FRAME」掲載の額縁を
摸刻することにいたしました。
▲木地はいつものように千洲額縁さんにお願いしました。
ふたつ同時制作しようと思います。
なぜふたつか・・・それはですね、
ほぼ9割がた失敗するであろうと思っているから。
いえ、もちろん失敗はなるべくしないように
必死に考えて計画するわけですけれども
サンソヴィーノスタイルの額縁はとにかく
難しい(わたしにとって)のです。
▲見本の写真より。シンプルに見えますけれど・・・
ねじれた帯の流れる角度、渦巻きの角度、
ちょっと外れるとすべて台無しになる・・・という
恐ろしいデザイン(わたしにとって!)です。
だけどチャレンジしたくなってしまう。
ひとつ目で失敗したら、すかさずふたつ目に
取り掛かって・・・という風に作業を進めると
失敗理由も忘れませんし、ひとつ目の
リカバリー方法も見えてくる。
二本立て制作はなかなか良い感じです。
(労力は2倍、いえ3倍4倍ですけれども)
前にも言いましたが 8月03日
額縁制作のさいごの仕事は、作品を額縁に納めること。
金具を取りつけたり裏板を閉じたり
小さなネジを締める作業がおおいのです。
で、使うのはドライバーです。
いままで、なぜか家にあったドライバーセット
(パーツが6本とグリップが付属セットの)を
使っており、さして問題はありませんでしたが
先日ホームセンターへ買い出しに行ったさいに
一本売りのドライバーを買ってみました。
そうしたら、なんとまぁ使いやすいこと。
いままではガッと握って本気でまわすところを
新しいドライバーは、ちょいとつまんでまわせる感じ。
握りやすい→回しやすい→力が要らない
つまり早くきれいに仕上がるのです。
いやぁ、びっくりしました。
▲左が新しいドライバー、右がセットの愛用ドライバー
でも今後は右の出番はほとんど無くなりそう。
けっして高い買い物ではないのですよ。
数百円で買えるドライバー、されどドライバー。
いままで何だったの・・・。
ものすごく得した気分になっております!
以前にもお話した記憶がありますけれども
道具って本当に大事ですね。
夜のお手紙は危険 7月27日
「夜に書いた手紙は朝に読み返してから投函すべし」
と昔から言われていますが
ブログもきっと同じですね。
このブログは友人にあてた手紙のような気分で
書きつづけています。
夜に書いたブログは日中に書いたブログと
内容が違う気がするのです。
日中には額縁の制作方法とか手順とか
より具体的なことが多い一方で
夜に書くブログは考えていることとか思い出とか。
かく言う今日のブログもご想像通り夜に書いています。
夜に書く方が感情を表しやすいのでしょうか。
深夜に気持ちのままにどんどん書き連ねた文章を
朝に冷静に読み返してみたら
「おっと、あぶないあぶない・・・」なんてこと
じつはわたし、結構な頻度であるのです。
だからやっぱり朝に読み返したほうが良さそうです。
とても個人的な内容は手紙やメール、ブログではなくて
顔を見ながらお話したいです。
そうは言ってもいまは会うこともためらわれたり
遠くて会いに行くこともままならなかったり。
なので、せめて電話でね。
気の持ちよう 7月20日
いまってとても便利な時代で、海外にいる友人とも
会話をするように手軽にメッセージや写真を
送りあうことができるのですね。
先日、金箔作業で必死になってキリキリしているときに
イタリアの友人から「おーい、何してるの?」と
気軽なメッセージが届きました。
わたしは「今は金箔作業中だよ~」と返したら
「いいね!金箔仕事はリラックスできるよね」
なんていう返信が来たのでした。
なぬ??金箔作業はリラックスできる???
読み間違えたかと思うほど意外な答えだったのですが
その後も作業をしている間、考えていました。
そうか、わたしがキリキリするような作業内容で
リラックスできる人がいるのだ。
それなら、わたしだってリラックスできるんじゃない??
そう思ったら、なんだか気分が楽になりました。
はっと目からうろこが落ちる感じ、そして
肩の力が抜けて血の巡りが良くなるような感じ。
同じことをするなら鼻歌まではいかずとも
気持ちを楽にしたいものです。
結局わたしは金箔作業が好きなのですからね。
シルヴァーノのカルトッチョ 8 完成 7月13日
シルヴァーノ・ヴェストゥリ氏のカルトッチョ額縁
箔作業も終わりまして、これにて完成です。
箔をどこまで置く(貼る)か
どこまで磨くか磨かないか・・・悩みましたが
貝殻の内側、C字部分の内側、葉の裏側を
磨かずに艶消しで仕上げました。
派手なデザインですので、艶消しがあると
すこし抜け感ができて落ち着くかと思っています。
裏にあったパオラの書き込みだけは
記念として残しました。
“A SCARTOCCIO VESTRI SILVANO”
古色付けはせず、このままで。
ひらひらと薄くて繊細な
カルトッチョらしい表現ができたのでは、と
眺めております。
シルヴァーノさん、いかがでしょうか。
摸刻の摸刻 7月09日
数年前につくった彫刻額縁 hori-makuha-1
のデザインでデッサン用の額縁を、というご注文を
いただきまして、制作中でございます。
▲以前つくった額縁を参考にしながら作業します。
もともとこの hori-makuha-1 額縁もイタリアの
古い額縁を参考に摸刻した額縁なのですが
今回はその自作の摸刻を参考にするわけでして・・・
摸刻の摸刻といいましょうか。
自分で作ったのに忘れている部分もあったりして
不思議な気分でした。
同じデザインをもっと頻繁に作っていれば
そのデザインのための作業が身に付くのでしょうけれど
そんなに機会があるわけでもない場合は
やっぱり見本や参考はある程度必要になるのでした。
▲彫り終わりましたらさっそく石膏!
この額縁も全面を純金箔で装飾して古色仕上げの予定ですが
以前の hori-makuha-1 より古色は穏やかにしようと思います。
もうすこし繊細な雰囲気の額縁になる予感です。
シルヴァーノのカルトッチョ 7 箔作業 7月06日
黄色ボーロ一色でいこうと決めた
シルヴァーノ・ヴェストゥリ氏のカルトッチョ額縁
ひっぱり続けましたがようやく
いよいよ箔作業の朝です。
わたしの黄色ボーロは赤ボーロに比べて粒子が荒いのか
粘りがないのか、カサカサとして箔が付きにくいのです。
なのでまずは念入りに1層新たにボーロを塗りまして
▲ボーロの質は色によるものなのか分かりません・・・
メーカーやロットによっても違うかもしれません。
内側からはじめます。
問題は外側の立体的な葉の部分です。
なにせ3Dですし奥に深いので、箔の大きさやら
置き始めの場所やら考えてグズグズしておりますと
あっという間にメノウ磨きのタイミングが来てしまって
箔を置きながら磨きながら同時進行です。
▲一日作業してもここまで。
遅い自覚はありますけれども、なんともはや。
でも徐々にコツがわかってきましたよ。
やはり箔は小さめに切った方が小回りが利いて
複雑な凹凸にも置きやすいようです。
翌日には箔置きも終えようと思います。
ふくれた顔で見上げたから 7月02日
昨年2019年の・・・いつだったかに
思いついて作りはじめた小さな額縁は
途中でなんだかやる気がなくなって
箱に入れたまま隅っこに置いていました。
昨日ひさしぶりに箱を見かけて思い出し
ふたを開けてみたら、額縁がむっとした
ふくれっ面でわたしを見上げたのでした。
(そんな気がしたのでした。)
ひさしぶりに見ても、やっぱりあまり
やる気はおきないのだけれど、あまりにも
いじけた風情だったので再開を決めました。
可愛そうなことをしました。
「ごめんね、仕上げますからご機嫌直してね。」
などと話しかけながら(変ですね、自覚しています)
彫り進めました。
▲この「小さな葉と実の集まり」がすこし・・・鳥肌。
いやいや、こういうデザインなのですよ。
デザインの細かさに対して木材が柔らかすぎて
それがやる気の起きない原因だったのです。
まだ仕上がっていませんけれど、なんとか
雰囲気は出てきました。
掃除して整えて、金箔を貼って仕上げるつもりです。
シルヴァーノのカルトッチョ 6 ボーロの冒険 6月29日
シルヴァーノ・ヴェストゥリ氏のカルトッチョ額縁
しつこく続けます。
思い返してみれば、自分が彫った木地以外に
一から石膏を塗って磨いて、と作業をするのは
初めてです。それだけに緊張するといいますか
彫刻した方への敬意をもって作業をしたいと思います。
それで・・・問題はボーロの色選び。
前回は黄色ボーロをベースとして4回塗り終えました。
その上に、凸部分に赤か暗赤か茶色か
とにかくもう一色のボーロを塗ろうと思ったわけです。
それが一般的な方法ですのでね。
で、思い出したのは先日得た知識
「フィレンツェでは茶色のボーロが多い」です。
茶色を塗って無難にいくかな。でもなぁ。
今回の額縁は、とにかく軽く薄く、を目指しています。
ボーロの色は箔の仕上がり色にも大変影響します。
茶色は重いし、赤だと派手だし、どうしたものか。
それで・・・黄色ボーロのみで箔を置いたらどうだろう、
と思ったのです。
▲前回に塗り終わった黄色ボーロ。
愛読書(?)の「Repertorio della cornice europea」
をぱらぱらと見ていますと、こんな額縁を発見しました。
▲これもいわゆる「カルトッチョ額縁」と思われます。
解説に「preparazione a bolo giallo.」とあります。
「黄色ボーロで金箔下地をつくった」ということ。
それもフィレンツェでつくられた額縁で。
ふむふむ、ならば今回も黄色だけでも良いのではないか?
しつこく悩んだ挙句、金箔下地のボーロはこのまま
黄色一色で行くことに決定いたしました。
黄色ボーロで箔置き・・・じつは苦手なのですよ。
だけど、まぁこれも経験、練習です。
次回、箔置き開始です。さらにつづきます・・・。
シルヴァーノのカルトッチョ 5 黄色ボーロ 6月22日
制作を続けます。
ボローニャ石膏を塗り、紙やすりで磨きます。
なにせ薄くと心がけたものですから
ちょっと磨けばすぐに木が出てしまう。
でもこれは仕方なし。
あまり気にしすぎてドツボにはまってはいけません。
端先、葉のなめらかなカーブはきちんと磨き
丸の連なりは表面をかるく研ぐ程度で
隙間をひとつづつ磨いたりしません。
葉の裏側も貝の内側もぬりっぱなしです。
ただ、そうして磨きのメリハリをつける
(手抜きともいう・・・)ためには
正しい濃度の石膏液を適量、適度な厚さで
塗っておく必要があります。
つぎは金箔下地のボーロです。
この額縁のように凹凸がはげしいものには
とにもかくにもまず黄色のボーロを塗ります。
▲シャルボネ製の黄色ボーロ、黄色というかオレンジ色
これまた薄溶きの黄色ボーロを4回塗って終えます。
▲葉の裏側などにもぬりました。
そしてつぎ、黄色の上に塗るボーロは
明るい赤か暗い赤か、はたまた茶色にするか。
そこでふと思い出しました。
またまたつづきます・・・。
オークションのオンライン見学 6月18日
フィレンツェにあるオークションハウスPandolfini では
古い額縁専門のオークションがあります。
▲2018年4月に行われた額縁オークションのカタログ。
これは終わった後の11月に古書店で買いました。
今年2020年6月17日の現地時間10時から
額縁専門オークションが開かれましたので
オンラインで見学しました。
▲Pandolfini(パンドルフィーニ)の
インスタグラムよりお借りしました。
美しすぎてうっとり。額縁天国!
▲パンドルフィーニのオークションサイト
16日午前10時よりオークション開始です。
オークション開催前には実物が公開展示され、
オンラインカタログでは詳細な写真を見ることができます。
不明な点は電話で問い合わせれば答えてくれるとか。
▲オンラインカタログで出品作品の詳細を見ます。
当日、開始時間にパスワードを入れてログインすると
オークション会場の中継を見ながら入札することができます。
▲中央の女性が進行役。下の画面に入札価格が続々と入る。
入札が終わると木槌で「カン!」と打って落札を知らせる。
入札は会場にいるお客さんに加えて電話でする人
そしてオンラインでする人といて3つの方法で進められます。
表示価格より少し安いところから始まって、
人気の額縁は桁が変わるほどの競り合いになって
見ているだけで戦々恐々、ハラハラします。
テレビや映画で見ていた世界なのです。
約2時間で総数183枚の額縁が競り落とされました。
欲しいものを落札するには素早い判断と度胸が必要!
慣れと自制心も必要かもしれません。
大変に面白い社会見学でした。
いつか現地の会場でも見てみたい。
そして入札してみたい・・・ような怖いような。
シルヴァーノのカルトッチョ 4 さらに考えた結果 6月11日
悩みが尽きないシルヴァーノのカルトッチョ木地です。
いつかこの額縁木地を見本にして摸刻したいと
企んでいるわけですが、それには木地のままが良い。
だけど。
シルヴァーノ氏はこの木地を彫るときに
石膏を塗ってボーロを塗って金箔で仕上げるという
次の作業を考慮していたはずです。
彫りの深さは仕上げによって決まるのですから。
ということは、やはりこれは本来の目的通りの
箔仕上げにするのがベストだろう、との結論に至りました。
やれやれ、悩みすぎましたけれど。
そうと決まればまずは下ニカワを塗りまして
▲目留めのためにウサギニカワを木地に塗ります。
濡れ色になりました。
かなり薄く溶いたボローニャ石膏溶液を
これまた薄く塗り重ねます。
とにかく液溜まりができないように
全体の厚さが均一にムラなくぬれるように
水分の表面張力を利用して塗ります。むずかしい。
▲石膏液の濃度は生クリームくらい。
もちろん泡立てる前の生クリーム。
細めの丸筆を使います。
4層塗って終えました。
これ以上でもこれ以下でもない、と思える厚さ
・・・のつもりです。
つぎは恐怖の紙やすり作業です。
取りもどす 6月08日
6月がはじまって、さまざまなことが
再開しました。
市が尾の古典技法教室 Atelier LAPIS も
1日から講座が再開になりました。
3,4,5月とお休みしているあいだに
3分の1の生徒さんが退会なさいました。
新幹線通学してくださっていた方
ご病気があった方、都心を通るのが不安な方
退会理由はどれも理解できるものばかりでした。
これからどうなるか・・・再開したいけれど
また休講になるかもしれません。
でもぐるぐる考えていても仕方がありません。
ここ数か月で対応も学びました。
出来る限りの予防をして、いまは前向きに。
そして何よりおだやかに。
日々の感覚を取りもどそうと思っています。
シルヴァーノのカルトッチョ 3 考えた結果 6月04日
シルヴァーノ・ヴェストゥリ氏のカルトッチョ額縁
イタリア・フィレンツェの額縁スタイルのカルトッチョ。
そのつづきであります。
分厚い石膏で繊細さがかくされていた彫刻木地、
一晩悩みましたが、石膏をすべて取り除くことに
意を決しました。
ボローニャ石膏は水溶性ですので、何年たっていても
水分を与えれば溶解します。
全部を取り除くとなれば、もう全体を濡らすしかありません。
たらいに入れた水をまわし掛けながら慎重に作業します。
修復用のヘラと歯ブラシを使いました。
▲水に漬け込んではいけません。
水を流しかけてはやさしくこすって取り除く。
慌てず焦らず赤ちゃんを沐浴させるような気持ちで。
濡らしてしまったことで木がふやけてケバ立ったり
膨らんでしまったりするのは仕方のないこと。
ですが紙やすりはかけません。
ちなみに
この木地は比較的新しいので直接水をかけても耐えられますが
古いの額縁修復時などにこの方法は使えません。
コットンで湿布をして石膏を柔らかくします。
くれぐれも古い木地にはご注意ください・・・。
一晩乾燥させてから彫刻刀でケバを取り除きます。
▲奥や葉の裏側など取り除けなかった石膏があります。
でもこれ以上の水の作業は負担です。
彫刻刀の素早い動きも感じられるような
シャープな切り口、繊細なラインが復活しました。
さて。
石膏をさらに取り除いてワックスを塗って
木地のまま仕上げにする選択もあります。
シルヴァーノ氏の彫刻を愛でるならそれもあり。
どうしよう、なにがこの額縁木地にベストか・・・。
さらに悩みはつづきます。
シルヴァーノのカルトッチョ 2 どうする? 5月28日
欠けてしまった木片を接着して
亀裂にはボローニャ石膏を塗ったところの
カルトッチョ額縁です。
乾いた石膏を磨きつつ、彫刻刀で分厚い石膏を
リカットしてみたのですが
▲白いところは彫刻刀で削った石膏部分
いやはや、やはり石膏が厚すぎです。
彫刻のラインが消えていて、リカットどころではない。
せめて貝のモチーフ部分だけでも塗りなおそうと
部分的に石膏を取り除くことにしました。
▲筆で水をひたひたにして
▲石膏がふやけたところをヘラでやさしくこそげます。
▲彫刻ではこんなに繊細な線が入れてありました。
▲4つの貝殻の石膏を取り除いたところ
これではほかの部分も推して知るべし。
このまま続けるか、いっそすべて石膏を取り除くか
一晩考えることにいたします。
ちなみに
カルトッチョというと日本では紙包料理を
指すようですが、イタリア語でカルトッチョとは
つまり紙包・・・。
この額縁デザイン、額縁の解説本によりますと
巻紙をイメージした装飾が特徴とのこと。
(紙というか葉に思えますが、さておき。)
シルヴァーノ・ヴェストゥリ氏彫刻の
カルトッチョ “a cartoccio” ですが
“a Scartoccio”(スカルトッチョ)と呼ぶこともあるようで
フィレンツェではスカルトッチョ、他地域ではカルトッチョ。
おそらく方言的なことだと思われます。
▲フィレンツェのパオラが書いてくれた
シルヴァーノの名前と「スカルトッチョ」
グスターヴォさんもスカルトッチョと呼んでいました。
さらにつづきます。
シルヴァーノのカルトッチョ 1 5月25日
2月のフィレンツェ滞在時に手に入れた
小さな額縁は “a cartoccio” と呼ばれる伝統デザインで
今は亡き額縁彫刻師シルヴァーノ・ヴェストゥリ氏が
手がけたものです。
わたしの額縁師匠パオラから石膏と黄色ボーロが
施されたものを買い受けました。
フィレンツェから日本へ送った荷物のなかで
細かい細工部分が折れてしまったのですが
▲外側220×175mm、中にははがきが入るくらいのサイズです。
とにかく早く直さねば、と思い立ったが吉日。
ひとまず折れてしまった木部は接着します。
▲くるりと立ち上がった葉が折れてしまいました・・・。
シルヴァーノ氏には残念ながらお目にかかる機会は
ありませんでしたけれど、腕も人柄も良い
繊細な人だったと各所で聞いていました。
その上でこの額縁を眺めてみると、どうも
彫刻の繊細さが石膏の厚みで隠されている気がする。
きっと彫りはシャープで細かいラインがあるはず。
ううーむ。ひとまず直したけれども。
なんだか違和感がぬぐえません。
石膏でモッタリしている部分は彫刻刀で
リカットしてみることに決めました。
▲なにか違和感が。
つづきます。
イタリア語に訳してみたら 5月21日
イタリア語の勉強を続けている・・・と
言えるのかどうか微妙ではありますがとにかく、
毎日イタリア語に触れるよう努めております。
いつも手元にあるのはイタリア語教材ですが
ちょっと気分を変えたいと思ったときに
ふと見てみたのが、自分のブログのイタリア語版。
つまり翻訳サイトで機械翻訳された自分の文章を
読んでみるというものです。
▲液晶画面を写真に撮ると水面になる・・・
自分で書いた文章がイタリア語に訳されると
こうなるのか、と新鮮な気持ちになったり
(機械翻訳なのでニュアンスが違う気もしますけれど)
自分が好む言い回しや単語が見えてきて面白いのです。
翻訳サイトによって訳され方も少しずつ違って
比べてみるのも興味深い。
わたしにとって翻訳サイトの新しい使い方になりました。
面白がってばかりでなかなか覚えられないのが
目下の悩みであります・・・。
そんな時もある 5月18日
ご注文を受けて作る額縁ではなくて
「こんな額縁どうだろう?」などと
思いついて試作を作る時のおはなし。
頭の中で描いた額縁の完成図があって
でも制作を進めるほどに、どんどん完成図から離れてしまう。
この額縁とわたしは相性が悪いのか 計画が甘いからか
何をどうしても額縁が、まるで小さな子供のように
「イヤ!」「それはダメ!」「違う!」
と叫んでいるように感じることがあります。
このまま作業を続けてもダメなものはダメ。
いったんこの額縁から離れます。
しばらく時間をおいて考えて、それでもダメだったら?
覚悟を決めてやり直すしかありません。
塗装も石膏もすべて取り除き、木地に戻してリセット。
そしてまた試行錯誤をはじめます。
「その時」は辛いし面倒だし、もう捨てちゃおうかな!
とヤケにもなるのですが、でもまぁ結局、
作り直して後悔したこともないのです。
リセット~再開も「時間はかかるけど悪くもない」と思っています。
新しいことを始める 5月14日
何が苦手かとたずねられましたら
数字と虫と即答できるわたしですが
計算機を片手に寸法を出しております。
▲この雑然とした机は混沌としたわたしの頭の中とおなじ
新しいプロジェクトの準備です。
いままでになく大きな
わたしの身長より高くなるような
祭壇型額縁制作のご依頼をいただきました。
鼻息も荒く張り切っております!
振り返って思い出した 5月11日
金箔を磨き終えてあまりの派手さにおののいた
バルディーニ美術館所蔵額縁の摸刻は
すこしの古色を足して完成しました。
ぎんぎらぎんの金箔がおちついて
彫刻の凹凸、陰影がより見やすくなりました。
今回はオリジナルの額縁の雰囲気を追って
磨り出しはしていません。
古色用のワックスを薄く塗って磨いておしまいです。
後日に虫食い穴をまねて作るかもしれません。
裏には特別な吊り金具を付けました。
イタリアの友人から譲っていただいた鉄の吊り金具は
鍛冶仕事で手作りされた現代のもの、
釘はイタリアの数百年前のものをあわせました。
▲本当に古い吊り金具のよう。
正面から吊り金具の茶色いあたまがひょっこり見えて
なんともかわいいくてたまらんのです。
印象が強くて、あまり需要は無さそうな額縁ですけれど。
どうしてこの額縁を作りたいと思ったのだったかなぁと
振り返ってみたのですが、
この強烈な力強さが感じられるデザイン
内側から外側にむくむくとあふれ出すような
「末広がり感」に惹かれたのだ、と思い出しました。
「works」内「classical」にこちらの額縁をアップいたしました。
どうぞご覧下さい。
会うことを決めている 5月07日
自宅待機が長くなることになりました。
皆さまいかがお過ごしですか。
延長は予想していたとはいえ・・・
いやはや。なんとも。
心と体の健康を保ちたいと思います。
今年の暮れ12月、どのような状況なのか
まだあまり想像できませんけれども
毎年のルーティーン「小さい絵」展に出品できるよう
小さなテンペラ画を模写しました。
フィリッポ・リッピの聖母子像から男性横顔の部分と
ルドゥーテのバラから部分です。
テレビもラジオも消して、音楽をちいさくかけて
遠くの小鳥の鳴き声と風の音を聞いて
ぼんやりとしながら模写する午後などには
まるで何事もなかったころのような気分になります。
会いたい人にはやく会いたいですね。
「これが終わったら、わたしはあの人に会うのだ」
と心に決めています。
短期集中可能期間につき 5月04日
例によってバルディーニ美術館の
額縁摸刻作業のご報告でございます。
なにせ自宅にこもりきりですので
集中して作業を進めることができます。
これもまぁ思いがけない良かったこと、
と思うことにして。
前回に内側の細い部分から箔を置きはじめた
写真をご覧いただきましたが
ひきつづき外側の渦巻き状の部分にも
もくもくと箔を置きまして
メノウ棒で磨いて、金箔の穴を繕ってまた磨いて
ああ、いつまですればいいのでしょうか・・・
と気が遠くなりかけたころにようやく箔仕事が完成します。
ぎんぎんぎらぎら金箔光る・・・
派手にもほどがありましょう。
でもまぁ、一仕事終えて満足。
今夜は晩酌が美味しくなりそうです。
ボーロの色もそれぞれ 4月30日
石膏を塗り、恐怖の紙やすり磨きを終えた
バルディーニ美術館の額縁摸刻は
金箔下地のボーロを塗るところまで来ました。
このボーロには基本的に赤・黄・黒があります。
イタリアでは時代と場所によって
ボーロの色に特徴があるのですが
今回は茶色にしました。
このバルディーニ所蔵の額縁、わたしの予想では
フィレンツェの1800年代のものかなぁ!
などと言っておりましたが大きな間違い、
イタリアの額縁史に詳しい方に教えていただいたところ
トスカーナ地方またはエミリア地方で(Toscoemiliana)
1600年代に作られたものでしょう、とのこと。
▲上の写真はフィレンツェのバルディーニ美術館にある
オリジナルの額縁。2018年訪問時に撮った写真です。
また、その時代のトスカーナでは
主に茶色のボーロが使われていたとのお話から
黄色ボーロに黒と赤を混ぜたものを作りました。
ちなみにエミリアは暗い赤、
ローマ、ナポリなど中央以南は黄色、
ロンバルディア、ヴェネトはオレンジ色の
ボーロを使っていたのが特徴だそうです。
純金箔も当時1600年代イタリアと
おなじ技法と道具で置いて(貼って)います。
激しい凹凸、側面まで貼り込んであるので
金箔の消費量も恐ろしいことになりそうです。
下地の色は大切 4月27日
先日彫り終えた額縁木地 に
水性ステインを塗りました。
仕上がりは金色艶消しなのですが
木地を茶色に染めておくことで
金の発色に深みが出て穏やかになり
かすかな揺れができてきます。
▲沢山の色がシリーズで発売されていますが
わたしは「オーク」色を使う機会が多いように思います。
下地に色を塗るか塗らないか
何色を塗るのか、どのように塗るのか・・・
仕上がりを左右する
とてもとても重要な工程です。
小箱を贈る 4月23日
ご覧いただいておりました小箱は
無事に完成し、贈り物にしました。
イタリアの友人へささやかな感謝と励ましに
雑貨とともに送りました。
普段より日数はかかりましたが
無事に手元に届いたようです。
▲側面は黒一色です。
▲蓋と身の合印として中央に赤を少しいれました。
写真だと見づらいのですが・・・。
蓋をぱかっと開けますと
今回は中に貼った別珍も黒です。
黒が好きな人ですので、お好みに合わせて。
イタリアの友人知人に元気に再会できる日が
一日も早く来るように願いつつ
わたしに何ができるか考えています。
「works」ページ内「other」にアップいたしました。
どうぞご覧下さい。
今年の福の神様は 4月20日
毎年かわらずに美しい花を咲かせてくれる
KANESEI自慢の黄色いモッコウバラは
KANESEIの福の神様でもありまして、
毎年この花が咲くころは大忙しなのです。
たいてい5月の大型連休の頃、遊びに行きたい
真っ盛りの時期なのですが。
今年はほかの植物同様にモッコウバラの
満開がずいぶんと早いようです。
この春、福の神様モッコウバラの花は
慰めと励ましの神様にバトンタッチ
なのかもしれません。
桜もつつじもお花見に出かけることができず
ひたすら息をつめて待機しているわたしたちに
「まぁまぁリラックスして、わたしをご覧」
と話しかけてくれているように感じています。
ご機嫌取りの日 4月16日
最近は皆さまと同様に外出も減って
自宅での作業時間が伸びています。
しばらく放置していたこの額縁
フィレンツェのバルディーニ美術館所蔵の額縁摸刻の
制作を再開することにいたしまして
先日ボローニャ石膏を塗りました。
なにせ急いではおりませんから
パーツ毎に丁寧に塗りました。
上の写真では側面はまだ塗っていません。
内側の細かい彫りにまず塗って乾かして、
周囲のおおきな彫り部分に塗って乾かして
そうしてようやく側面に取り掛かろうと思います。
こうして時間をかけて自分のために作業できるのも
今だからこそかもしれません。
出かけたり人に会ったりする機会が減って
気分が鬱々とすることもありますけれど
いままで先延ばししていたことに手を付けたり
「自分のご機嫌をとってなぐさめる日」というのも
悪くない過ごし方かなぁ、と思っています。
小箱のたのしみ 5 4月13日
小箱制作のつづき、そろそろ仕上げです。
装飾を入れ終わった小箱には
フィレンツェのゼッキで購入した
gommalacca シェラックニスを塗ります。
このニスでテンペラ絵具が箔とより密着し
安全に扱えるようになります。
▲奥に見えるガラス瓶が gommalacca
アルコールベースのニスです。
このニスはすぐ乾きますので、引き続き
古色付けの箔磨り出しをします。
スチールウールで角を擦って下地を出します。
グラッフィート模様の上は触らずに。
そしていつもの古色ワックスを薄く塗り
乾いたら磨いておしまいです。
内側には黒い別珍を貼りました。
これで大切なものを入れても大丈夫。
この小箱制作の手順はいつもの額縁制作と
同じなのです。
ただ小さくて立体で、というだけ。
でも気分が変わって、好きな模様を入れられて
手のひらに乗せて眺めることができて
とても楽しい作業です。
小箱のたのしみ 4 4月06日
ひきつづき小箱制作についてご紹介します。
前回テンペラ絵具をのせてグラッフィート装飾の
準備を終えました。
今日は乾いた絵具のうえに模様を転写して
掻き落とし、つまりグラッフィートします。
▲トレーシングペーパーに描いた下描き模様を
細い棒でなぞって転写しますが、この場合は
カーボン紙等使わず、絵具に凹み線を作ることで
模様が見えるように転写します。
上の写真の中央、黒い絵の具の部分
うっすら白い線で模様が転写されているのが
見ていただけますでしょうか。
カーボン紙を使うこともありますが
今回は細かい装飾模様なので下描きも細い線で。
凹み線のみの転写にしました。
さて、いよいよ掻き落とし、削り出し、です。
普段は竹串やネイル用のオレンジウッド等を
細く削って掻き落としに使っていますが
今回は細い線を出すために、Gペンを使うことにしました。
▲箔を傷つけないように慎重に掻き落とします。
▲ちょっと厚めに絵具層を作ったので
思いがけず絵具が硬く掻き落としにも苦労します。
蓋の模様はフィレンツェの旧サンタッポローニア修道院
(旧聖・アポローニア修道院)入り口にあった
テンペラ画の衣装模様をお借りしました。
この旧修道院はカスターニョの最後の晩餐で有名な場所ですが、
このテンペラ画はカスターニョではなくて・・・
作者名をメモするのを忘れてしまいました。やれやれ。
▲聖人の衣装のすそ模様だった・・・。
ひとまず全面に模様を入れ終わりました。
保存しておいた絵具で修正をして
なんだか気に入らなかった部分に追加で刻印を打って
今日の作業は終わりです。
小箱のたのしみ 3 4月02日
先日ご覧いただいた小箱制作のつづきです。
ピカピカに磨き終えて刻印を打ったら
グラッフィート装飾のためにテンペラ絵具をのせます。
グラッフィートとは、磨いた箔のうえに
テンペラ絵具を塗り、絵具が乾いたら
細く尖らせた木製の棒(竹串なども可)で
絵具を掻き落として下の箔を見せるという技法です。
さて、箔の上にテンペラ絵具をのせるにあたり
とにかく同じ厚さになるように、というのがコツ。
ヒタヒタに絵具を塗るというか置きます。
卵黄の量は・・・まぁいつもと同じくらいで大丈夫。
今年イタリア滞在中に見たグラッフィートは
いままでわたしが行っていたよりも
絵具層が分厚い、ということが分かりました。
ですので、ちょっと今回は厚めにこってり
絵具をのせることにしました。
ちなみにテンペラ絵具は乾くと卵黄が
酸化重合して水には溶けなくなり
一度乾いた絵具を使うことはできませんが
ラップをしてさらに密封容器に入れておくと
3~4日は使うことができます。
その場合、卵黄に防腐剤を入れることを忘れずに。
▲混色して作った絵具はグラッフィート修正用に保存。
絵具が乾きましたらいよいよグラッフィートで
装飾模様を入れます。
これがまた楽しいのですよ。
小箱のたのしみ 2 3月26日
純金箔をぴかぴかに磨いたら
刻印で模様を入れましょう。
刻印入れの方法にはいろいろとありますが
今回はメノウ棒を軽く打って入れます。
力を加減して点の深さ、大きさが揃うように。
点の刻印が入るとさらに金のキラキラが増します。
小さくてギュッと詰まった世界へ
作業を続けます。
小箱のたのしみ 3月23日
先日から、またひとりがさごそと
小箱を作りはじめました。
金箔の額縁を修復する作業の途中で
すこしのお楽しみです。
金箔はピカピカに磨けました。
これから装飾模様を入れます。
黒と赤でグラッフィートの予定。
イタリアのルネッサンス時代の模様です。
またこちらで制作過程など
ご覧いただこうと思っています。
荻太郎先生「顔」の額縁 3月19日
昨年ご覧いただいた「バレリーナ」に続き
荻太郎先生の作品を額装させて頂きました。
サインは入っていませんので
発表なさるご予定で描かれたものでは無いかもしれません。
だけどタッチの力強さと勢い、迫力には
見るたびに圧倒されてしまう。
微笑んでいる様子は仏様を思い出させます。
守られているような、叱咤激励されているような
そんな気がします。
額縁はごくシンプルに
細い木枠につや消し金、 線刻を入れました。
いかがでしょうか。
いつものデザインだけど 3月16日
イタリア・フィレンツェでの彫刻修行後
はじめての額縁彫刻ですので
なんだかちょっとワクワクするような
自分にハラハラするような
変な気分になっています。
あちらで入手したあたらしい彫刻刀も使いつつ。
フィレンツェ修行のおはなしは
もう少し落ち着いたころに、と思っております。
まずは日々できることを地道に。
花でも愛でて 3月13日
なんだか落ち着かない毎日ですね。
わたしは元々自宅でひとり作業が日常ですので
あまり変わらない日々を過ごしておりますが
やはり息苦しさを感じています。
庭のヒヤシンス一家は変わらずに今年も
美しい花を咲かせてくれています。
作業の途中で花を愛でております。
皆さまもどうぞお元気でお過ごしください。
五寸釘を握りしめて 3月05日
真夜中に、恨みの藁人形に打ち付けるのは
五寸釘・・・
ですけれど、わたしの五寸釘は打たずに使います。
それももっぱら日がある時間でございます。
線刻するニードルとして重宝しています。
この五寸釘、つまり長さ150mm、太さ5mmの大きな釘ですが、
さすがにそのままでは細くて作業がし辛い。
革テープを巻き付けて握りやすくしています。
▲これぞ本当の五寸釘。
▲ちょっと太くてシャープな線が彫れます。
この重くて太い五寸釘、これを深夜に生木に打つなんて
相当な気力体力が必要なことでしょう。
なんともはや。
この五寸釘、大学生の頃に道で拾いました。
誰が落としたんだろう。
藁人形と一緒に持っていた人でしょうかね。
あまり考えないようにしています。
それにも理由があるのです。 2月27日
KANESEI額縁の側面には、金箔はあまり貼りません。
黄茶色の金箔に近い色を塗って仕上げます。
その理由を聞かれることがあるですけれど、
まずはフィレンツェの額縁師匠マッシモ&パオラが
そうしていたから、というのが始まりではありますが
わたしなりに理由を言うとすれば。
純金箔って結構な迫力があります。
特に古色を付けたりすると迫力に重みも加わって
ともすると額縁の印象が強くなりすぎてしまう。
また、デッサン用などの細く繊細な額縁で
側面にも箔を貼ると太く重く見えるような気がします。
額縁は真正面からより斜めからのほうが
人の視界に入る場面は多いのです。
側面に「金ではないけれど金に似た色がある」と
印象が軽やかに、薄味になると言いましょうか。
作品を鑑賞するために正面から観るときには
しっかり箔の装飾があり作品とバランスをとりつつ、
斜めから見たときには額縁の存在を主張しすぎない、と言うか。
上手く言えませんが「押しが減る」ように
わたしは感じています。
額装する作品やサイズ、額縁のデザイン、飾る場所
そしてお客様のご注文によって
側面に金箔を貼る額縁も、もちろんあります。
とくに祭壇型額縁など側面に貼らない選択はありません。
正面には金箔を貼るのに側面には貼らないなんて
手抜き、ケチ(びんぼっちゃま風?懐かしい)と思われると
残念なのですけれど、理由もあるのです。
結局のところ好みの問題ではありますけれども
ご参考にしていただけたらと思います。
みんな臭かった 2月20日
なにやら匂い(臭い)の話がつづきますが。
Atelier LAPIS の生徒さんがある日
「古いウサギニカワがあるのだけど、まだ
使えるかどうか・・・」とおっしゃるので
まずは見てみましょう、と持って来ていただきました。
下の写真、左が古いニカワ、右が現在のニカワ
どちらもホルベイン社製で
水10:乾燥ニカワ1の割合で作った溶液です。
▲乾燥ニカワは古くても、カビたりしていなければ使えます。
古いニカワ液の蓋を開けた途端、すさまじい臭い!
一度も洗ったことがない野良犬が濡れて蒸れたような
何とも言えないケモノの脂臭といいましょうか。
ビンの下にはすこし濁った澱もあります。
そうそう、これこれ!このニカワの強烈な臭いは
とても懐かしいのです。
わたしが初めてウサギニカワを使ってテンペラ画を
描いていた大学生の頃(かれこれ随分前の話・・・)
ウサギニカワと言えばこの感じ、それはそれは臭くて
研究室がこの臭いで満たされ、鼻がマヒしていました。
古いニカワは今のニカワより不純物が多いのでしょう。
だけど、この古いニカワのほうが古典的といいますか
ルネッサンス時代のニカワに近いでしょうし、気分的にも
「古典技法で制作しているのだ!」と盛り上がります。
数年前から「ニカワを溶かしても臭わないな、
鼻は楽だけど、なにか違う・・・」と思っていたのです。
久しぶりにクッサ~~い「ザ・ウサギニカワ」の臭いを嗅いで
なんだかとても楽しくなったのでした。
この臭い、フラ・アンジェリコもレオナルド・ダ・ヴィンチも
みんな嗅いで臭がっていたのでは・・・。
匂いの記憶 2月17日
先日、近くに用事があったのですが早めに着いたので
ずっと気になっていた「旧小坂家住宅」を訪ねました。
世田谷トラストまちづくり
二子玉川駅から少しあります。静嘉堂文庫美術館近く。
急な坂道沿いにあって、敷地面積は広いけれど
いわば崖とその周囲、といった感じの場所。
今は雑木林の敷地が公園になっているのと、
崖上にある邸宅が無料公開されている施設です。
世田谷区の指定有形文化財になっています。
訪ねたとき、他にお客様はだれもおらず
広いお屋敷内を迷いながら見学しました。
お茶室や内倉、ティンバー風の応接室など
とても凝った造りのお屋敷。
一番奥にたどり着いたら、そこは主寝室でした。
▲シャンデリアや石膏装飾の天井がすてき。
奥の盾状のものはこの家の主、小坂順造氏の肖像彫刻です。
左のカーテンの向こうがサンルーム。
サンルームからの眺めが素晴らしいのです。
庭の向こうには富士山も見える明るい部屋で
とても落ち着いた雰囲気、ほっとしました。
ほっとしたのは雰囲気だけではなくて、
なぜかとても良く知っているにおいがするのです。
もうずっと前に亡くなった祖父の家のにおい。
もちろん祖父の家はこんな立派なお屋敷ではありませんでしたが
独特の同じにおいがします。
古い家特有のにおい・・・だけではないのです。
なんと表現して良いのか分からないのだけど、
古い家具や少し湿度のある空気の、
絨毯や壁や、あらゆる物のにおい、でしょうか。
近くには、祖父が持っていたのと同じステレオが。
▲ビクターの古いステレオ、レコードとラジオです。
我が家にいまだに置いてあるので見間違えません。
そのほか、サッシではない窓や鍵、建具がそっくりだったりと
あまりに祖父を思わせるものが多くて
ぎょっとするやら懐かしいやら。
部屋着の着物姿の祖父がいても驚かない気持ちでした。
においの記憶って凄まじい。
脳の深いところから突然蘇ってきます。
不思議です。
今までとは違う気持ちで 2月10日
ベルナール・ビュフェ美術館に行きました。
一緒に行った人の希望で立ち寄りましたので
わたしは何となく、大した興味もなく行ったのですが。
久しぶりに、というのもなんですが
とても感動しました。
期待していなかったのも大きいかもしれません。
(失礼な話です、すみません。)
▲写真はベルナール・ビュフェ美術館H.Pからお借りしました。
ビュフェの作品はいままでにも何度か
目にすることはありましたが、正直なところ
あまり好みではなくて流し見していました。
今回、若いころの作品から小品、大作など
まとめて鑑賞することができました。
第二次大戦中にもあきらめずシーツに描いたこと
自画像をずっと描き続けていたこと
特徴的な黒い線が誕生したころのこと
苦悩したこと、感じたこと考えていたことなどなど。
作品もさることながら、専門に扱う美術館なので
丁寧に解説、展示がされていたことで理解が深まりました。
美術館設立者がビュフェ作品にほれ込んで集めた
とのことで、その愛情と熱意も感じられました。
額縁もスタイリッシュでかっこいいものがありました。
ガラスが入っていないので、絵の色艶やタッチが
手に取るようにわかるのも素晴らしいのです。
以前に流し見していたころと比べて
自分の精神状態も経験も変わったからかもしれません。
でも今後またビュフェの作品を観る機会があれば、
きっと今までとは違う心持で鑑賞することが
できるような気がします。
東京からすこし遠いけれど、旅気分でぜひ。
おすすめです。
弟子入り準備 1月30日
普段はご注文を受けた額縁を作りますが
「自分のために」作る額縁もあって、
新しく準備をはじめました。
ヴェネツィアで18世紀に作られた額縁をサンプルに
似たような形の木地で制作予定です。
▲女性的な花模様、C字のモチーフがロココ
中央の平らな部分”specchio”がヴェネツィアらしいデザイン。
▲外側にもう一周彫刻がありますが後ほど足す予定です。
・・・下描きに描き落とし発見・・・。
まだバルディーニ美術館額縁の作業が残っていますが
(これからボローニャ石膏を塗らなければ)
また新しい額縁を準備し始めたのは
2018年秋に会った彫刻師グスターヴォさんに
短期弟子入りさせていただけるからなのです。
この木地と彫刻刀を担いで遠路フィレンツェへ
行ってまいります。
修行の成果など、またご報告させてください。
2回分の幸運 1月27日
先日1月9日に所用があり車を運転していましたら
鳥のフンがフロントガラスに・・・!
わたしが「ぎゃー!」などと叫んでおりますと
助手席にいたTokyo Conservasion 修復スタジオの
室長が「”運がつく”って本当だよ。俺も顔に
鳩のフンが落ちてきたことがあったけど
その年は記念すべき良い1年になったからね!」と
慰めてくださったのでした。
じつはわたし、今年の初詣で並んでいたときに
頭の上に鳥のフンが落ちてきたのです。
お正月早々なんたること・・・と
顔に縦線が入っていた(ちびまるこ風)のですが
室長のおはなしが本当なら、わたしの2020年は
それはそれはもう素晴らしい1年になるに違いない。
▲鳥・・・鶏のから揚げ。田町の老舗にて。
大きなから揚げをハサミで豪快に切って食べる美味。
なにせ9日間で2回もウンに当たるなんて
(それも市街で。森の中ではないのです。)
そうそうあることではありませんでしょう?
▲鳥・・・これも鶏。我が家のクリスマスのご馳走。
こんな写真を撮っているから鳥(鶏)に恨まれた可能性も。
室長の言葉を信じて。
2020きっと素晴らしい1年になるでしょう!
いや、素晴らしい1年になるよういたしますよ!
汚れたガラスは、後日父が拭き掃除してくれました・・・。
運は父にいったかもしれません!
歌会始 2020「望」 1月17日
1月16日は毎年1月半ばのお楽しみ「歌会始」でした。
2020年のお題は「望」、令和初めてのお題に
とても相応しい明るいお題でした。
それぞれの歌を読み上げる人たち7名の方々の
お顔を拝見するのも実は楽しみのひとつなのですが
(皆さんの年相応の変化に自分も同様に感じられたりして・・・)
今年から新たな若者メンバーが加わり心機一転、
20代青年の声も若々しく伸び伸びとさわやかでした。
7名に年齢に幅があるほうがやはり良いのですね。
こうしてまた、新しい時代になったことを感じます。
選歌にいくつか「ああ、そうだなぁ、良いなぁ」と
感じる歌があり、しみじみ。
目の前にその人が見た風景が広がるようでした。
上皇后となられた美智子様の御歌が無いのは・・・
歌会始の楽しみが半減した感じです。
仕方がないことではあるのですけれど。
これもまた、新しい時代ということでしょう。
来年のお題は「実」だとか。
令和3年の歌会始、穏やかに迎えられますよう。
1500年前と同じものを使う 1月10日
少し前のお話ですが、埼玉県行田市にある
「さきたま史跡の博物館」へ行きました。
ここは5世紀から7世紀の大型古墳群で有名だそうですが
国宝展示室にてちょうど企画展開催中でした。
「金錯銘鉄剣」とその精密な復元品の展示です。
オリジナルは錆びているけれど、その迫力たるや!
オーラがただものではなく発せられているような。
権力者の威厳の象徴。
純金で象嵌された文字は今も輝きを失っていません。
復元品は大きさ材質、作り方から研ぎ方まですべて
5世紀ころに作られたままの姿で復元されたとか。
ガラスケースに入っていますがすごい迫力。
目の前に突き付けられたら背筋が凍りそう。
▲右下の剣が復元品。ひどい写真ですみません。
象嵌の様子、刃の輝きが間近で見られました。
鉄剣も驚きの品でしたが、わたしにはこちらも衝撃。
奥には鉄剣とおなじ稲荷山古墳から出土した
道具類も展示されています。いずれも国宝です。
・・・なんだか見慣れた道具がただ古びている、
という感じです。
▲左から砥石、ヤリガンナ、チョウシ、カナハシ、大小のチョウナ
いずれも現在でも伝統建築で使われている道具そのままの姿。
5世紀にはすでに今のわたしが額縁制作でも使うような
ペンチのような、ニッパーのような道具も。
▲サビをとって直せばいまにも使えそう?
そうか、1500年前の職人も同じような道具を
日々使っていたのか
この道具はすでに1500年前に完成された形なのか
感慨深い気持ちになりました。
1500年の時間は人間の進歩に長いのか短いのか?
これで本当にわたしのもの。 1月08日
昨年末に買ってしまったkindle、
手に入れたのが嬉しくて
目印のようなものを付けたくなりました。
▲ケースは白。麻のような色です。
Kindleにどうにかしてタッセルを付けたい。
使わないと溜まったタッセルもかわいそうですし。
でもストラップホールなどありませんし。
日曜の夕方に工作することにいたしました。
秘蔵?のリボンを取り出しまして。
わたしの大好きなDEMELのリボン
Kindleケースの背の幅にぴったりです。
裏に両面テープを貼りました。
内側から貼りはじめ、一番下でタッセルを通して
また内側で貼り付ければ完成です。
これでこのKindleは「わたしのもの」になりました。
タブレットにもつけているのです。
使い勝手の良し悪し、耐久性などは
二の次にしております・・・ハハハ。
抱負達成が抱負である・・・。 1月03日
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
皆様はどこでどのようなお正月をお迎えですか。
わたしは相も変わらず我が家で家族と一緒に
おせちを囲み日本酒をいただき
なかなか幸せな元日でございます。
今年のお節料理、30日31日で突貫工事状態で
作りましたので内心不安だったのですが
(味見はしましたけれど、冷えると変わりますでしょ)
まぁなんとか許容範囲で一安心でした。
▲料理は額縁同様、無心になれる物づくり。
ブログを長く続けて良いことのひとつに
昔の記録が見られることがあります。
毎年のお正月、なにを書いていたことやらと見たら
抱負やらスローガンを掲げておりましたが
それを追求できたかと問われますと、なんとも。
という訳でして、われながら凝りませんけれど
本年2020の抱負は毎年のことながら
「フットワークを軽く心と頭を柔軟に」そして
「その抱負達成に近づく」でございます。
ハハハ、がんばります・・・。
あけましておめでとうございます 1月01日
旧年中はありがとうございました。
新春を迎え皆様のご多幸をお祈り申し上げますと共に
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
令和2年 元旦 KANESEI
Buon Natale 2019 12月25日
メリークリスマス!
ことしもクリスマスになりました。
仕事納めまであと少し、でしょうか。
どうぞお体大切に、穏やかなクリスマスを
おすごしください。
掃除をしなさい 12月23日
フィレンツェにあるバルディーニ美術館所蔵の
額縁模刻はぼちぼちと進めています。
外側は大まかに彫り終わりが近づいて
今は深さ調整と「掃除」をしております。
毛羽やら小さな段、彫り残しを掃除すると
スッキリ整って見違えます。
▲掃除には小回りの効く細い彫刻刀を使います。
留学先の学校で彫刻の授業を受けていたころ
作業中、先生に見ていただいたら
「それじゃ次、少し掃除しなさい」 と毎回言われていました。
自分ではそれなりに掃除したつもりでも
先生の目にはまだまだだった訳ですが
この掃除がいまだに苦手です。
今となっては誰も言ってくれませんから
自分で自分に「もう一息掃除しなさいよ」
と言いつつ作業しています。
掃除は大事です。
分かっちゃいるけど!
できた、ような。 12月20日
kirikami シリーズ四角いバージョン
出来上がった・・・と、思います。
いや、どうかな。
もういいかな、まだかな。
妥協ではないけれど、不安というか。
これで「完成しました」と言って良いのか。
毎度のことながら迷います。
いえ、迷わなかったことがない、が正解です。
ううむ。
一晩おいて朝の明るい陽射しでもう一度見て
それから決めることにします。
凹は凸よりむずかしい 12月16日
制作を続けています。
このデザイン、切紙模様が凹んでいるのが
特徴なのですが相変わらず試行錯誤です。
第1作目のまるいバージョンと違う方法で
この凹みを作っているのですけれど、
どちらの方法にも一長一短あるのでございます。
もっとブラッシュアップさせたい。
平面には凸をつくるより凹をつくるほうが
むずかしいような気がしています。
あっちもこっちもどこででも 12月13日
ご想像の通りでございます。
▲だって年末大セールだったのです!
広告付きのいちばんお手頃価格のもの。
さっそく原田マハ作品を数冊購入したり
無料のものをダウンロードしたりしました。
夏目漱石やら与謝野晶子などは
もう著作権が切れているのですね。
おかげで懐かしい「こころ」など
また読んでみる気持ちになりました。
なにせ家族全員が読書好きで
我が家にはわたしが読んでいない本がまだまだ
山積みですので、ちょっと後ろめたいのですが
それはそれ、これはこれ。
思えばイタリア留学中は日本語の活字に飢えて
友人間で文庫本がぼろぼろになるまで
回し読みしていたのでした。
普段なら読まないホラー小説など読んだりして。
古本屋のあるパリが羨ましかった思い出です。
今はKindleがあれば、どこでも読めますものね。
便利な時代になったものです。
出不精ですがKindleをもって出かけたい気分。
電車で「塩狩峠」を、カフェで「こころ」を、
ついでに新しい作品を探してみたりして
あっち読んでこっち読んで楽しもうと思います。
語学の勉強・・・も、できたら良いな。とか。
あたらしいオモチャを手に入れました。
感想などまたお話させてください。
額縁生まれ変わり 12月09日
ようやく完成いたしました。
▲修復後。欠損を再成形して純金箔を貼りました。
少しの磨り出しをして下地の赤を出し、茶色の古色仕上げ。
▲修復前。金色の塗装と緑青色の古色で仕上げた額縁でした。
上部の欠損部分には金色のペイント修理の跡も。
今まで古い額縁の全面箔貼り直しには積極的ではなかったこと
また、普段とはちがう方法での箔置きをしたことなどもあり
(ミッショーネは部分的に装飾で使うことがメインでした)
下地の整え方や接着剤、仕上げ方法の検討などで
時間を消費してしまう結果になりましたが
理解も深まったという大きな収穫もありました。
お客様には託してくださったことに大変感謝申し上げます。
古い額縁に全面箔貼り直し、いままで避けていたのは
どうにもちぐはぐな印象になってしまう恐れがあったから。
ひどい例えですけれど、お婆さんが若作りしているような。
今回トライして分かったことは、下地を整えて
ある程度の古色を付ければ美しく仕上がるということです。
当然といえば当然なのですけれど、これはやはり
実際に試行錯誤しながら行って自分で理解することが
必要だったということでしょうか。
「山をひとつのぼり終えた」といううれしさを
感じながら完成した額縁を眺めています。
欲しいの?欲しいんでしょ? 12月06日
ここのところ、なんとも気になるのが
Kindle(電子書籍専用リーダー)です。
ものすごく今さらなのですけれど。
紙の本を愛するゆえに遠ざけてきた感もありますが
Kindle の小ささ軽さ、その容量は大変な魅力。
だけど「本」なら貸し借りも自由ですが
kindle は1作品につき1回限り14日間貸せるのみ。
古本は差し上げるのも売るのも可能だけど
コンテンツは売れないようですし溜まる一方?
なにせわたしは石橋を叩いて渡るどころか
渡る人を後ろからじっと眺めて10年経つような人間
と自覚しておりますので、新らしいことには程遠く
ようやく「気になるなぁ」にたどりつきました。
画集やじっくり読み返したい本は「本」を買って
情報や軽い読み物は電子書籍で、と分けるのが
皆さんの使い方なのですよね、きっと。
なんだかんだと自分に言い訳をしつつ
手に入れるような気がしています・・・。
出会っていたのは後で分かる 12月02日
フィレンツェのルネッサンス美術に
わたしが心から興味を持ったのは
NHKのテレビ番組を観たときからでした。
当時、高校3年生です。
それ以来、どうしてもフィレンツェに
行きたくてたまらなくて、
大学進学時は学校主催で行われる夏の旅で
フィレンツェに行ける学校を選び、
結局大学卒業後には両親の許しで
とうとう3年間の留学までさせてもらい、
額縁の本場で制作と修復を学び
身につけることができました。
今もテレビでは、イタリアの
ルネッサンス美術についての番組は
様々に放送されています。
出演のとても若いタレントさんが
幼い――でも一所懸命に――コメントを
話している姿を見ると、
当時の自分と重なるような気がします。
そして今の若い人たちが番組を見て
なにかの情熱を持ったかもしれません。
人生の方向を決めるきっかけやチャンスは
些細なことで、どこででも出会いますね。
そしてそれは後にならないと分からないのです。
わたしにとっては偶然観たテレビ番組が
いま思えば大きなきっかけのひとつでした。
色々な人の「振り返って分かるきっかけ」を
聞いてみたいと思います。
やっぱりやめた。 11月29日
隙間時間で作っている小箱です。
金箔をメノウで磨いてから
卵黄テンペラ絵具数色で彩色しました。
そして放置すること数か月・・・
なんだかな、なにか違うような。
イメージしていたより「乙女度」が高い。
思い切って絵具を削り落として
装飾をやり直すことにしました。
▲金箔の上に白、緑、紫、ピンクでふっくら彩色して
七宝風にしたかったのですが、取り除きます。
金箔がしっかり磨いてあれば
テンペラ絵具はポリポリと除くことができます。
「やっぱりやめた」が可能なのです。
いわばグラッフィート技法と同じこと。
今回は割りばしのお尻で削り(こすり)ました。
さて、すっかり金色に戻ったところで
刻印を打ってみようかな、と思います。
もう少しルネッサンス風味にする予定です。
kirikami にわかに 11月22日
2015年に銀座のギャラリー林さんで行った
写真とKANESEI額縁の展覧会(もう4年前!)に
出品しました kirikami と名付けた円形額縁があります。
たたんだ紙の角を△や〇に切って広げた模様から
このタイトルを付けました。
切紙の模様を額縁上に表現する方法を試行錯誤して
ぐるぐる・・・という記憶ばかり強いのですが
4年たった今、にわかに人気(?)上昇中です。
「この額縁のデザインで」または
「これと同じ額縁に鏡を入れて」などの
お問い合わせをいただいております。
いままでなしのつぶてでしたのに。
不思議ですが、そんなこともあるのですね。
さてそんな訳で、ただいま四角い kirikamiシリーズ
制作真っ最中でございます。
幅広マスキングテープを貼って、模様を転写します。
▲4年前の型紙を参考に四角の模様下描きをつくりました。
そして模様を切り抜きます。
以前、マスキングテープはお手頃価格のものやら
100円ショップのものを使ったこともあります。
でもマスキングテープは良いものを使うのが一番。
とくに切り抜く場合は差が顕著です。
いやまぁ当たり前なのですけれど、品質が完成の良し悪しに
とても影響するのがマスキングテープ、とつくづく思います。
模様の切り抜きを終え、端先の加工もして
(端先の加工、危うく忘れるところでした!)
日が暮れたので今日の作業はおしまいです。
顔料の製作者とアンジェリコのお好みと。 11月18日
先日のテレビ番組で、アドリア海で見つかった沈没船について
いつ、どこの港から出てどこへ向かい、
誰のどんな荷物を積んで誰に送っていたのか
調査する様子を観ました。
その船はルネッサンス時代、ヴェネツィアの総督が
トルコのスルタンの求めに応じて送ったガラスと
その他贈り物を積んでいた船でした。
海中調査し、膨大な資料から探り出し明らかになっていく様子は
とても面白かった!
その沈没船の積み荷に顔料もありました。
赤い顔料の辰砂、白い顔料の鉛白でした。
当時ヴェネツィア産の顔料は品質が良いことで
有名だったそうな。
昨年秋にフィレンツェのサン・マルコ美術館の
赤は辰砂、白は鉛白が展示されていたことを思い出しました。
この沈没船はフラ・アンジェリコの生きた時代の100年も後だし
フィレンツェとヴェネツィアは当時ちがう国であったから
可能性はとても低いと思うけれど、想像が膨らんでしまう。
フラ・アンジェリコはヴェネツィア産の顔料を
好んでいたかもしれない、なんて。
どんな人がどんな場所で、どんな道具で
あの顔料を作っていたのかな、その生活はどんなかな、とか。
ヤマザキマリさんが物語にしてくれたら
とてもとても面白そう!と思ったりしております。
ひとまず使わずに。 11月15日
先日、お財布の整理をしていたら
やや?
平成31年の500円硬貨であります。
ピカピカと美しく財布の中でも目立って輝いています。
これって珍しいのではないかしらん?と思って
小銭入れから別のポケットに入れておきました。
使用済みですけれどきれいですし
ひとまず使わずに、記念に取っておくことにいたします。
平成31年。
令和の時代になって、もうずいぶん経ったような気がしてしまいます。
数十年後、忘れたころに引き出しの奥からこの硬貨を見つけ出して
あの頃は・・・などと思い出すのに使うかもしれません。
小さなかわいこちゃん6 11月13日
メノウ棒での点刻印が終わりまして。
さぁ!お愉しみの古色付けでございます。
▲夜なべ仕事の翌朝、装飾が完成しました。
▲まだ金の色が新しくて生々しいのです。
木槌でのキズ作りはせず、磨り出しのみをして。
今回は彫刻の凹凸に加えて点刻印もありますので
ゆるめに溶いたワックスを筆で塗ることにしました。
筆で塗ったとしても、筆跡が残ったら台無し!
筆につけるワックス量を調整し、塗り方も
伸ばしたり叩いたりこすったり工夫します。
▲凹や点にも擦りこんで輝きを残さない。
ワックスが乾いたら乾拭きして、完成です。
もしも我が家にあったなら 11月08日
展覧会などで素敵な作品を見たとき
ああ、これがわたしのものだったらどんなに幸せだろう、
朝から晩まで手に取ってじっと見たい
なんて勝手なことを想像しています。
先日のニュースで、フランスのお宅のキッチンで
チマブーエのテンペラ画が発見されたと聞きました。
わたしが想像した生活を送った人が現実にいたのです。
専門家が見に来るまで、そのお宅では大切に
でも「普通に」毎日チマブーエの作品を眺めて、
なんならチマブーエの作品の前で料理をし食事をし、
絵は油やら煙やらにさらされていたわけです。
でももう、この絵は今後二度と一般家庭に置かれることはなく
管理された空間でこれからの長きにわたる時間を
過ごすことが決まりました。
極端な変化だけど、こんなことも現実にあるのですね。
このチマブーエの絵にもし心があったら(ありえないけれど)
もしかしたらこのままキッチンで、毎日親しみを持って
愛でられながらの生活を望んでいたかもしれない
などと妄想してしまう。
けれど作品はその価値を認められ、保存修復され、
安全な場所で管理されつつ多くの人に見てもらうのが
誰にとっても良いということなのでしょう。
「実際に自分の手元にあったら」は想像して
楽しむだけのほうが良さそうです。
泥棒も怖いですしね。
小さなかわいこちゃん5&額縁の作り方 11月04日
小さな祭壇型額縁、点の装飾が完成しました。
古色を付けますけれど、ここで裏の処理をば。
この木地は合板を土台にして組み上げてあります。
合板?ベニヤ??チープ・・・と思われるでしょうか。
でも最近の合板はとても良く美しくできております。
反ったり割れたりが少なく丈夫ですし。
さて、裏面と裏板に色を塗ります。
金を使った額縁には、わたしはターナーが出している
「生壁色」というアクリルグアッシュを使います。
イエローオーカーより赤みが少なく、くすんでいて
金との相性が良いように思っています。
絵が接する部分には何も塗りません。
この色以外にも、クリーム色も違和感なくなじみます。
茶色ステイン着色の額縁には裏にもステインを塗ります。
額縁と似た色、もしくはインテリアと似た色が無難です。
この絵具が乾いたら、いよいよ仕上げ。
古色付けでございます。
小さなかわいこちゃん4 10月25日
久しぶりになりました「小さなかわいこちゃん」
小さい祭壇型額縁であります。
金を貼り磨き、いよいよ装飾をします。
▲装飾模様の下描きを作りました。
当初の予定では、金の上にテンペラ絵具を塗り
絵具をかき落として金を出す「グラッフィート」で
ルネッサンス風模様を入れるのでしたが、
ご注文くださったお客様が「せっかく金だし
やはり全面金で仕上げてほしい」とのお話。
合点承知でございます!ということで
細いメノウ棒で点を打って模様にします。
カーボン紙で模様を転写して、点を打つ。
磨かれた金の上のカーボンはティッシュで拭えば
すぐに落とすことができます。
その代わり手で触っても落ちてしまいますから
狭い範囲を転写して打って、また転写して、と
繰り返すほうが安全です。
この技法、なんでしょうか。やはり刻印でしょうか。
メノウによる点刻印、とでもさせていただきます。
この極細のメノウ棒は大変便利です。
額縁やテンペラ画用ではなくポーセレン用。
陶器の絵付けで使うために作られたメノウ棒です。
東急ハンズで購入しました。おすすめです。
落とすとすぐに折れますので扱いは要注意。
てんてん、てんてん、てんてんてん・・・
ひたすらに点々打ち。
今宵もまた「♪か~さんは~夜なべ~をして~」と
歌いながら夜なべ点々作業です。
あの記憶を失いたくない 10月23日
毎年この時期、秋がはじまると
今年は行こうかな、と迷うけれど
結局行かずに冬を迎えてしまう場所があります。
何年も前に行った湖は細い山道を登って行った先にあって、
夏はバーベキューや水遊び、釣りを楽しむ人で
かなりにぎわう場所のようでしたが
わたしたちが行った11月のはじめは誰もいなくて
駐車場はガラガラ、お店も閉まっていました。
とてもよく晴れた風の強い日でした。
澄み切ったつめたい空気、
ひざ丈の草がザーザーとたなびき、水面もさざ波だって
ちぎれた雲が飛んでいきます。
青空が湖面に映るけれど、もっと青く深い。
色と匂いと空気の冷たさがどれも強いのです。
あまりに美しすぎる、と言いましょうか。
今ここと、夢あるいは死後の世界の境のような
この世ならぬ場所のような現実味のない感じで
呆然と眺めました。
美しさの記憶が鮮明で強すぎて、
もう一度行きたいけれど、
あの時とすこしでも違ったら夢から覚めてしまう、
あの記憶が丸ごと失われてしまうかもしれない、
そんな恐怖もあって、それ以来行っていません。
憧れは憧れのままに、
美しい記憶がひとつでもあるなら、壊さないように
大切にしたほうが良いのかもしないけれど。
やっぱりいつか行きたい、と思っています。
額縁用じゃなくても額縁に。 10月21日
いつもお世話になっている額縁材メーカーさんから
新しいカタログが届いて、新商品にわくわくしつつ
さっそく新商品木地を使った額縁を作っています。
アユース材の薄い木地に丸〇とフリルのような
ちょっとした彫刻をしました。
この木地、メーカーさんのお話によると
額縁用ではなくて建材(内装)用として作ったとのこと。
どおりでドロ足(裏側にある、絵を入れる枠)がありません。
▲だいぶ薄くて華奢な木地なのです。
▲裏。ぺらっと薄くて、いわゆる額縁の形ではありません。
ドロ足がないので薄板を組んであるだけ、といった趣き。
たしかに額縁と建築は切っても切れない仲です。
額縁は元はといえば窓枠や扉枠から派生していますから。
建築の様式はそのまま額縁の様式に通じます。
2016年2月に完成した「hori-acanthus-1」額縁は
内装メーカーの棹木地を使って作ったのでした。
この時もやはりドロ足を作りました。
さて、このままではただの四角い木・・・ですので
ドロ足を取り付けます。
▲10×25mmの材を組んで取り付けます。
これから濃い茶色に染めて、ワックスで古色を足して
かわいらしい犬の版画を納める予定です。
新しいデザインの額縁を作る楽しさ、格別です。
平らは良い。 10月18日
つめ込み過ぎているわたしの本棚は
棚板がすこしずつたわんでいましたが
とうとう本を取り出すにも戻すにも
おおきな労力が必要なほどになったので
棚板を交換をすることにしました。
家族に相談したら、奥から長ーい
板が登場しました。
なんと、祖母が使っていたという
着物の洗い張り用の板ですって。
もう何十年も物置で眠っていた板。
反りも無く面取りされて美しいままです。
これを切って、ダボ用のミゾをルーターで入れて
(すべて家族がしてくれた作業です・・・)
無事に棚板2枚を交換することができました。
本が平らに並んでいるってすばらしい。
すっと取ってさっと戻せるってすばらしい。
本体に合わせて茶色に塗ることも考えましたが
祖母が使っていた当時のままにしています。
おばあちゃん、ありがとう。
その作者はいったい誰 10月11日
Lawrence Alma-Tadema
ローレンス・アルマ=タデマ
イギリス・ヴィクトリア朝時代の画家で
古代ギリシャ・ローマや古代エジプト等歴史を
テーマにした写実の作品を残しています。(wikipediaより)
特に古代ローマの神殿や美しい女性の髪、服などの描写は
引き込まれるような魅力にあふれています。
“The Roses of Heliogabalus”
Sir Lawrence Alma–Tadema 1888
見よ、このバラの花びらの描写を・・・!
そのアルマ=タデマ作品には祭壇型額縁が多く使われていて
折々に彼の額縁について調べています。
すでに先月のお話なのですけれど、
東京で観られる場所はないかな、と探したところ
八王子にある東京富士美術館が1点所蔵しており
常設展で公開中、それも9月16日まで!
最終日間近に大いそぎで行ってまいりました。
「古代ローマのスタジオ」という作品です。
絵の詳しい解説は上記リンクをご覧いただくとして
額縁はやはり金の祭壇型額縁がつけられていました。
額縁写真をご紹介できないのが残念ですが
作品が板絵ということもあるけれど、額縁の薄さに驚き。
薄いというだけで繊細さが倍増している印象です。
ボーロは赤色、金に褐色の古色加工がされている可能性。
彫刻の装飾もegg&dart , lambstongue など帯状にシンプルで
柱頭だけ細かい渦巻のイオニア式装飾がある・・・。
とにかく繊細で、石膏層が薄く硬質な美しさ。
装飾的なのに無駄が一切ないというか。
ぜひ” Alma-Tadema frame”で検索してみてください。
素晴らしい額縁がいろいろと登場します。
アルマ=タデマは自分で額縁のデザインをしたそうですが
これだけの額縁を作る職人さん、一体どんな方だったのだろう。
富士美術館の額縁は比較的シンプルですが
もっと大きく凝った額縁がたくさんありますから。
なにせ超絶技巧の装飾で、一瞬目が点になります。
完璧主義という彼の人柄が額縁からも感じられるのです。
トーマス・モーという説もあり、でも彼は指物師だから
装飾はできなかったのではないか、という反論もあり。
Sir Lawrence Alma–Tadema
Sir がある通り、1899年に騎士の称号を得ました。
温かな人柄、完璧主義者、そして堅実なビジネスマンでもあったとか。
ロンドンには数々の額縁工房がありましたから
きっとそのうちのどこか、という有力な説もあって
いやぁもうアルマ=タデマの額縁研究だけで
充実した論文になりそうです。
額縁は歴史も材料技法もすべて面白いです。
そして作るのも修復するのも面白いのです。
額縁の海は広すぎて深すぎて、いやはや。
飽きるまで迷えばよろしい。 10月07日
「決まらない」だの「思いつかない」だの
ぶーぶー愚痴を言っておりましたが
(失礼いたしました。反省。)
ガタガタと日々過ごしているあいだに
どうやら通り過ぎたようです。
駄々をこねていた子供があるとき唐突に
「もう『迷う遊び』に飽きました。」に至って、
霧が晴れて、という感じ。
迷い期は辛いけれど、終わりが来ると知っている。
迷ったり悩んだりするのも、考えてみれば
迷ったり悩んだりする余裕(時間)が
あるのですからね・・・。
本人は必死だけど、俯瞰で観ればまだ甘い、
そんなものなんだろうと思います。
追い詰められたり諦めたりした訳ではなくて。
飽きるまで迷って、霧が晴れて、また迷って
それを繰り返しながら生きています。
きっと死ぬまで続くんだろうなぁ。
記録の方法と記憶のゆくえ 10月04日
気づけばそれなりの数の額縁を作りました。
デザイン画の形で記録保存してきましたけれど
きちんと統一したデータで残すべき、であります。
いや、今さらなのですけれども。
何年も前のと同じサイズと仕様の額縁を作ってほしい
なんてご依頼も当然あるわけですし。
ひとりで考えてひとりで作っているから
今まで済んでいただけで、これは良くないでしょう。
いや、今後もひとりの予定ですけれど、それはさておき。
記録の方法を模索中です。
いやほんと、今さらなのです・・・。
記憶はどんどん薄れていくのです。
明るい乙女の嫁入り支度。 10月02日
チューリップも含めて3点すべて額縁に納まりました。
昨年は暗い背景絵に黒い額縁ですっかり
根暗な乙女に迷走しておりました。
今年はちょっと反省いたしまして。
▲青空とお花と鼓笛隊、どうです、明るいでしょう!
▲のんきそうな鼓笛隊と
▲ルネッサンス時代の貴婦人です。
これら3点は、今年も今年とて暮の12月に行われる
「小さい絵」展に出品するべく準備しております。
気分は相変わらず「娘を嫁がせる母」でございます・・・。
「小さい絵」展の詳細は、またお知らせさせてください。
なんとドロ足とは! 9月30日
先日「額縁の作り方 22 」で
ドロ足のお話をしましたが、わたしは
「ドロ足」の名前の由来はわからないままでした。
ドロ足とは額縁の裏側に取り付ける材木で、
額縁が作品に対して高さ(厚さ)が低い場合
足す部分を指します。
▲金色の額縁本体より一段高くなっているところがドロ足。
この額縁は裏にグレーの紙を貼っています。
Atelier LAPIS で「ドロ足とはなんぞや」と話していたとき
MAさんがぽつりと「ドロ足って、昔は泥の木を
使って作ったのが最初だからって聞きましたよ」
と話してくださったのです。
さすがMAさん!額縁制作会社にお勤めなので
こうしたことにもお詳しいのです。
生徒さん方と「へぇぇ~~!!」が止まりませんでした。
泥の木について調べてみたら
日本に古くからあるヤナギ科の木で別名ドロヤナギ
成長が早いけれどあまり良い材ではないとのこと。
昔はマッチの軸木になっていたのですって。
(そういえばガサガサして折れやすい木だった記憶。)
現在はランバーコアの芯に使われることもあるそうです。
家具や建材には使えないけれど安価だから
裏側の高さ調整に使っていたということでしょうか。
え、じゃあもし泥の木とは違う材木を使う習慣だったら
たとえば「杉足」とか「桐足」なんて呼ばれていた
可能性があるということ??
現在は「ドロ足」の名称だけが残っていて
市販の額縁でも実際に泥の木を使うことはほとんどないでしょう。
とにもかくにも、ドロ足の名称由来が謎だったのは
わたしが単に「泥の木」を知らなかったから、に尽きますな。
ご存じの方にとっては「何をいまさら」ですしね。
大男が泥んこの足でドスドス歩く風景が(やめてほしい!)
いつも頭に思い浮かんでいたわたしです。
ドロ足はドロノキ・・・なるほど。
ひとつ学びました。
足りないもの 9月25日
最近「決まらない」ことが多い。
なにを見ても何を考えてもピンと来ません。
レストランでのメニューも、額縁のデザインも。
ううーむ。なぜじゃ。
インプット不足と決断力不足。
ひらめき、自信の不足もありそう。
それだけではなくて、なにか、こう・・・
瞬発力とでもいうのでしょうか。
重く足踏みしている気分です。
以前にもあった「この感じ」ですから、きっと脱出します。
ちょっと落ち着いて、深呼吸などして
それからお風呂にゆっくり入ろうかと思います。
おすすめの脱出方法がありましたら教えてください。
荻太郎先生「バレリーナ」の額装 9月23日
大学時代の先輩からいただいたご注文は
荻太郎先生の版画作品の額装、
frido-1 のデザインです。
荻太郎先生のゼミ員だった先輩の
思い出がたくさん詰まった作品を
額装させていただけるのはとても光栄です。
作品が納められた額縁の様子は
あまりご紹介できず、空っぽの額縁ばかりですが
今回は先輩に許可をいただいて、額装した姿を
こちらでご覧いただこうと思います。
ガラスをいれてしまうと反射が写ってしまい
せっかくの作品を正面から撮影できず。すみません。
荻先生はいつもお好みのデザインが決まっていて
額縁からも先生を感じられるのですが
今回は先輩がKANESEI額縁シリーズから
選んでくだいました。
荻先生の作品を見慣れている方には
ちょっとびっくりかもしれません。
荻先生の代表テーマのバレリーナ。
凛としたほほえみ、涼しい色使い。
額縁には艶消し純銀箔の明るい白さと
下地に使った赤ボーロの微かな温かみで
なかなか良い雰囲気に仕上がったと思います。
いかがでしょうか。
荻先生に見ていただくことが叶わないのが残念。
お許しいただけたか気になります。
厳しくも思いやりのある先生のご意見を
伺いたかったと思っています。
バルディーニの額縁 9月20日
ようやくここまで来ました
まだざくざく彫りですけれども。
Atelier LAPIS の講師時間にガサゴソと
作業しておりますが、生徒さん方にも
制作風景を見ていただけるのは良いかな
と思っております。
▲額縁の中に額縁。右横に木片を置き忘れて撮影。
だけどこの額縁。
四角い木地から曲線形を切り出す必要がありまして
・・・大変でした。
ちょっと分厚い木地なのです。
自宅の電動卓上糸鋸では対応できなくて
結局、手引きのノコギリで切り出し
ヤスリで仕上げるという、まったくもって
木地作りから「古典技法」になってしまいました。
気分だけはいにしえの職人。
いや、このありさまじゃ万年見習いですな。
断面はお見苦しくて披露できませんけれど
これから何とか整えます、はい。
ともあれ、部分的に荒くでも彫ってみると
なんとなくイメージが見えてきたように思います。
かわいい予感。
いかがでしょうか。
そうして決めたのは 9月18日
迷いに迷い、悩みに悩んだ(おおげさ)
チューリップ模写の額装ですが、
けっきょくベージュの別珍に納まりました。
▲額縁木枠は購入しました。
無難といえば無難であります。
でもまぁ、花びらの紫と補色の黄色系で
コントラストありつつもまとまったかしらん・・・
と思っております。
お部屋もぱっと明るくなります。
いかがでしょうか。
小さなかわいこちゃん3 やっぱりちまちま 9月13日
小さな祭壇型額縁をつくっています。
木地を彫って、ボローニャ石膏を塗り磨き、
ようやく金箔作業です。
以前に「祭壇型額縁をつくる」でご紹介した額縁は
これよりもうんと大きな額縁でしたけれども
大きくても小さくても、作業手順は同じでございます。
今回の小さな祭壇型額縁もまた、黄色ボーロを3層塗って
赤色ボーロを2層塗りました。
今回は少々厚めのボーロです。
ボーロの層が厚いと金がしっとりと仕上がり、
薄いボーロだとさっぱりシャープな雰囲気に。
デザインやお好みで試してみてください。
黄色と赤のボーロを塗る場合には
凹に赤を塗らないように注意します。
▲やはりボーロの色は独特で美しいのです。
金箔は、大きく切った箔片をばーんと置いてから
凹をこまかく繕うか、最初から小さな箔片を置くか。
わたしは額縁が大きかろうが小さかろうが
彫刻の凹凸には、結局小さく切ってちまちまと
箔を置くほうが上手くきれいに仕上がるようです。
これは作業する人それぞれ好みや得意があるでしょう。
磨り出しの仕上がりにも影響がありますから大切です。
さて、箔を置いたらその日のうちにメノウで磨きます。
▲め、目が!目が・・・! 反射光が眩しく刺さります。
なんだかお仏壇かお神輿かといった風情ですが
これからまだまだ装飾作業が続きます。
イタリアのルネッサンス風に仕上がる予定。
乞うご期待であります!
どうするどうする? 9月11日
ただいま悩んでおります。
どの色の布にしましょうか・・・。
数年前に完成したのに、むき出しでおいていた
チューリップのテンペラ模写、満を持して(?)
額縁におさめようと思うのですが、
バックの布の色が決まりませぬ。
ベージュは明るいけれど金と色が近いのです。
モスグリーンはシックだけど強すぎるでしょうか。
となると、この茶色がかったグレーかな。
でもちょっとぼやけていますか?
この絵が展示される「小さい絵」展は
12月ですので、冬使用の別珍で考えたいのです。
グレーかベージュか。
いまのところ2択まで絞られました・・・。
でも、白のモアレですっきりと!も良さそう。
どうしよう??
なんだかもう何が何だか分からなくなって
決まらない・・・そんな時は後日に持ち越し。
新たな気持ちで見直せばあっさり決まるものです。
どれがお好みですか?
吊金具の美 9月09日
先日ご紹介しました額縁本「CorniciXV-XVIIIsecolo」の
中央あたりには、吊金具を集めた写真が
掲載されておりまして、これが素敵なのです。
▲額縁本「CorniciXV-XVIIIsecolo」より
昨秋のフィレンツェ滞在で買った金具2種と
パオラが使っている金具、そして
KANESEIオリジナルで作ってもらった銅と真鍮2種と
形がそっくり同じような金具も載っています。
フィレンツェで--パオレッティさんのお店で--
買った2種とパオラの金具はどちらも鉄。
本に載っている古い金具も鉄ですので錆びています。
ちなみに日本で今使われている吊金具のほとんどは
錆びないステンレスです。
鉄とステンレス、だいぶお値段もちがいますが
腐食した鉄は額縁を安全に保持できませんからね。
▲上の2種がパオレッティさんで買ったもの、
下左がパオラのもの、その隣2つはKANESEIオリジナル。
だから日本が良くてイタリアがダメという話ではなく、
湿度の違い、習慣の違いなどあります。
そして恐らくですけれども、イタリアでも美術館等では
ステンレスの吊金具も使われているのではないでしょうか。
どの金属製の吊金具を使おうと、定期点検は
必要不可欠です、という前提でのお話です。
だけど美しさに限って言えば、まぁわたしの好みですが
ステンレスより鉄の金具の方が断然美しい!と思います。
錆びた鉄と古色の付いた額縁の組み合わせ、
力強さと物語を秘めていると思いませんか。
▲額縁本「CorniciXV-XVIIIsecolo」より
錆びた鉄の吊金具は装飾としてつけて、
裏からステンレスのしっかりした金具で保持する・・・
なんて本末転倒な吊金具の使い方も考えてしまいます。
小さい方を真鍮、大きい方を銅で作ってもらっています。
ステンレスの無機質なイメージは無くて
鉄より劣化スピードが遅い(と思っていますが)ので
実用も兼ねた「見せ金具」としてはとても気に入っております。
繰り返しますけれど、どの金属の吊金具を使おうと
定期点検は必要不可欠でございます!
小さなかわいこちゃん 2 9月04日
千洲額縁さんから届いた祭壇型額縁木地、
小さなかわいこちゃんでありますが、
さっそく制作開始です。
下描きをしまして
彫りまして
石膏を塗ります。
細かい彫刻部分に石膏を塗るには
筆選び、筆に含ませる石膏液の量の調整が大事です。
細目の丸筆を使って薄く作った石膏液を少な目に含ませ
絵の具を塗るような感じで丁寧に塗ります。
液溜りができたらそのつど筆でぬぐうこと。
さて次の作業は、例によって石膏磨きです。
晩夏とはいえ残暑の中、石膏磨きはいつにも増して辛い。
マスクは暑い、石膏粉は肌に貼り付く
エアコンを付けると風で粉が飛ぶ・・・
いやいや、ぐちを言っている場合ではありませぬ。
やりますぞ。
家人間の悩みは深い。 9月02日
額縁の制作も修復も、いつも家の作業部屋で
ひとりきりで行っています。
朝から晩まで作業をする日は一歩も家から出ず
会話をするのも家族とだけ、なんてこともあります。
先日友人と話していたときに
「あなた、家で仕事をしている時って
どのくらい歩いているの?」と聞かれて
「300歩くらい?180無い日もあったな。アハ!」
と言いましたら心配されてしまいました。
「笑ってないでせめて散歩くらいしなさい!」ですって。
たしかに。ハイ。
でも携帯電話の歩数計での計測ですものね、
数時間立ちっぱなしの作業もありますし、
トイレに携帯電話は持って行きませんし!
・・・でもその誤差はしょせん微々たるもの?
▲家の中から外を眺めるって良いものです・・・。
運動きらい、外出きらい、家大好き、
家にいて退屈することは全くない。
スケジュール帳に予定がびっしり詰まると
安心する人とうんざりする人がいますけれど
わたしは絶対的に後者なのであります。
いや、でも。運動か。
しなければねぇ。そうですよねぇ。
むーん・・・家の中で出来ること(家にいたい)
階段の上り下りを沢山とか、どうですかね?
・・・だめ?
小さなかわいこちゃん 8月28日
千洲額縁さんにお願いしていた木地が
満を持してやってきました。
祭壇型です。
千洲額縁さんにいくつか数をお願いしておりますが
諸事情ありまして、まずはひとつ先に仕上げて頂きました。
これまた小さくて、部品作りも組み立ても
とても面倒だったと思います。
大きくても小さくても、手間はあまり変わりませんから。
いやはや、小さくって可愛いですなぁ。
これから彫刻をして、全面に金箔を貼って
グラッフィートで装飾模様を入れます。
小さくてギッシリ!の予定でございます。
最後の審判の歯 8月26日
6月のおわりにお話ししました
親知らず問題。
(個人的なことで失礼いたします。)
抜くならいっそ早く抜いちゃおう、と
8月23日に右上の親知らずを抜きました。
真夏の抜歯はいやだ、なんて申しましたが
もう秋が見えてきましたしね。
1本の歯。たかが1本、されど1本。
口の奥がさびしいけれど
咬み合わせがすっきり落ち着きました。
そして期待した小顔にはなりませんでした。
イタリア語で親知らずは
Dente del giudizio.
giudizio を直訳すると審判、良識。
読んだところによると「良識の歯」と訳されるとか。
良識を持ったおとなになってから生える
つまり「親知らず」と似たような意味です。
だけど「審判の歯」のほうがイメージに近い。
おとなになって生えるのか審判を受ける。
そしてその歯は抜かれる運命なのか。
どいうような。
ちなみにミケランジェロの傑作「最後の審判」は
イタリア語で Giudizio Universale.
かつてイタリアで左下の親知らずを抜いて以来
わたしにとって「親知らず=『最後の審判』図」になっていて
青い背景のイエス様に「その歯、抜くべし。」(びしっ)と
宣告されているような気分になるのでした。
額装しました angelo-4 8月23日
フラ・アンジェリコの受胎告知図から
大天使ガブリエルをテンペラで模写し、
あわせて作った額縁 angelo-4 に納めて
ようやく完成いたしました。
黄金背景のテンペラ画、額縁も純金箔、
ライナー(絵と額縁の間)は紺色の別珍。
なかなか派手でございますね。
昨年2018年2月に模写した同じ絵は
angelo-3 と名付けた額縁に入れました。
ライナーはダークグレーです。
同じ絵を同じように模写したつもりですが
なんだか顔も服の陰影もいろいろ違いますね・・・。
ううーむ。
それはさておき。
額縁、ライナーが違うと雰囲気も変わります。
どちらがお好みでしょうか?
ダメ元だったけれど。 8月21日
先日おはなししました新規作成計画の額縁、
千洲額縁さんにお願いしました木地もとどき
いよいよ開始でございます。
▲下描きをしました。左右の木片はあとで取りつけます。
今回も「見切り発車」的な制作ですので
途中で修正を繰り返すことになるのです。
でもまぁ、これも訓練、練習です。
微妙に違う木地のつじつま合わせも必要ですから。
繰り返すうちにきっと上達するはず!
と自分に期待しつつ。
今回のモデルにした額縁の所蔵先である
フィレンツェのバルディーニ美術館に
制作場所、年代、サイズ等の問い合わせメールを
送ったのは7月のことですけれども
お返事はまだ来ません・・・。
届いていないのかな、それとも文章が悪かったかな。
きっと単に「いちいち答えていられないから」
なんて理由なのでしょう。
ヴァカンス前で忙しかったのでしょうし。
ダメ元で送ったメールでしたし。
・・・でもやっぱり、ちょっとガッカリしています。
S先生の額縁ー3 8月14日
S先生の額縁ご紹介は今日の3で最終回です。
まえの2点とは違い、銀と黒の装飾です。
外側寸法は330×240mm
銀箔の下には赤色ボーロ。
じんわりと浮いた錆が美しい趣を出しています。
吊金具は、もしかしたらヨーロッパで
買っていらしたものかもしれません。
この額縁の木地はおそらくキャンバス木枠、
F4号サイズでしょう。
ご自分のイメージする額縁を完成させるために
さまざまに工夫なさったのですね。
四隅にできた留め切れも美しい額縁、
そしていろいろと考えさせられる額縁です。
S先生の額縁3点は Atelier LAPIS に
飾らせて頂くことになりました。
生徒のみなさん、ぜひお手に取ってごらんください。
制作の参考に、そして励みにして頂けたらと思います。
S先生の額縁ー2 8月12日
先日からご紹介しておりますS先生の額縁ご紹介2は
石膏盛上げ(パスティリア)装飾の作品です。
サイズは外側202×202mm、小さな額縁ですが
これだけ細い線と立体感のある花と葉
そしてなにより端先の点々模様を入れるのは
とても難しく根気の要る作業です。
裏から見ると、この木地も手作り。
裏板はポリカーボネート、絶縁テープで端の処理
T字金具で留める・・・これは保存仕様額縁。
修復家の仕事と分かります。
S先生、どんなことを考えながら
この額縁を作っていらしたのでしょうか。
人気なあの子の額縁は 8月09日
フラ・アンジェリコの受胎告知図
なんとか完成いたしました。
合わせた額縁を作ります。
前回の模写で作ったのは angelo-3 で、
15世紀のトスカーナで作られた額縁をモデルに
薄いカマボコ型の木地に金箔、刻印で模様を入れました。
今回は刻印で模様を入れるのは同じ、
16世紀半ばイタリア・ピエモンテ州で作られた
素朴な雰囲気の額縁を参考にします。
▲70×80mmの板に描きました。
大天使、オリジナルより笑いすぎ。むむ。
▲模様を転写して、右のニードルで線を刻みます。
{ } の模様を入れるのは転写しながら中止に決めました。
我ながら笑ってしまうほど小さいものが好きです。
オウム2羽飛び立つ 8月07日
お正月にご注文を頂いて
気づいたら夏真っ盛りになってしまいました。
オウム2羽のテンペラ模写がようやく完成し
元気に飛び立って、もとい
お客様にお引渡しすることができました。
相変わらず小さな模写絵です。
プレイヤーズシガレットについていた
シガレットカード(と言うのですか)の絵から。
京都の骨董店から買ったアンティークのカードです。
▲お客様は「酉年に家族が増えて、それ以来鳥が好き!」
と話して下さいました。
オウム、漢字で書くと鸚鵡。
鳥偏なのは納得です。
「櫻」とつくりが一緒で「おう」
「武」のつくりで「む」ですって。
かっこいい漢字ですね。
これで覚えられた気がします。
新規作成計画 8月05日
ようやくサンソヴィーノ風額縁が
終わりましたので、さて次。
また隙間時間にガサゴソ作るつもりです。
フィレンツェの バルディーニ美術館で昨年
見た額縁(下の写真)を真似してみようと企んでいます。
上記のような見上げた写真を数枚撮りましたが
正確なサイズも凹凸も側面もよく分からない・・・。
でもまぁkanesei風味ということで!
想像力をたくましくいたします。
完成すればかわいいんじゃないかな〜 と思っております。
だいたいの寸法がでましたので
いそいそと千洲額縁さんに木地をお願いします。
この額縁--バルディーニ美術館所蔵の--は
いつどこで作られたのか。
わたしなりの目星は付けておりますけれど
果たして正しいのか不安でもあり。
美術館に問い合わせてみようと思います。
返答をいただけることを祈って!
S先生の額縁-1 8月02日
あるご縁があって、修復家S先生が作られた
古典技法の額縁を3点頂戴することになりました。
丁寧に、とても美しく仕上げられた額縁は
ご自分で楽しむためだけに作られた(と思う)のですが、
わたしの手元に届いたのも何か意味があるのかもしれない
と思い、こちらでご紹介することにしました。
195×135×30mm 小さいけれど重厚感があります。
ゴシック風のアーチのうえには
グラッフィート技法で植物模様が入っています。
左右で違うデザイン、曲線の流れが繊細です。
裏面から見れば、1枚の厚い杉材からすべて
くりぬき彫刻して作り上げてあることが分かります。
▲角もきれいに面取りされて「裏面も美しく」です。
どれだけ時間と手間がかかったことか。
その手間をたのしみながら作った様子が
手に取るように感じられる額縁です。
人魚の本当の姿はきっと 7月22日
銀座にある日動画廊から
毎年カレンダーを頂戴しておりますが、
ことし2019年7月のページには
レオナール・フジタの「人魚」という
作品が掲載されています。
メインには長い髪にヒトデを飾りにして
いたずらっぽく微笑む女性の上半身と
背景にお魚、そして人魚が描かれています。
この絵を見るたびに目を引かれるのが
背景の「人魚」のすがた。
この人魚、ものすごくリアルです。
ディズニーなどとは全く違います。
イワシくらいのサイズ感。
手がヒレになっていて髪は藻のよう。
大人なのか子どもなのかもわからない。
こんな人魚なら現実にいるかもしれない
と思わせるようなすがたです。
かわいいような不気味なような。
メインの女性は下半身が描かれていませんから
いわゆる人魚かどうかわかりません。
もしかしたら彼女は人間で、タイトルの「人魚」は
この人魚のことを指しているのかも?
と、思い始めています。
ななこ、もうひとつ 7月19日
nanakoori というなまえで作っている
額縁シリーズがあります。
なまえにある「斜子織」の織り模様を
絵の具で装飾しています。
いままで赤、マゼンタとつくりましたが
今回は黄色--ジャスミンティーのような
イメージの色--でつくっています。
すこし離れてみてみれば
籐で編んだカゴのような雰囲気にもなりました。
ひとマスずつ3本の線を引きます。
印刷したように均一に、濃淡も同じに、とは
しておりませんけれども、
この不揃いな感じを楽しんでいただければと思います。
行きつく思いはつまり 7月17日
もうひたすら独り言のような内容
おまけに長文でございます。
じぶんで書いたブログをたまに見返してみると
ふだん、自分がどんなことを考えながら
何をしているかが客観的に見えます。
たまに消してしまいたいページもあるけれど
それはもう、そのときのわたしの記録として
恥ずかしながらそのままにしています。
ブログで皆さんにお話していないことも考えたり
失意したり慌てたりしておりますが、
それらも含めて、ブログを見返すのはけっこう
大切なことのように思えています。
見返してつくづく思うのは、わたしはひとつのことを
ずっと続けて作業することを避けている・・・
というか「出来ない」のではないか?!
テンペラ模写は何枚も同時進行、
修復の作業をして乾くのを待つ、ということにして
(ほかにも手を入れるべき部分はあるけれど。)
新規作成の額縁デザインの下描きをして、
ちょっと休憩したら気分を変えて
ブログを書いたりメールの整理をしたりして、
「ああ、そうそう、あれもやらなきゃ」と思い出して
修復を待っている額縁の写真を確認しながら
修復計画を練ったり本を調べたり。
そうこうするうちに一日が終わる!というような。
この額縁を完成させてから、改めて次の額縁と
きっちりけじめをつけて・・・というふうには
していないのです。
そのつど作業に集中しておりますので
ひとつずつ順番に終える必要がある、とも思いませんが
これって、どうなんだろう。
効率が良いのか悪いのか。散漫な性格の問題か。
ある日は TokyoConservation で修復作業をし、
またある日はAtelier LAPISで講師をし、
まるで行き当たりばったりの流れ者のようです。
昨日観たテレビで、イタリアの男性が
「ずっと同じことをするのは嫌なんだ。」と
午前中は農作業、午後は海へ出て漁、
ひとりで気ままに、でも真剣に誠実に仕事をしていました。
そして彼の姿勢を見守り信じる家族、友人がいる。
この男性の気持ち、良く分かります。
なぜならわたしも同じような生活ですから。
そんな「気まま」言い換えれば「わがまま」と
言える仕事の仕方ができるのはひたすらに
周囲の方々の理解なのです。
ありがとうございます。
人気のあの子はどこにいる? 7月15日
またひとつ黄金背景の天使模写の
ご注文をいただき、準備を始めました。
80×70mmくらいの小さな板に
フラ・アンジェリコの受胎告知より
大天使ガブリエルです。
▲金箔を貼りました。照明が反射してギンギラギン。
黄金背景テンペラ画は描く前に金箔を貼ります。
絵具で描く部分には黄色いテープでマスキングしています。
これからメノウ棒で磨くところ。
この天使を模写するのも何度目になるのか。
愛らしくもりりしい横顔、やさしい微笑み、
とても人気なのもわかります。
フラ・アンジェリコは受胎告知の作品を
何点も描いていますけれど、
この子(大天使ですが)はわたしにとって
特に思い入れもあります。
1450年から1455年に描かれたといいますから
もうすぐ570年ですって。
570年前も今も、人々が惹かれる美しさは
普遍なのでございます。
Fra Angelico
Annunciatory Angel, between 1450 and 1455
だけど、まだ実物を見たことがありません!
告知を受け取るマリア様像とともにあるそう。
デトロイト、遠いけれどこの天使に会いに
いつか行きたいものです。
今年は明るい乙女に。 7月08日
今年も今年とて、小さなテンペラ画模写を
ちんまりと続けています。
いま描いているのはルネッサンス風の女性、
鼓笛隊、そしてインコ2羽。
インコの行先はもうすでに決まっています。
(半年以上お待ち頂いている!)
いつものように、4枚並べてあっち描いてこっち描いて。
青は青、赤は赤で同時進行なのです。
昨年つくったものは背景が暗いうえに額縁も暗くて、
でもモチーフや額縁デザインはメルヘンチックな
「暗黒の乙女風」でしたけれど
今年はもうすこし明るい方向でいきたいものだと
少々反省している次第です。
再会はいつもハラハラ 7月05日
いつも大変にお世話になっているお客様のところで
以前に作ったり修復した額縁に再会するとき
うれしいような、でも実はハラハラするような
複雑な心もちになります。
とくに、修復ではなく新しく作った額縁が
美しくライティングし展示されていると
大切にして頂いている喜び、安心もあるけれど
経年の変化が大変気がかりになります。
「おお~い、大丈夫か、元気かい??」と
娘を嫁に出した親心とでも言いましょうか。
いままでまだ問題がおきたことはありません。
(わたしが知る限りですが・・・。)
でもたまに、夜中にぱっと目が覚めて
「あれは大丈夫だろうか」などと思うこともあるのです。
お客様にお引き渡ししてそれっきり、
行方も分からなくなる額縁があるなかで
こうして度々様子を確認し、問題があれば
またわたしが--作った本人が--手入れできる
環境にあるのは、これもしあわせなことだと
思っています。
とは言え、わたしの目が黒いうちは
問題が起らないことが何よりいちばん。
美しく丈夫で長持ち、そんな額縁を目指します。
憧れの人に近づきたい 棟方志功とメガネ 6月28日
いま府中市美術館では「棟方志功展」が
開催されています。
先日トントコと観に行ってまいりました。
タイトルに「連作と大作で迫る版画の真髄」と
ありますように、いままで観たことが無かった
巨大な作品に圧倒されました。
大作とはいえ木版画なので、何枚もに分割して
版木が作られ刷られ、貼り合わせてあります。
それぞれ1枚ずつの墨の色の違いやつなぎ目のずれが
何とも言えない「美しさと迫力の大切な一味」でした。
その数日後に TokyoConservation の修復スタジオで
室長に「展覧会良かったですよ」と話したところ
「実はね・・・」と新しいメガネを見せてくださいました。
ツルの裏には「MUNAKATA」と。
とても美しく力強い形。男性向きですね。
棟方志功が黒縁メガネをかけていたのは有名ですが
そのオマージュでしょうか、こんなメガネがあるとは。
室長は以前から「棟方志功をとても尊敬している」と
話しながら、モノマネ(!)も披露してくださるのです。
このメガネをかけた室長、さらに棟方志功に
近づけるのではないでしょうか。
憧れる人の名前が入ったものがあれば
それは身近に置きたいですよねぇ。いいなぁ。
わたしは誰の何が欲しいかな、
ワイエス、バルテュス、有元利夫か・・・
フラ・アンジェリコ?
ふむ。
とうとうこの時が来た dente del giudizio 6月26日
数日前から、どうにもこうにも
上奥の歯茎が痛くて夜中に目が覚めてしまう。
歯みがきで出血する。食事も楽しくない。
これはいかん!と歯医者さんに駆け込みました。
歯槽膿漏か?歯がぐらぐらになっちゃう??
と戦々恐々でしたが、レントゲンなどの結果
親不知の影響でした。
なんと。
上あご左右に生えている親不知ですが、
生えた時からこの日が来ることは分かっていたはず。
いつか来る日とは思っていたけれど、本当に来ました。
抜いたほうが良いみたい。
夏の抜歯で暑さとの2重の苦しみに呻きたくない。
「じゃ、秋にはね」と看護師さん。
夏の間に覚悟を決めましょう。
冬に先延ばししないようにします。
と、いまのところは思っております!
ちなみにイタリア語で親不知の歯は
dente del giudizio といいます。
左下の親不知はフィレンツェの大学病院で
抜いて頂いたのでした。
遠い思い出・・・
ボーロの持つ魅力 6月19日
いま Atelier LAPIS のMさん制作中の
彫刻額縁が佳境を迎えております。
こつこつと丁寧に作り続けてきた木地に
銀箔を貼ろうということで準備を始めました。
石膏地に黒ボーロを塗ったのですが・・・
白い石膏地のときは可愛らしさが感じられましたが
黒にすると印象は一変します。
▲ボーロ塗り中。まだ白が透けていますが
このあと漆黒になりました。
これがもうあまりのカッコ良さにほれぼれ。
力強さと優しさを兼ね備えたような雰囲気です。
黒髪の精悍な青年、でも少年の面影も残る、というか!
ボーロ(箔下地)には伝統的に赤、黄色、黒があり
そのどれもがとても美しい色です。
粘土ですので土の暖かさが感じられます。
額縁に興味の無い友人も、ボーロの色を
褒めてくれたことがあったのを思い出します。
土系の顔料をニカワで溶いても何かが違う、
この雰囲気はやはりボーロ特有と言えるのでしょう。
以前から彩色にボーロを使うことも考えましたが
今回Mさんの額縁を見て、改めてボーロのもつ
色の美しさにハッとさせられました。
Mさん、銀箔をやめてボーロ仕上げにするか
現在ご検討中。
わたしもボーロ彩色の仕上げを考えてみよう・・・
問題はニスですな。いや、ワックスか。
フフフ。楽しくなってきました。
庭の謎 6月17日
最近、気になってしかたがないこと。
我が家のバジルとシソはプランターで育って
食卓では大いに役立ってくれております。
が、特に栄養豊富な土でもないのに
その大きさが・・・
バジルの葉はふつうサイズの4倍に大きくなり
シソにいたってはわたしの手より大きい。
ぎえー。
虫に食われ過ぎて闘争心が湧いたのか
(もっと大きく強くなってやる方針)
人に食われ過ぎてやけっぱちになったのか
(もっと硬くモジャって食べにくくなってやる方針)
謎でございます。
大きかろうが硬かろうが刻んで食べちゃいますけど。
その横で、我らがヒヤシンス軍団
時は満ちたと思われますぞ。
▲そろそろ掘り上げだぞ~覚悟しろ!
父さん! 6月10日
わたしにとっての「お父さん」像は
もっぱらテレビの中ではぐくまれました。
現実にも頼りになる父がおりますよ。
ドラマ「大草原の小さな家」の父・チャールズ
ドラマ「大地の子」の養父・陸徳志
アニメ「赤毛のアン」の養父(?)・マシュー
この3人の「お父さん」はみな
絶対的な愛情と強さをもっていて
波乱万丈の物語の中でもゆるぎません。
その愛情の深さ、思い出しても泣けるシーンが沢山。
これら「お父さん」を観ればいまだに
どこか安心してしまうのです。
6月8日土曜日の朝、とても懐かしい
メロディーが聞こえてきたと思ったら
「大草原の小さな家」リマスター版が
BS3で放送され始めたのです。
これからしばらくの間は毎週チャールズ父さんに
会えるかと思うと嬉しい。
娘ローラは「お父さん」ではなく「父さん」と呼ぶ。
画像はwikipediaよりお借りしました
それにしても幼い頃にテレビで見た父さんは
立派なオジサンでしたけれど、今となれば
案外若い父さん(俳優マイケル・ランドン)
だったのですね・・・。しみじみ。
セラミック砂で思い出す 6月05日
先日、おおきな画材店に買い出しに行きました。
必要なものをカゴに入れつつ
商品棚を端から端までじっくり見てみました。
以前から気になっていたのが、額縁に砂を付ける装飾。
フランスのバロック(ルイ14世)終わりから
ロココ(ルイ15世)スタイルによく見られます。
下の写真の中央を走る帯部分、粒々しているのは
砂の上に金箔が施されています。
▲写真中央あたり、ザラザラした部分に砂が使われています。
砂壁に金箔、のような感じ。
フィレンツェの学校で修復したときは、学校にあった砂
(どこの砂か、買ったか採集したかも聞かなかった)を
ニカワで貼りつけた記憶があります。
学校の砂も細目、中目、荒目と準備してありました。
ルイ14~15のスタイルで額縁を作るか・・・は別として
砂をつかったザラリとしたマチエールは面白いので
わたしも日本で使ってみたいと思って、時は流れ。
先日みつけたのはセラミックバルーンという商品です。
いわばセラミックで「作られた砂」。
これを使えば均一な粒で美しいマチエールが作れそうです。
▲加熱したタラコがグレーになったような・・・?
きっと以前から販売されていた材料でしょう。
今まで知らなかったなんて。
棚の端から端まで見てみた甲斐がありました。
「ほんとうの砂」の自然なばらつきは無いけれど
整ったザラザラ--変な表現だけれど--を
作ることができそうです。
セラミックの砂と聞いてなにか思い出しませんか?
「風の谷のナウシカ」を思い出しませんか・・・?
ユパ様ー!
ほんのり磨きの美 6月03日
先日ご覧いただいた花彫刻 fiore-4 を
作っていたときのお話。
古典技法の金箔置き(金箔貼り)は
メノウ石で磨き上げ、まるで金の塊りのような
奥深い輝きを出すのが醍醐味です。
正しい技術で箔を置き、正しいタイミングで磨けば
金箔はより強く密着し丈夫になります。
数μの厚さしかない金箔とは思えない美しさです。
そんな訳でして、金箔を磨くとなったら
わたしはもう「磨かずんば死」でした。
大げさ? まぁそうですね、でもそれくらい
「磨くと言ったら磨くのです!」と
真剣に丹念にしつこく磨き上げていました。
ですが、最近思うのです。
ギャンギャンに磨き上げた金は息苦しい。
確かに吸い込まれるように美しいけれど、
硬く隙が無さすぎるのではないか、と。
いままでの8割くらいの気持ちで磨いた額縁は
10割磨きの額縁よりやさしく軽く親しみが持てる。
押しつけがましさが減る。
艶消しとも違う美しさがあるようです。
「磨きゃ良いってもんじゃなんだよ、きみぃ!」
と額縁の神様に言われたような気がします。
ばっちり磨きの金が必要な額縁もあれば
ほんのり磨きの金が生きる額縁もある。
気づきました。
合わなければ合わせよう 5月22日
日本とイタリア、伝統を大切にするのは同じでも
金箔の規格サイズが違います。
とても小さなことだけど、わたしには大問題。
わたしが箔置きに使う道具はイタリア規格ですが
なにせ日本の金箔はイタリアの金箔より
2cm近くも大きいのですから。
イタリアの金箔1枚の幅に合わせた箔刷毛は
(箔を移動させる刷毛。日本の箔挟みの代わり)
日本の金箔1枚には小さいし、半分には大きい。
なので、日本の金箔半分サイズに合わせて
切っちまいます。
▲柔らかく弾力のある毛が厚紙の台紙に挟まれている。
リスの一種の動物の毛、とのことですが。
切り口を額縁模様のテープで保護して完成です。
おまけで繕い用の小さいサイズの刷毛も出来て
便利便利、一石二鳥でございますよ。
道具は使う対象に合わせて作られる。
使う対象が変われば道具も変わる。
合わなければ合わせちゃいましょう。
古典技法でひとりにひとつ 5月13日
古典技法ではニカワ、石膏液
箔下のボーロなど、とにかく湯煎します。
キッチンやら作業部屋のコイル式電熱器を
使っておりましたが、
キッチンは汚したくないし、電熱器は時間がかかる。
なんだか上手くいかない・・・でしたが。
とうとう最終兵器を見つけました。
商品名は「おりょうりケトルちょい鍋」
この間に発売された電気鍋です。
ずいぶん人気のようで、入荷するまで
しばらく待たされてしまいました。
直径18センチ、深さ7センチほどと
わたしの湯煎作業に最適な大きさで、
何が素晴らしいって40℃から100℃まで
好みの温度で保温できること。
ニカワを70度以下で保たねばならず
湯煎には気を使うのですが、
この鍋ならおまかせ放置が可能なのですもの。
密封できるフタが付いていますから
100℃にガーッと沸かして、シリコン粘土を
柔らかくしたりもできます。
仕事が終われば鍋だけ取り外し
まるっと水洗いもできちゃう。
すばらしく便利。
メーカーおすすめはチーズフォンデュや
お酒をお燗したり、もちろんひとり鍋など。
他にもいろいろ使いみちはありますよ。
古典技法でもひとりにひとつ、ちょい鍋。
あると便利です。
本当は奇数好き 5月10日
最近彫っていたのは fiore(花彫刻)
シンプルな花のモチーフです。
これはKANESEI始まりの頃から作っている
思い入れのあるデザインなのです。
昨年フィレンツェで買い足した新入り彫刻刀も活用し、
ほぼ№7のカーブ形シリーズで彫りました。
(1や9も使いましたけれども。)
いま持っている彫刻刀を見てみると、どうやら
わたしは№7,5,3のカーブが好きらしい。
№9, 11も持っている。でも№4,6は一本もない。
自分の手の動き、デザインの好みで
好きなカーブがあるのは分かります。
そして数字としてはなぜか6と8を好みますが、
彫刻刀に関しては奇数好き、と気づきました。
我ながら無意識の好み、面白いです。
今度は№5の彫刻刀を集めてみようかと思います。
レオナルドは言ったのか 5月08日
ことし2019年は我らがレオナルド・ダ・ヴィンチ
没後500年で、本国イタリアでは
たくさんの展覧会が開かれているようです。
5月2日の命日は大型連休中日
何とはなくレオナルドの画集を見ていました。
これは大切な友人から頂いた大切な本。
1949年にイギリスで出版されたものです。
いまの画集に比べれば鮮明さには欠けますが
パラフィン紙につつまれていて
紙の色や手ざわり、におい
小口は切り落とされていない手製本の様子が
「正しい本」の姿のように思います。
本好きが作って本好きの手を渡ってきた本
なのです、きっと。
▲ページの端が切りそろえて無い。それが良い!
レオナルドのデッサン
セリフを言わせたくなるような絵もあります。
感情の発露「わぁ!」「おおお・・・」など聞こえてきそう。
▲もの言いたげな人物たち。ルーブル美術館蔵
でも彼の素描からは北斎漫画のような笑いの要素は
ほとんど感じません。
描くものに笑いを入れる必要はないけれど
作者の性格は少なからず表れるもの。
レオナルドは冗談を言ったりふざけたり
したのでしょうかね?
▲猫と龍の練習。観察眼は鋭く几帳面に描かれている。
でもまんが的要素は無く猫はあまりかわいくない。
イギリス・ウィンザー ロイヤルライブラリー所蔵
レオナルドのくり出すオヤジギャグに
サライがうんざりしていたり・・・
いやいやまさか、想像できません!
こちらの冗談には一緒に楽しく笑ってくれるけれど
自ら冗談やオヤジギャグを言うことはない。
素描を見て、そんな人だったように思います。
妄想叱咤激励 5月03日
ことしのゴールデンウィーク
法事で広島へ行くほかは、友人と会う程度で
家におります。
連休中はふだんの外出――Atelier LAPIS や
修復スタジオ、習い事――がお休みなので
家での作業に集中してせっせと進めました。
ことしのスローガン、スピードアップですから!
そうは言っても目標達成はなかなか大変。
根が怠け者で仕事が遅いですからね、
スピードアップしてようやく普通に近づく。
「自覚しているならさっさとしなさい!」
「わたしはこんなにがんばっていますよ」
とKANESEI福の神、モッコウバラの花に叱られ
(正確には叱られた気分。いつもの妄想。)
ハイ、がんばります・・・。
イタリアに行きたいなぁなんて呑気なことを考えるのは
目の前のご注文の山を終わらせてからにしなさいよ、と
自分につっこみながらの連休でございます。
モッコウバラはことしも見事な満開でした。
サンソヴィーノチャレンジ つづき⑤ 4月24日
いつから作りはじめたのかもはや
記憶がさだかでないサンソヴィーノ額縁、
調べてみたら昨年2018年6月でした。
構想時間もふくめるとほぼ1年。
やれやれでございます。
前回は金箔を貼っている作業を
ご覧いただいたのですが、今日は
いよいよ満を持して(?)仕上げです。
白木部分には水性ステインという
木部着色剤を塗ります。
磨いた金と茶色のコントラストが生々しい。
そして古色付け。
叩いて凹ませ、磨り出して下地の赤を見せて、
茶色のワックスを塗り込み「ほこりパウダー」をはたく。
満身創痍の身に油と粉塵を塗りたくるという
まさに「額縁の拷問」、可哀想ですけれど
心を鬼にして。
さて、汚しを付けたらパウダーがなじみ
ワックスが乾くまでしばらく寝かせます。
やわらかいウエスで磨いて、足りなければ
同じ作業を繰り返し、好みの「古さ」を表現します。
完成目前です。
雄牛の胆汁 なぜ今も 4月17日
雄牛の胆汁を買いました。
ご存知の方もいらっしゃると
思いますけれども、これは
水彩画やテンペラで使う「はじき防止剤」
つまり界面活性剤の働きをします。
磨き上げた金箔の上に卵黄テンペラで
彩色するとき、絵具が金にはじかれて
定着しませんが、この液を数滴いれると
伸びが良くなり、しっかり定着してくれます。
とても役に立つのです。
これがあればグラッフィート装飾もスイスイ。
ルネッサンス初期の技法書にも載っています。
この液体を絵具に混ぜてみようと思った
最初の人は素晴らしい発想と勇気の持ち主。
いまは合成で無色透明無臭、
商品名だけ「雄牛の胆汁」として
販売されているものもあるようです。
でも今回わたしが購入しましたのは
イタリアのマイメリ社製で、
精製されているけれどまさに牛の胆汁。
薄黄色でちょっとした臓物臭もあります。
浮遊物もちらほらと。(何かは知りたくない・・・)
いまとなってはわざわざ牛の胆汁を買わずとも
合成の方が良いのかもしれませんが
古典技法を常とするKANESEIとしては
古い処方の物が手に入るならば
やぶさかではありません。
臭いけど。
ちなみに上の写真、左にあるのは
ずいぶん昔にフィレンツェの画材店
ゼッキで買ったものです。
経年ですこし色が濃くなりましたが
そして何やら白く沈殿していますが
買った当初から濃い茶色、そして
その臭いたるやもう苦くて塩っぱい
強烈な異臭を発していました。
思い出してもグワーッときます。
ゼッキ製のフタを開ける勇気は
もはやありません。
でも「謎の毒薬」風の枯れた佇まいは
なんだか気に入っています。
「これを飲むと手がヒヅメになるよ
フフフ・・・」とかなんとか。
飲み物に混ぜてもあまりに臭くて
すぐにバレそうであります。
貼るのか置くのか問題 4月12日
以前「祭壇型額縁をつくる 8 」でも
お話したのですけれど、
金箔は額縁に「貼る」のか「置く」のか。
独り言のような内容でございます。が、
留学を終えて帰国当時からなんとな~~~く
気になり続けている貼るのか置くのか問題。
言い方ひとつではありますが、でも
言い方って大切ですから。
日本の額縁制作の世界では、箔は
「貼る」ではなく「置く」と表現します。
日本の額縁創成期は漆工の職人さん方の
活躍が多かったそうなので、
そのまま伝統的な「箔置き」という言葉が
使われ続けてきたのではないでしょうか。
一方、KANESEIのお客様などからは
「金箔が貼ってあるのですか」とのお言葉が
多いところから鑑みるに、日本語では
一般的に金箔は「貼る」のでしょう。
薄い紙状のものをくっつけるのは「貼る」です。
さて、イタリアの職人さんはなんと言うか。
Io metto foglia d’oro. わたしは金箔を置く。
「置く」“mettere”という動詞を使います。
やっぱり「箔を置く」のですよ。
なんでだろう。
どうしてでしょうね??
実際に西洋古典技法で箔の作業をしてみれば
たしかに「箔を置く」という感覚ではあります。
おそらく漆工の世界の感覚でも、箔は
置くと表現するのが相応しいのでしょう。
極めて薄い金箔を、日本は竹挟みではさんで、
あるいは透けるような和紙につけて、
イタリアは繊細な刷毛に静電気でつけて持ち上げて、
対象のもの――漆器や仏像、額縁――に
フンワリと置いて、そしてそっと押さえる。
「箔を貼る」は完成品を見ている人の感覚
「箔を置く」は製作の作業をしている人の感覚
から出てくる表現、でしょうか。
となると、他のアジアの国で漆工に携わる職人さん、
ロシアのイコン制作の方々、
ポーセレンや写本の世界などでは
どう表現しているのか知りたいのです。
む~ん・・・箔を「置いて」いるような気がする。
辞書や翻訳サイトでは出てこない
いわば現場の表現ですからね、
いつか職人さんご本人にお聞きするチャンスが
あれば面白いなぁ、と思っています。
まるい。 4月10日
我が家のまえには立派な桜の木があって
桜吹雪が庭にも道にもいっぱい舞います。
それはそれはうつくしい。
あれ、花びらの跡がまるい。
下はマンホール。
たくさん集まるとピンクもより濃く華やかです。
午後の強い風のあと、もう消えていました。
ほんのしばらくだけの、まるくきれいな風景でした。
型取り大会 今年も幕開け 3月27日
額縁の装飾につかうオーナメントを
たくさん型取りしました。
まずは型をつくるところから開始。
昨年秋にフィレンツェで買った
引出しツマミも仲間入りです。
変なマーブル色になっていますけれども
これは「おゆまる」、白は「型取りくん」
(どちらも商品名ですが覚えやすい。)
どちらもシリコン粘土というのでしょうか、
熱を加えると柔らかくなり、冷えると
弾力がありつつも硬くなるものです。
繰り返し使えるのでとても便利。
できあがった型に石膏を流し込んだらしばし待機。
固まって型から外せばオーナメント完成です。
▲完全に乾くまでしばらく待ちます。
自作の型に加えて、先日ネット通販で
購入したシリコンモールドでも作りました。
今はこんな型も売っているのですねぇ。
▲海外から取り寄せたシリコンモールド。
期待していた雰囲気とは違いました・・・。
かなり細かくて複雑な模様で気泡が入り易い。
でもこれはこれでかわいい。
気泡はあとでパテ埋めします。
ううむ、試した結果、いま使っている石膏は
メーカー推奨量よりほんの少しだけ水多めの方が
気泡ができにくいような気がします。
完成したオーナメントを並べて干します。
落雁のようで美味しそうですな。
額縁に使ったり、小箱に使ったり。
クリスマスのオーナメントも作れそう。
まずはリボン4つを使って額縁制作です。
どこでだれに習おうと 3月20日
昨年暮にAtelier LAPIS にご入会くださった
Aさんとはじめてお目にかかったときのこと。
古典技法の本場である欧州ご出身のAさんが
日本で日本人から古典技法額縁制作を教わる・・・
Aさんがご見学に来て下さったとき、わたしは
「日本で日本人から古典技法額縁制作を習うのは
嫌じゃありませんか」と聞いたのです。
そのことについてAさんは
「日本人だからって日本の文化すべてを
知っている訳でもないでしょう?
欧州人皆が古典技法額縁に詳しいわけでも
興味を持っているわけでもないのと同じ。
興味を持って勉強した人が教えているなら
わたしはそこに行って学ぶ。
学ぶのに場所と人種は関係ない。」
と話して下さいました。
そうですか。
そうですよね。
「日本人なのにイタリア古典技法
なんてわざわざ言って、おこがましい」
「せっかく文化豊かな日本に生まれ育ったのに
なぜわざわざイタリア古典技法なんだ」とわたしは
どこかうしろめたさを持っていたと気づきました。
だから欧州ご出身のAさんがいらしたとき
「わたしなんかで良いのでしょうか」
などと思ったのでした。
そもそもお時間を作って見学に来てくださった方に
「嫌じゃないか」もなにもありませんよね。
嫌じゃないから来てくださっているのに。
ばかばかしい考えだと、
振り返って考えてみればすぐに分かることです。
なぜうしろめたさを持ち続けていたのか
もはや自分でも分からないのですけれど、
生まれてこの方、一事が万事この調子なのです。
これはもうわたし生来のいじけた性格ですね。
イジイジジットリとしていると
できあがる額縁もいじけてしまう。
LAPIS に来て下さる生徒さん
額縁をご注文くださる方々にも失礼です。
明るく堂々とした額縁をつくるために
いい加減もうすこし明るく生きようと思います。
などと、思い至った春です。
いったい何年生きてきたんだ、ですって?
ハハハ・・・いやはや。
なんともかんともお恥ずかしい限り。
一緒にお笑いください。
難しさはおなじこと。 3月13日
彫刻刀研ぎ、相変わらずの課題でございます。
台所に砥石をひっぱり出してきては
ガサゴソと研いでおりましたが
この度「電動刃物研ぎ機」なるものを
使ってみました。
▲構造としてはかなりシンプルな機械。
スイッチオン!
手前の金属板に手をのせて刀を持ち固定。
奥のカップから水が滴下されます。
ドーナツ状の砥石が反時計回りにぐるぐる回転。
すると軽快な音とともに刃が研がれていく・・・
のですが。
円盤が回るということは、
円の外側と内側で回転スピードが違う。
円に刃を当てる位置、向き、角度で
研ぎ具合がまったく変わるのですね。
おまけに思ったより回転が速いので
あっっ と思ったらやりすぎたりして。
砥石のどこに刃を当てるか、
刃を動かすタイミング、
自分の手のクセ、力加減、
滴下する水の量、そして
刃と砥石のベストな角度を掴むコツ。
これらを理解して身につける必要あり。
素人としては変速機能が欲しい!
手で研ぐには練習が必要だけれど
機械で研ぐにもやはり練習が必要でした。
ちゃちゃっと簡単に手早くギラギラ刃物に!
なんて道はありませんのでした・・・。
という訳で、しばらく手で研ぎつつ
機械の練習もしようと思います。
機械が上手に使えれば時短は確実ですからね。
じつはこの東芝以外にもいくつか
電動研ぎ機が手元にあるのです。
ふむっ!と小鼻を膨らませた土曜日でした。
わざわざ作るもの 3月08日
このジャムの空き瓶に入っているのは
埃、ホコリです。
とは言えニセモノホコリ、できたてほやほや。
古色、つまりアンティーク風の仕上げや
古い額縁の修復にはかかせません。
パウダーを調合して作ります。
まさか本当のホコリは使えませんからね。
イメージするのは掃除機を掃除したときに
最後に出てくる細かいパウダーホコリです。
あの本物のホコリになにが含まれているか
想像したくないし見たくもないけれど
色のイメージだけはしっかり覚えました。
グレーにすこし茶色が感じられるような
微妙な色味を目指します。
これは「基本のホコリ」で、これをさらに
濃くしたり薄くしたり色味を変えたりして
額縁それぞれに合わせてそのつど調整します。
ホコリ色も、昨年秋に行ったフィレンツェで
パオラの「ホコリ」を見てから改めて
自分なりに調合しなおしました。
小さな変化、でもわたしにとっては
大きな変化なのであります・・・。
手紙 3月01日
ブログ、時代遅れなのですかね。
今はさまざまなSNSがあって
手軽に情報発信ができるけれど。
写真だけでは伝えきれないこともあるし
わたしには140文字では足りないのです。
「diario」日記と称しながらも
手紙のようなこのブログは、まだ
ここで続けていこうと思います。
ご覧くださってありがとうございます。
美しい道具を使いたい 2 2月13日
先日ご覧いただいた彫刻用の木槌は
じつは2本作ってもらったのでした。
重いのと軽いの。使い分けができます。
その重い方に金箔を貼ってみました。
祭壇型額縁の作業中ですが、ちょっと遊び。
ひとまず金箔を磨いただけですけれど。
わー、かわいーい。
もう完全に自己満足の世界でございます。
ムダな装飾?
いえいえ、そんなことはありません。
古典技法の額縁制作もそうですが
木彫にもさまざまな道具が使われます。
日々使う道具ですので、徐々に手になじんで
自分の分身のような、手の延長のような
大切なものになっていきます。
そんな道具は、できれば美しいものが好ましい。
美しい道具を使えば美しいものが出来る
とは言えません!・・・けれど
美しい道具を手に取った時に感じる
ふとした穏やかで気持ちの良い心が
わたしの手を通して作るものに反映されたら、
と思います。
手のひらサイズの小さい絵展 吉祥寺にて 2月09日
昨年暮の池袋東武百貨店につづきまして
2月後半に東急吉祥寺店でも
「手のひらサイズの小さい絵展」が
開催されます。
ギルランダイオの少女像模写
そしてクリヴェッリの花の模写
2点を出品いたします。
お近くにお出かけがありましたら
どうぞお立ち寄りくださいますよう
お願いいたします。
サンソヴィーノチャレンジ つづき④ 1月31日
もうお忘れかと思いますが、
サンソヴィーノ額縁の制作は 続いております。
「いい加減に終わらせなさい!」との
お声が聞こえてくるようですので
そして今年のKANESEIスローガン
「スピードアップ」に則りまして
迅速に完成させる意気込みでございます。
という訳でして、ようやく金箔です。
この額縁は彫刻が入り組んでいますし
箔は部分的に置きますので 面倒な様に感じますが、
箔部分は平らな面が多く帯状ですから
唸らずに箔置きが出来ます。
次回は箔をメノウで磨きあげた
ピカピカの金をご覧にいれます!
完成まであと少しでございます・・・。
道具には合わせて作られた道具がある。 1月24日
わたしが日々使っている彫刻刀は
スイスのpfeil社製のシリーズで、
木槌で打って使えるのが特徴です。
いままで日本の木槌(キヅチ)、
いわゆるカナヅチと同じ形状で木製のものを
使っていたのですが、ようやく
ヨーロッパで彫刻に使われている
縦型と言うのでしょうか、そんな
木槌を手に入れました。
下の写真は左が Atelier LAPIS にある
筒井先生が揃えてくださったpfeil社の木槌、
右は作ってもらったわたしの木槌です。
ずいぶん前からLAPISにあることは知っていました。
「へんな形、使い勝手はどうなんだろう」と
長い間眺めていたのですが、使ってみたら
まぁなんと便利なのでしょうか。
手元を見ずに打ってもきちんと当たるし
木槌の重心が軸の延長上にあるので
振るのが楽なのです。
さっそく「マイ木槌」をお願いしたのでした。
なるほどなぁ、ヨーロッパの彫刻刀には
ヨーロッパの木槌が合うのですなぁ。
そして日本の鑿(のみ)にはきっと日本の木槌で
打つのが一番良いようになっているのですね。
彫刻刀(鑿)のおしりの形状や重さそれぞれ
違いがありますから。
合うように作られて何百年も使われているのですから
当然といえば当然なのですけれど。
真新しい木槌、これから使い込んで
凹みや艶が出てきてくれるのが楽しみです。
古色再考 やっぱりそうだった 1月21日
ここのところお話しております古色、
つまりアンティーク風の仕上げについて
しつこく考えている・・・といいますか
ふとした時に思い出し続けています。
「もう古色話は飽きました」とおっしゃるのも
重々承知なのですけれども、あとすこし
おつきあいくださいませ。
メディチ家所蔵の豪華絢爛な額縁は
500年経っても壊れていないし汚れていない。
金はうつくしく磨き上げて完成されていて
いまもその状態が保たれています。
ずいぶん前から気になっていたことに
「古色仕上げは昔からあったのか」なのですが
今回フィレンツェの旅で改めて理解できた気がします。
ルネッサンス時代には金箔をほどこした額縁に
古色仕上げはあり得なかった、ということです。
蝋燭の灯る薄暗がりで輝かすために施す金を、
なぜわざわざ汚したり古く見せる必要がある??
▲同じデザインの額縁。左が金そのままの輝き、右が古色つき。
輝きも色も全く違う。
古色仕上げの額縁が作られるようになったのは
せいぜいここ200年くらいなのかもしれません。
建築技術が高くなって窓の大きな家が出来て
室内がとても明るくなった。
教会だけでなく家で絵画を楽しむようになった。
蝋燭からランプ、電灯になって・・・
人々の生活も考え方も好みも、幅が広がった。
そうして額縁装飾の幅も広がった、
ということなのではないでしょうか。
そうそう、
古い金箔の輝きを再現する方法、
ひとつの案を思い浮かべています。
近々にも試してみなければ。
乞うご期待!でございます。